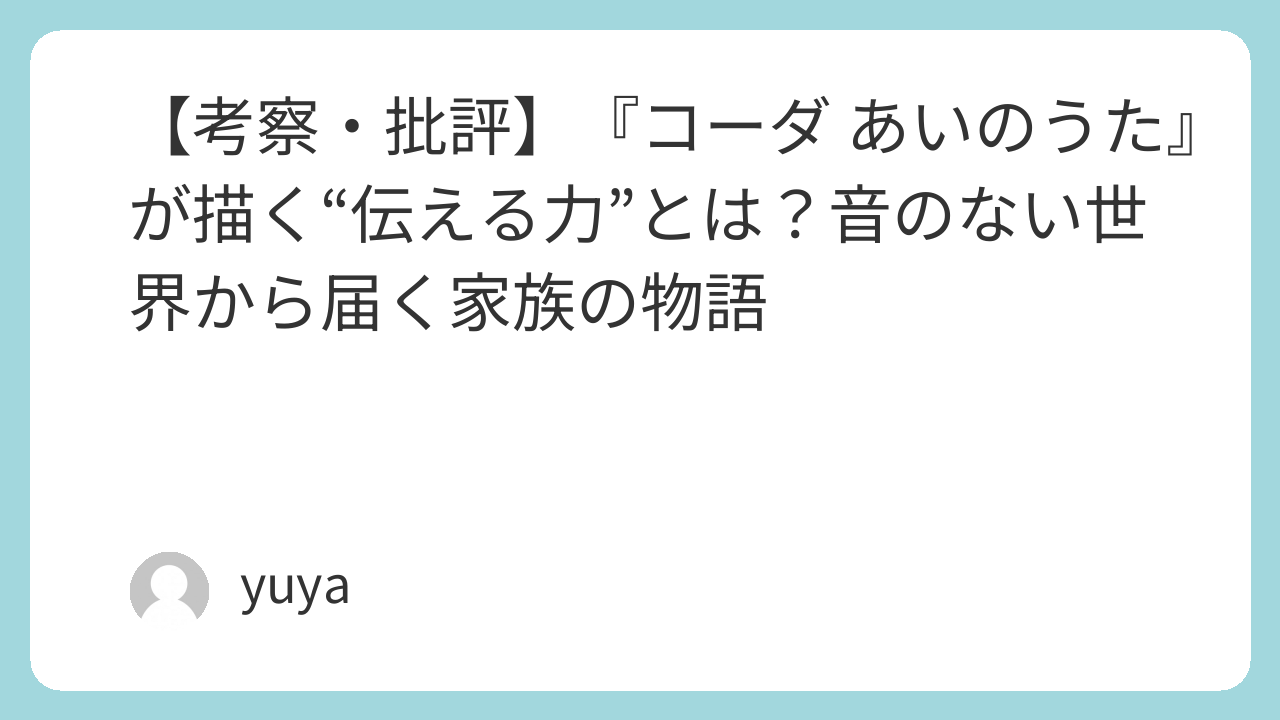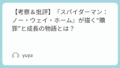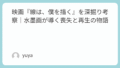2021年に公開された映画『コーダ あいのうた』は、ろう者の家族の中で唯一耳が聴こえる少女ルビーが、音楽の夢と家族との絆の狭間で揺れる姿を描いた感動作です。原作はフランス映画『エール!』であり、本作はそのハリウッドリメイク作品としても注目されました。
本記事では、単なる感動の物語に留まらず、映画的手法や象徴性、社会的テーマにまで踏み込んだ「考察」と「批評」の視点から、『コーダ あいのうた』を多角的に読み解いていきます。
聴こえない世界と手話表現 ― 音から視覚への転換
本作の最大の特徴の一つは、手話を主なコミュニケーション手段とする「ろう文化」が物語の中核にあることです。音が聴こえない世界に生きる家族が、視覚的な手話で日常を過ごす姿は、普段聴覚に頼って生活している観客にとっては新鮮であり、同時に多くの気づきを与えます。
監督はろう者のキャストを起用することでリアリティを持たせ、音声言語とは異なる「視覚の言語」としての手話を映画表現の一部として巧みに取り入れました。音のない「静寂」のシーンでは、逆に観客の感覚が研ぎ澄まされ、登場人物の呼吸や目線、手の動きが雄弁に語ります。これは、音を排したからこそ成立する“映画ならではの演出”といえるでしょう。
「伝える」ことの意味と葛藤 ― 歌・手話・沈黙の間で
ルビーが歌に夢中になる一方で、彼女の家族はその「音」を理解できません。ここに、音を媒介とするコミュニケーションと、手話による非音声の伝達との間のズレが生まれます。
特に象徴的なのが、ルビーの合唱コンサートを聴きに来た両親のシーン。音の聞こえない彼らは、他の観客の反応からしかその歌声の良し悪しを判断できません。その瞬間、彼らがどれほど日常的に「情報」から断絶されているかを観客は思い知ることになります。
しかしルビーが家族のために歌詞を手話で届ける場面では、手話と歌が一体となり、音を越えた深い「伝達」が実現されます。この融合は、音楽=音という固定観念を揺るがすものであり、「伝える」という行為の本質を静かに問いかけてきます。
家族の距離とすれ違い ― 衝突・理解・折り合い
『コーダ あいのうた』の家族描写は、単なる理想的な家族愛ではなく、リアルな“すれ違い”を丹念に描いています。特にルビーと両親との間にある「進路選択」をめぐる葛藤は、多くの若者が抱える普遍的なテーマとも重なります。
ルビーが音楽の道に進もうとすることは、家族にとって「理解しえない」領域への挑戦でもあります。彼女にとっては自己実現でありながら、家族にとっては「自分たちを置き去りにする行為」にも見える。ここに生まれる感情の断絶は、親の期待や依存、子の自立という複雑な構造を反映しています。
最終的に、家族はルビーの夢を理解し、送り出す選択をしますが、それは一夜にして起きた奇跡ではなく、積み重ねられた衝突と対話の結果であることが描写されます。
象徴モチーフと映像構造 ― 海・湖・両側性が語るもの
本作では「海」「湖」「魚市場」などの自然や風景が、象徴的に配置されています。特に海は、広大で開かれた未来を象徴する一方、家族にとっては生業であり、ルビーを縛る存在でもあります。
また、劇中で歌われる「Both Sides Now(青春の光と影)」は、まさにこの映画全体のテーマを端的に表現しています。「両側から見る」ことの大切さ——音と無音、夢と現実、聴者とろう者。それぞれの視点を持ち寄ることで初めて見えてくる真実があります。
映像表現も、こうした「両義性」を巧みに取り入れています。音のあるシーンとないシーンのコントラスト、視覚と聴覚の交差は、単なる感情喚起を越えた映画的メッセージとして機能しています。
オリジナル版(『エール!』)との比較と映画的技巧
原作『エール!』との比較において、『コーダ あいのうた』は文化背景や演出の細部を巧みにローカライズしながら、よりエモーショナルで洗練された作品に仕上げられています。
たとえば、アメリカ版では音のない場面の使い方により重きが置かれており、無音による“共感の装置”として機能しています。またキャスティング面でも、ろう者の役を実際のろう者俳優が演じることでリアリティと社会的意義が増し、単なる感動ドラマに留まらない社会的広がりを持たせました。
リメイクでありながら、「音を使わないことで音を伝える」というパラドックス的な手法に挑んだ点は、批評的にも高く評価されるべきポイントでしょう。
Key Takeaway
『コーダ あいのうた』は、耳が聴こえる/聴こえないという分断を超えて、「伝えることの本質」を静かに、力強く訴えかける作品です。手話と歌、音と沈黙、家族と夢。相反するように見える要素が丁寧に織り込まれ、私たちに“他者の立場でものを見る”ことの大切さを教えてくれます。この作品は、ただの感動ドラマではなく、豊かな「考察」に耐えうる現代的な映画体験なのです。