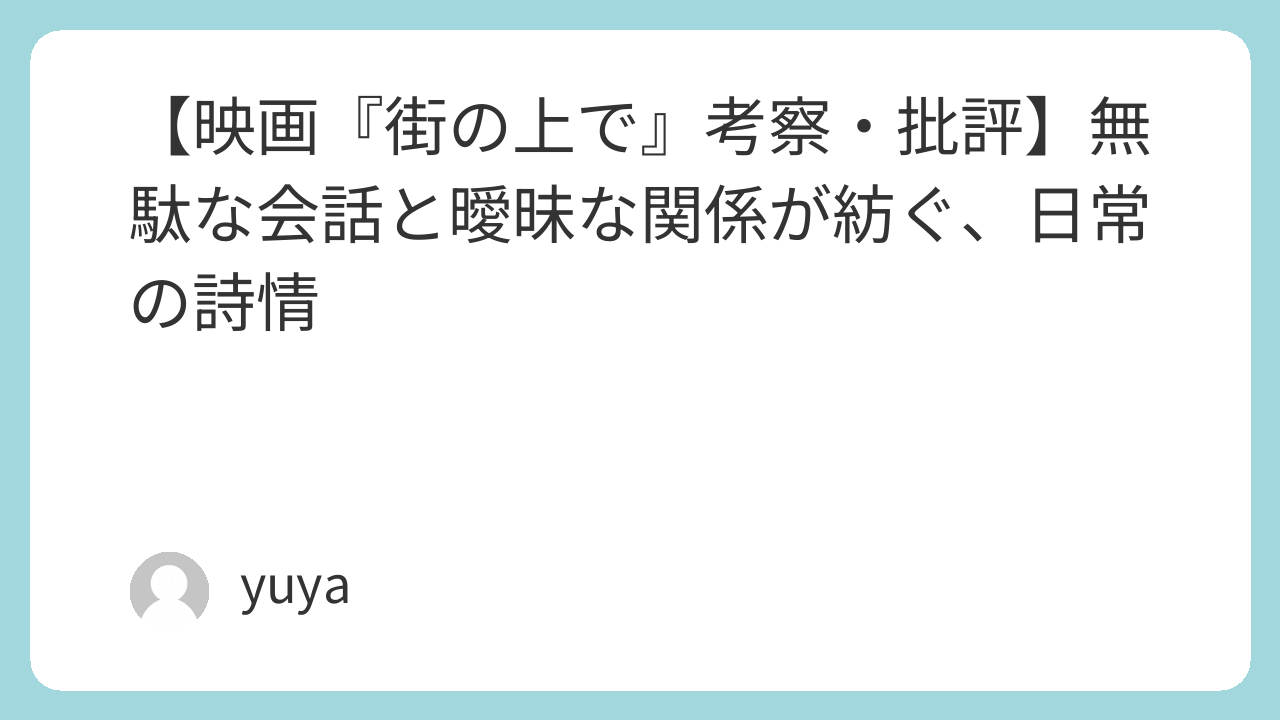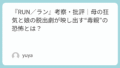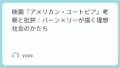今泉力哉監督による映画『街の上で』(2021年)は、下北沢という街に暮らす青年・荒川青を中心に、彼を取り巻く複数の女性たちとの関わりを、柔らかな時間の流れのなかで描き出します。この作品が提示するのは、物語性よりもむしろ“何も起こらないこと”の豊かさ、会話の無駄、視線の揺れ、空間の手触りです。
本記事では、検索キーワード、特に批評性の高い観点を中心に、この作品を掘り下げていきます。
「会話の無駄」と〈間〉──日常の余白を映す語り手としての本作
『街の上で』の最大の特徴は、「事件」が起こらないことにあります。恋愛の劇的な展開もなければ、人生を変えるような衝撃も訪れません。代わりにあるのは、何気ない会話、取り留めのないやりとり――たとえば古着屋での会話、別れ話の途中での雑談、そして無言で共に過ごす時間。
これらの“無駄”な時間やセリフは、今泉監督が繰り返し描いてきた「日常の〈間〉」の美学そのものです。実際、観客はその“間”のなかにこそ、登場人物の心理の揺れや人間関係の質感を感じ取ることになります。
このように、“無意味”に見えるものの中にある意味を汲み取る力を試されるのが、『街の上で』という映画の本質です。
下北沢という街と空間――場所性が紡ぐ登場人物の関係性
本作のもう一つの主役は、「下北沢」という街そのものです。再開発が進むこの街は、劇中では変わりゆく空気と、変わらない日常が同居する舞台として機能しています。
カメラはしばしば街の風景を長回しで捉え、人物と空間との関係性を丁寧に描写します。たとえば商店街の一角での待ち合わせシーンでは、背景に映る通行人や看板がそのまま生活感を醸し出し、「作られた映画セット」ではないリアルな街の息遣いが伝わってきます。
青の移動=街の中を歩くことは、まるで“散策”という形式をとった心の揺れのメタファーでもあります。都市空間と個人の心理がリンクしている点も、本作の隠れた魅力といえるでしょう。
恋愛/友情のあわい:境界を揺らす登場人物たちの関係性
本作の登場人物たちの関係性は、極めて曖昧です。青はかつての恋人・雪と別れた直後にもかかわらず、新たに出会う女性たち(小さな映画の監督、古着屋の客など)と微妙な距離を保ちつつ交流を深めます。
ここでは明確な「恋愛関係」も「友情」も明言されることなく、ただ言葉と視線と沈黙だけが積み重ねられていきます。この曖昧さこそが、現代の都市生活における人間関係の実相を反映しているとも言えます。
恋愛と友情の境界が溶け合うような感覚。それは、関係性を“定義”することではなく、“経験”することに重きが置かれた世界観です。
映画というフィクション性と視線の技法──作為性をあえて露わにする演出
作中では、青が自主映画の撮影に参加するというメタ構造が挿入されます。このエピソードによって、観客は「映画の中の映画」という二重の視点に立たされることになります。
さらに、登場人物がふとカメラの方を見たり、自然な演技のなかにどこか“演じている”という意識が滲む場面もあり、今泉監督の演出はあえて映画というフィクション性を露呈させています。
これは、観客に対し「これはあくまで作られた物語である」という距離感を示すと同時に、その“作られた”こと自体にリアリティを感じさせる逆説的な効果を生み出しています。
時間・テンポ・“ま”の感覚──映画的体験を醸成するテンポの構造
現代では多くの観客が映画を「倍速」で観ると言われていますが、『街の上で』はそのような消費的な視聴態度を拒否する作品です。
物語において時間は流れるものではなく、“滲み出る”ものとして扱われています。これはテンポの遅さではなく、むしろテンポが“生きている”ということの証明です。登場人物が言葉に詰まり、沈黙することで生まれる〈間〉が、観客に余白を与え、物語の外側に思考を広げさせる。
このように、時間とテンポの扱い方こそが、『街の上で』という映画が「映画である」理由を明確にしています。
総括:ありふれた日常に宿る詩情を捉えた傑作
『街の上で』は、物語の派手な起伏よりも、静かで淡々とした日常の“手触り”を何よりも大切にした映画です。無駄な会話、曖昧な関係性、都市と人間の距離、そして映画そのものの存在を問い直す構造──どれもが一見控えめながら、深い余韻を残します。
観終わったあと、ふと「何も起こらない1日」に価値を見出したくなる。そんな感覚を抱かせてくれる、今泉監督の美学が詰まった一作です。