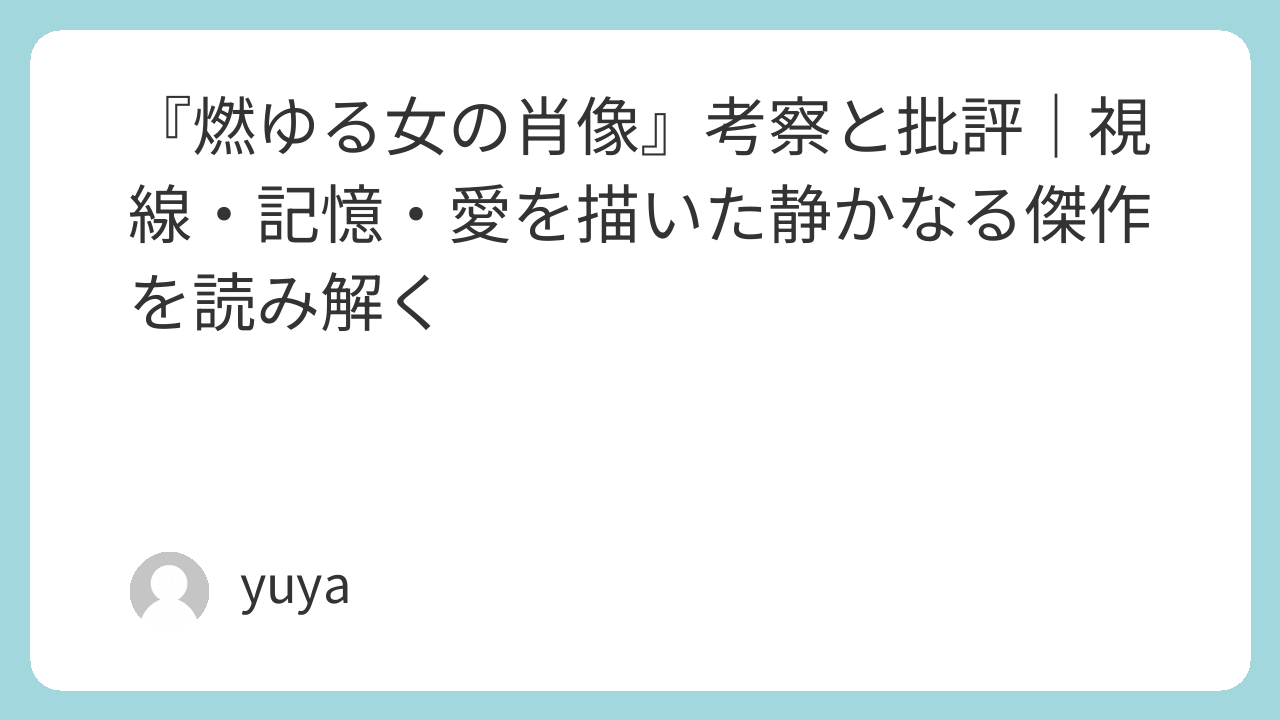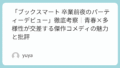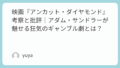フランス映画『燃ゆる女の肖像』(原題:Portrait de la jeune fille en feu)は、セリーヌ・シアマ監督による2019年の作品で、女性同士の恋愛を中心に、「見ること」「描くこと」「記憶に残すこと」といった深いテーマが織り込まれています。
本記事では、作品の背景と主題、象徴性、視覚表現を丁寧に読み解きながら、現代的なフェミニズムやジェンダーの視点を交えて考察していきます。
作品概要と背景:時代設定・キャラクター・あらすじのあらまし
本作は18世紀末のフランスを舞台に、貴族の娘エロイーズと画家マリアンヌの間に芽生える恋を描いた歴史ドラマです。
エロイーズは修道院から戻されたばかりの女性で、結婚を拒みながらも家族の意向で肖像画を描かれる運命にあります。マリアンヌは「結婚用の肖像画を描く画家」として雇われながらも、最初は素性を隠して彼女を観察し、後に本当の関係を築いていく――という物語構成です。
この設定のなかで、本作は恋愛ドラマにとどまらず、女性が社会において「選ばされる」こと、芸術において「見られる存在」になることへの違和感、反抗、そして解放を静かに描いていきます。
「見る/描く」の関係性:芸術行為と視線の寓意
『燃ゆる女の肖像』のもっとも核心的なテーマのひとつが、「視線と芸術」の問題です。
映画全体を通して、マリアンヌがエロイーズを“観察”し、彼女の表情や手、仕草を記憶しながら描こうとする過程には、単なる芸術行為ではなく、深い心理的な交錯があります。
「見る者=主体」「見られる者=客体」という従来の関係を崩し、二人の女性の間には対等な視線が交わされていく点が象徴的です。
やがて、マリアンヌが絵の主題であるだけでなく、エロイーズ自身も彼女を“見返す”存在となっていきます。この相互の視線の交錯は、「描くこと=愛すること」「記憶すること=存在させること」という命題に変換されていくのです。
主題と象徴性の読み解き:火・記憶・神話との対応
タイトルにもある「火」は、本作の中心的な象徴です。
火は情熱や欲望の象徴であると同時に、一瞬で消え去る“燃焼”の儚さをも表します。
エロイーズがドレスに火をまといながらも平然と立ち尽くすシーンは、そのまま彼女の激しくも抑圧された感情を暗示しています。
また、本作にはギリシア神話の「オルフェウスとエウリュディケ」のエピソードが挿入されます。
冥界から恋人を連れて戻る途中、オルフェウスは「後ろを見てはならぬ」という掟を破り、愛する人を永遠に失う――という物語。この神話は、「見てしまうことで終わる愛」「記憶としてしか残せない関係」として、マリアンヌとエロイーズの物語に重なっていきます。
さらに、エロイーズの最後の姿を描いたページ番号「28」は、永遠のページとして記憶に刻まれる“私だけの肖像”であり、火のように一瞬だが、永遠に消えない記憶の象徴となっています。
ジェンダー・フェミニズム・LGBTQ的視点からの批評
本作が強く評価されている理由のひとつに、「男性の視線」が完全に排除されている点があります。
画面にはほとんど男性が登場せず、世界はすべて女性たちによって構成されており、それが非常に特異かつ力強い演出となっています。
ここには、男性中心的な社会における女性の役割を「見られる者」「従う者」として捉える視点への批判があり、マリアンヌとエロイーズの関係が、そうした規範を逸脱していくことの痛みと歓びが描かれます。
また、レズビアン映画としても評価が高く、恋愛対象が「女性だから」ではなく、「彼女だから」愛しているという描き方も、現代的なLGBTQ表象として誠実であると受け止められています。
演出論・映像美の分析:構図/音楽/カメラワーク/静寂の効果
映像的にも『燃ゆる女の肖像』は非常に完成度の高い作品です。
カメラは固定気味に構えられ、絵画的な構図を多用することで、まるで“動く絵画”のような美しさを生み出しています。
特に、自然光やキャンドルの灯りを利用したシーンでは、人物の肌や表情が柔らかく浮かび上がり、まさに18世紀の肖像画を彷彿とさせます。
音楽についても特徴的で、劇中音楽はほとんど使用されず、沈黙や自然音が印象を支配します。
その分、終盤のヴィヴァルディ『四季』「夏」第3楽章の使用が際立ち、感情の爆発と記憶の定着を印象づけます。
また、まばたきを極端に減らした演技や、静寂の中における“間”の演出も、本作特有の緊張感と集中力を高めています。
まとめ|Key Takeaway
『燃ゆる女の肖像』は、単なる恋愛映画ではなく、「見る」「描く」「記憶する」という芸術と存在の根源を探る作品です。
ジェンダーや社会規範の抑圧の中で、それでも愛を育み、永遠に記憶として焼きつけようとする女性たちの姿は、静かでありながら深い余韻を残します。
視覚と沈黙の美学を極限まで突き詰めた傑作として、現代映画史に刻まれる一本であることは間違いありません。