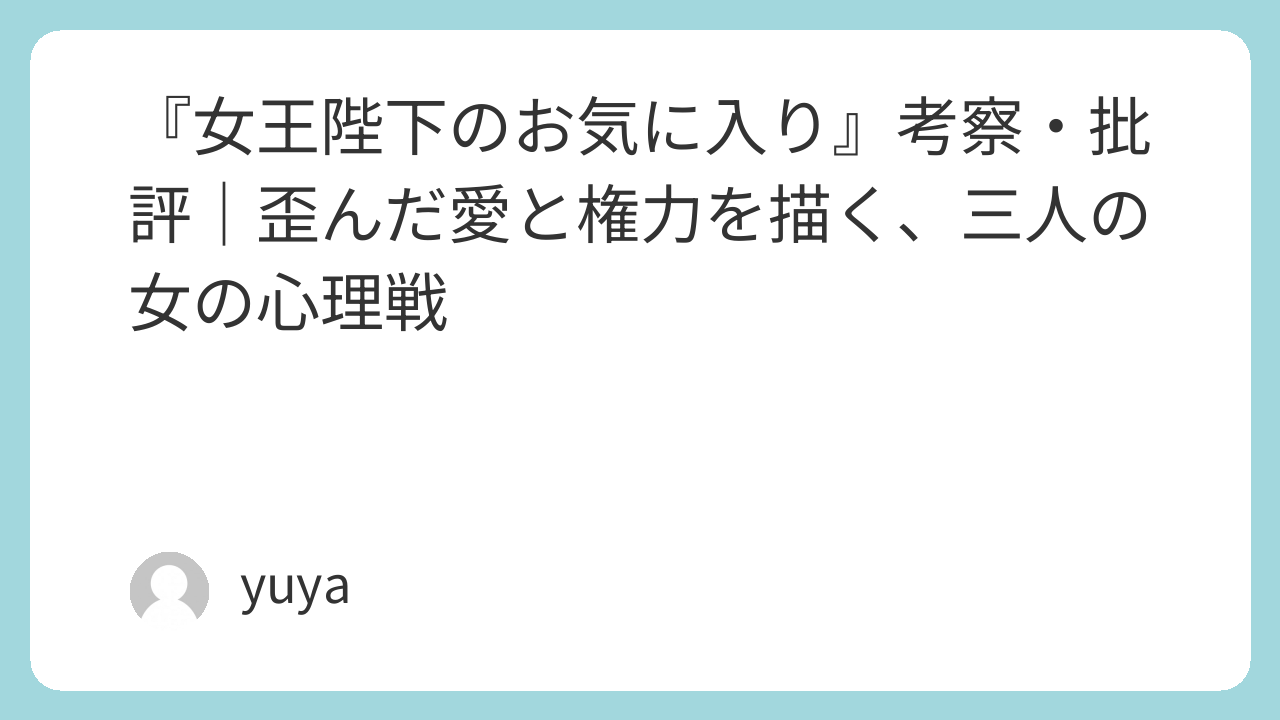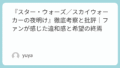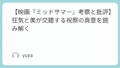『女王陛下のお気に入り』(原題:The Favourite)は、2018年に公開されたヨルゴス・ランティモス監督の歴史ドラマ映画でありながら、その実、極めて現代的なテーマを孕んだ異色作です。舞台は18世紀初頭のイングランド宮廷。病弱なアン女王と、彼女を取り巻く二人の女性——側近であるサラと、新たに登場する侍女アビゲイル——の複雑な関係を通じて、権力、愛、嫉妬、そして自己保存本能が交錯する人間劇が描かれます。
この記事では、ただの歴史劇としてではなく、寓話的でありながら皮肉に満ちたこの作品を、「考察」と「批評」の視点から深掘りしていきます。
作品概要と制作背景:歴史改変と創作のあいまいさ
『女王陛下のお気に入り』は、実在したイングランド女王アンと、彼女の側近だったサラ・チャーチル、そして後に側近となるアビゲイル・マシャムの三者関係を描いています。しかしながら、史実に忠実というよりは「史実をベースにしたフィクション」であり、人物像や関係性には多くの創作が加えられています。
監督のヨルゴス・ランティモスは、現実と虚構の境界を曖昧にする作風で知られ、本作でもその手法が遺憾なく発揮されています。脚本はデボラ・デイヴィスとトニー・マクナマラが手がけ、ウィットと皮肉に富んだセリフ回しが特徴的です。政治的な駆け引きよりも、登場人物の感情や権力欲に焦点が当てられており、歴史ドラマの枠に収まりきらない奥行きを持ちます。
三人の女性の力関係:アン王女・サラ・アビゲイルの心理戦
物語の中心は、アン女王を巡るサラとアビゲイルの心理戦です。サラは幼い頃からの親友としてアンを支配しており、政治的にも実権を握っています。一方、落ちぶれた貴族出身のアビゲイルは、最初は純粋な仕え人として登場しますが、やがて自らの地位を取り戻すべく、計算された行動を取り始めます。
三者の関係は単なる「三角関係」ではなく、愛情と支配、依存と裏切りが複雑に絡んでいます。アンは母性と愛を求める一方で、自らが誰よりも上に立ちたいという欲望も抱えており、サラもアビゲイルもそれを巧みに利用しようとします。この力関係の変化が物語の緊張感を高めており、最後には「勝者不在」の苦い結末を迎えます。
映像表現と美術・衣装・撮影演出:様式と寓意の狭間で
本作の大きな魅力の一つが、緻密に計算された映像美です。豪奢な宮廷衣装や美術セットは、18世紀イングランドの華やかさを再現する一方で、広角レンズを多用した不安定なカメラワークや自然光の使用により、どこか「歪んだ現実」としての世界観が構築されています。
とりわけ特徴的なのが、魚眼レンズによる撮影です。これにより、空間が湾曲して見え、視覚的に違和感を与えます。これは、登場人物たちの精神状態や、偽りと欺瞞に満ちた宮廷の世界を象徴しているとも解釈できます。また、衣装は時代考証に忠実でありながらも、キャラクターの内面を強調するために意図的な装飾が加えられています。
性的モチーフとジェンダー観:愛情と欲望の位相
『女王陛下のお気に入り』が他の歴史映画と一線を画すのは、女性同士の愛情と性的関係が核心にある点です。ただし、ここで描かれる性愛はロマンティックなものではなく、権力と結びついた非常に政治的な関係性です。
アンとサラ、そしてアンとアビゲイルの関係には、支配と服従がセットになっています。性的接触は「信頼」や「親密さ」の証ではなく、「相手より優位に立つための道具」として機能している場面が多いのです。ここには、伝統的なジェンダー観を逆手にとった批評性があり、女性が「権力を行使する主体」として描かれる稀有な作品となっています。
ラストシーンと結末の意味:勝者なき争いと虚構の余白
本作のラストシーンは極めて象徴的であり、多くの解釈を生む余地があります。最終的にアビゲイルがアンの側近としての地位を勝ち取る一方で、彼女はかつて抱いていた自由や尊厳を失っていることが示唆されます。そしてアン自身も、精神的にも肉体的にも誰にも愛されず、利用されるだけの存在として孤立しています。
この結末には、「誰も真の勝者ではない」というメッセージが込められており、人間関係の残酷さや権力構造の空虚さが浮き彫りになります。最後に映し出されるウサギたちのイメージは、失われた命や女性たちの運命を象徴しており、観客に不快な余韻と深い問いを残します。
Key Takeaway
『女王陛下のお気に入り』は、表面的には歴史劇でありながら、その本質は人間のエゴと欲望を描いたサイコロジカルドラマです。三人の女性の繊細で熾烈な心理戦を通じて、観る者に「権力とは何か」「愛とは何か」を問いかけてきます。美しくも歪んだ映像表現、政治的なジェンダー批評性、そして余韻を残す結末まで、あらゆる要素が緻密に絡み合った傑作と言えるでしょう。