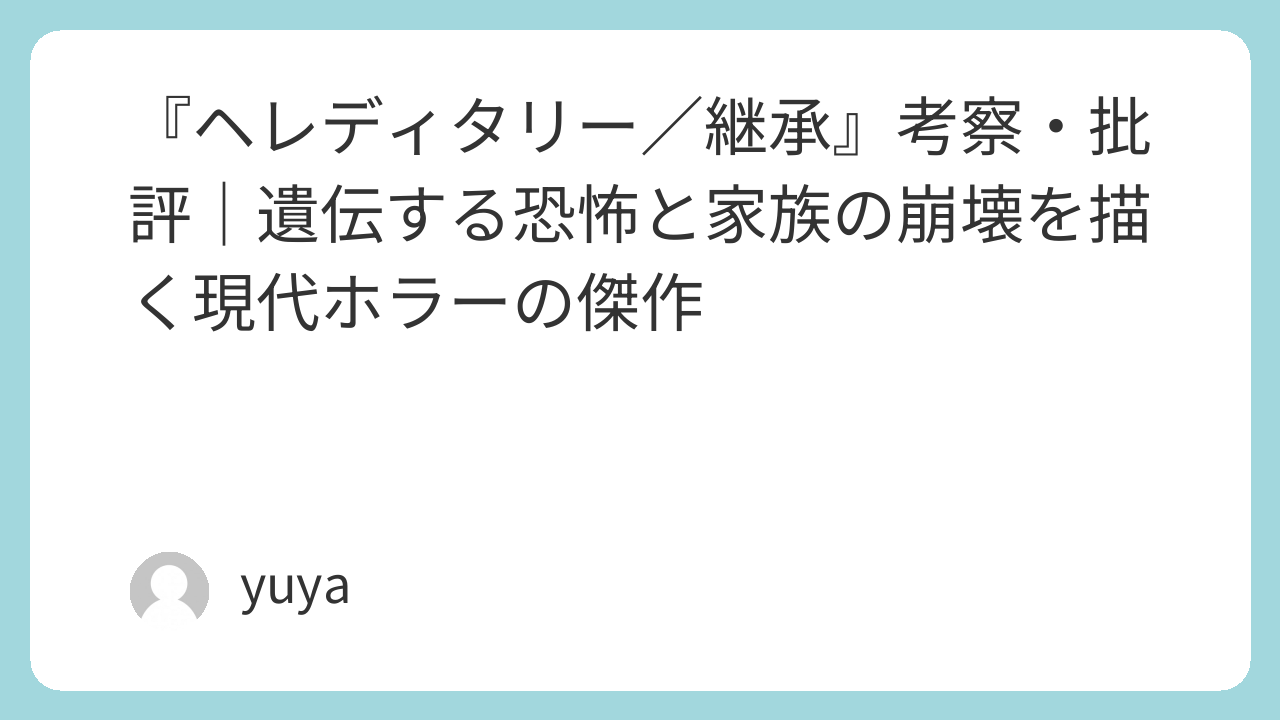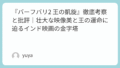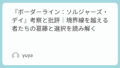アリ・アスター監督の長編デビュー作『ヘレディタリー/継承』(2018年)は、単なる「怖い映画」ではなく、観る者の精神を深く抉るような体験を提供します。「継承」という邦題が示す通り、この映画は血縁や家族に潜む恐怖を描いた作品であり、ジャンルの枠を超えた深いテーマ性を孕んでいます。
本記事では、本作を多角的に掘り下げていきます。家族の歴史がもたらす呪いと、その運命に翻弄される人々の悲劇を、物語構造や映像表現、心理描写の面から読み解きます。
「継承(Hereditary)」の意味:血縁・先祖・トラウマが物語にもたらすもの
タイトルにある「Hereditary(遺伝・継承)」は、本作の主軸を成すキーワードです。表面的にはオカルト的な「呪い」の話でありながら、それは実際には、家族に連綿と受け継がれる精神的・社会的な「負の遺産」を象徴しています。
主人公アニーの母エレンは、家族を支配し、神秘的な儀式と関わりを持っていた人物。彼女の死をきっかけに、アニーの家族にも異常な出来事が次々と起こりますが、それは偶発的な事件ではなく、長きにわたる「継承」の一環として描かれます。
ここでの継承とは、DNA的なもの以上に、「意志」「記憶」「呪い」が次の世代に受け継がれてしまうことへの恐怖でもあります。観る者は、逃れられない宿命に縛られた登場人物に、自らの家族や過去を重ねるかもしれません。
家族関係の崩壊とその心理描写:母・祖母・子どもの関係性の重み
本作の恐怖の源泉は、霊的な存在よりもむしろ、人間関係にあります。とりわけ、アニーとその母エレン、さらにアニーと娘チャーリーとの関係性には、深い断絶とすれ違いが見られます。
アニーは、自身の母に対して強い反発心を持ちながらも、その影響を断ち切ることができず、母親としての役割にも自信を持てていません。その結果、彼女自身が子どもたちに無意識のうちにトラウマを継承してしまっている様子が描かれています。
子どもたち—特にピーター—は、愛情と抑圧のあいだで揺れ動きながら、自己同一性を見失っていきます。こうした親子の軋轢を通して、本作は「愛するがゆえの恐怖」「家族であることの逃れられなさ」を描き出しているのです。
演出と映像美:ミニチュア模型・空間構成・光と影の使い方が語るもの
アニーの仕事である「ミニチュア模型作家」という設定は、視覚的にも象徴的にも非常に効果的です。彼女が作るミニチュアは、家庭の一場面や事故現場など、現実と地続きであるがゆえに観客に不気味さを与えます。
さらに、カメラワークやライティングにも注目です。家の構造はまるで「模型」のように箱型に撮られ、観客はまるで「神の視点」から家族の悲劇を見下ろす形になります。これは、登場人物たちが大きな力に操られていることの暗喩でもあります。
光と影の演出も秀逸で、特に夜の場面では、何が潜んでいるのか分からない暗闇が恐怖を増幅させます。その一方で、明るい昼間のシーンにも恐ろしい出来事が起こり、「常に油断できない世界」が演出されています。
構造と伏線:物語がどう組み立てられているか、ラストの意味をどう読み解くか
『ヘレディタリー』は非常に緻密に設計された脚本を持ち、多くの伏線が巧みに張り巡らされています。冒頭の葬式の描写、チャーリーの奇妙な癖、ピーターの授業シーンなど、すべてが後半で恐ろしい形で回収されます。
クライマックスに至るまで、観客は「これは何の話なのか?」と戸惑いながらも惹きつけられていきます。そして終盤、ついに真の「継承」が完了した時、全てがパズルのようにつながり、不気味な納得を得るのです。
この結末は、観る者によって解釈が分かれるでしょう。「運命に抗えなかった悲劇」なのか、「真の自分に目覚めた儀式」なのか。いずれにせよ、観賞後も深い余韻を残すことは間違いありません。
批評・評価:観客と批評家は何を恐れ、どこに新しさを見たか
『ヘレディタリー』は、ジャンルを超えた「アートホラー」として、多くの映画ファンと批評家に衝撃を与えました。その恐怖は、単なるジャンプスケアや残酷描写ではなく、「心理的な圧迫感」や「静かなる絶望」に由来します。
一方で、「理解しにくい」「重すぎる」といった否定的な声も少なくありません。ストーリーの難解さや、観客を突き放すような演出に戸惑う人もいるでしょう。
それでも本作は、ホラー映画に新たな地平を切り拓いた作品として高く評価されており、同監督の次作『ミッドサマー』と並んで、「心に残るホラー」として語り継がれています。
Key Takeaway
『ヘレディタリー/継承』は、「恐怖」とは何かを根源から問い直す作品です。家族、血縁、トラウマといった普遍的なテーマを通じて、観客に深い思索を促します。その複雑な物語構造と象徴的演出によって、ただのホラー映画では終わらない、重厚な映画体験を提供してくれるのです。