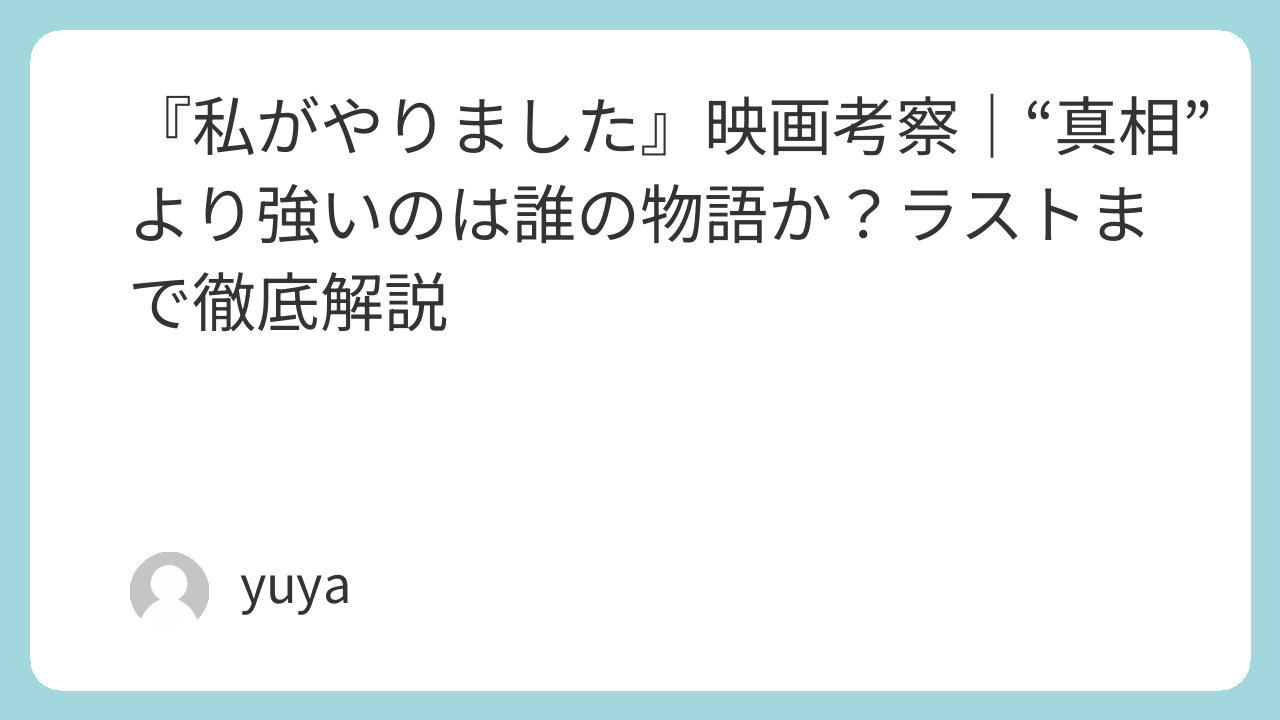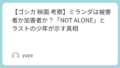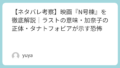「本当に大事なのは、誰が犯人だったか」ではない――。
フランソワ・オゾン監督『私がやりました』は、殺人事件をめぐる法廷劇の形を借りながら、“真実”と“語られ方”のズレを鋭く描いた一本です。
マドレーヌ、ポーリーヌ、オデットという3人の女性が、それぞれの思惑で「私がやりました」と言い得るこの物語は、ミステリーであり、風刺であり、シスターフッドの映画でもあります。
この記事では、ネタバレありであらすじを整理しつつ、タイトルの意味、ラストの解釈、そして本作が現代に突きつけるテーマを深掘りしていきます。
『私がやりました』の基本情報と作品の立ち位置
『私がやりました』は、フランソワ・オゾン監督による2023年フランス映画で、日本では2023年11月3日に公開されたクライムミステリーです。上映時間は103分(国際情報では102分表記もあり)で、ナディア・テレスキウィッツ、レベッカ・マルデール、イザベル・ユペールという3人の女性キャラクターが物語の軸を担います。作風としては“重い事件を軽やかに語る”タイプで、ミステリー、法廷劇、風刺コメディの要素が同居しています。
あらすじ整理:誰が「犯人」なのかをめぐる物語
物語は、若手女優マドレーヌが有名プロデューサー殺害の容疑をかけられるところから始まります。親友で新人弁護士のポーリーヌが組み立てた「正当防衛」のロジックにより、マドレーヌは無罪を獲得。さらに“悲劇のヒロイン”として名声まで手に入れます。ところがそこに、かつての大女優オデットが現れ、「本当の犯人は自分だ」と名乗り出ることで、事件は「真相解明」よりも「誰が物語の主語になるか」の争いへと変化していきます。つまり本作の核心は、犯人当てそのものより、犯罪・正義・世論がいかに演出されるかにあります。
原作からの改変が示すテーマ:文学界→映画界への移し替え
この作品は1934年の戯曲『Mon crime』を下敷きにしていますが、オゾンは設定を大きく改変しています。監督インタビューによれば、原作側では主人公の職業設定が異なるのに対し、映画版では「女優」に変更し、“嘘を演じる職業”そのものを物語のテーマ化しました。ここで重要なのは、法廷での弁論や証言が「真実の提示」ではなく「説得力のあるパフォーマンス」へ転化していく点です。
この改変によって『私がやりました』は、単なる時代劇ミステリーではなく、イメージが真実を上書きする現代のメディア社会を照射する作品になっています。
「嘘」と「演技」はなぜ観客の共感を生むのか
本作の面白さは、主人公たちが“完全に潔白”ではないのに、観客がつい彼女たちの側に立ってしまうところです。
オゾン自身が語るように、この映画には「下手な女優が大きな嘘によって良い女優になっていく」という皮肉な成長譚が埋め込まれています。さらに、嘘によって社会的抑圧の構造が可視化されるため、観客は「手段としての嘘」に倫理的な揺らぎを感じながらも、彼女たちを単純に断罪できなくなる。
ここでの考察ポイントは、真実か虚偽かより先に、誰の言葉が信じられる文脈を獲得するのかです。『私がやりました』の法廷は、正義の場であると同時に“演技の劇場”でもあります。
シスターフッドの描写:連帯は「善」だけでできていない
「私がやりました 映画 考察」で外せないのが、シスターフッドの描き方です。オゾンは本作を女性連帯の映画として位置づけつつ、そこに“打算”“嫉妬”“競争”もあえて混ぜています。つまり、理想化された連帯ではなく、利害や虚栄を抱えたまま成立する現実的な同盟が描かれている。
だからこそ本作の女性たちは、聖人として称揚されるのではなく、矛盾を抱えた主体として魅力を放つのです。連帯は純粋でなくても機能するし、むしろ不純だからこそ強い──この逆説が本作の現代性を支えています。
1935年パリ設定の意味:過去を借りて現在を語る
物語は1935年のパリに置かれていますが、オゾンはこの時代を厳密な再現としてではなく、ある種スタイライズされた舞台として扱っています。監督は、1930年代設定にすることで現代の重い主題(性差別、権力、#MeToo的文脈)を“距離を保って語れる”と説明しています。
また、歴史的に見てもフランス女性の参政権は1944年の法令、初投票は1945年で、さらに既婚女性が夫の同意なしに就労・口座管理できる法整備は1965年です。1935年という設定は、女性が制度的に大きな制約下にあった社会を背景にしており、劇中の闘いに強い説得力を与えています。
オデットという攪乱者:第三の女が物語を反転させる
中盤以降で空気を一変させるのがオデットです。彼女は「真犯人」を名乗ることで、マドレーヌとポーリーヌが築いた成功物語を根本から揺さぶります。
このキャラクターの機能は、真相暴露それ自体よりも、“被害者”“加害者”“功労者”という役割がいかに交換可能かを示すことにあります。オデットが現れた瞬間、物語は二項対立(善/悪、真/偽)では処理できなくなり、観客は「誰の語りを採用するか」を迫られる。
考察記事としては、オデットを“トリックスター”として読むと全体が整理しやすくなります。
ラストの解釈:真実の勝利ではなく「物語の所有権」の決着
本作の終盤は、一般的なミステリーのように「事実の一点回収」で終わりません。むしろ、最後まで残るのは“どの物語が社会で流通するか”という問題です。
オゾンが語る通り、作品は冒頭と終盤を舞台的な装置で括り、人生そのものを演技として見せる設計を取っています。したがってラストの読解ポイントは、犯人当ての正解ではなく、語る者が権力を持つという構造認識です。
『私がやりました』は、正義が勝った話ではなく、語りの主導権を誰が握るかをめぐる現代的寓話として締めくくられる──。