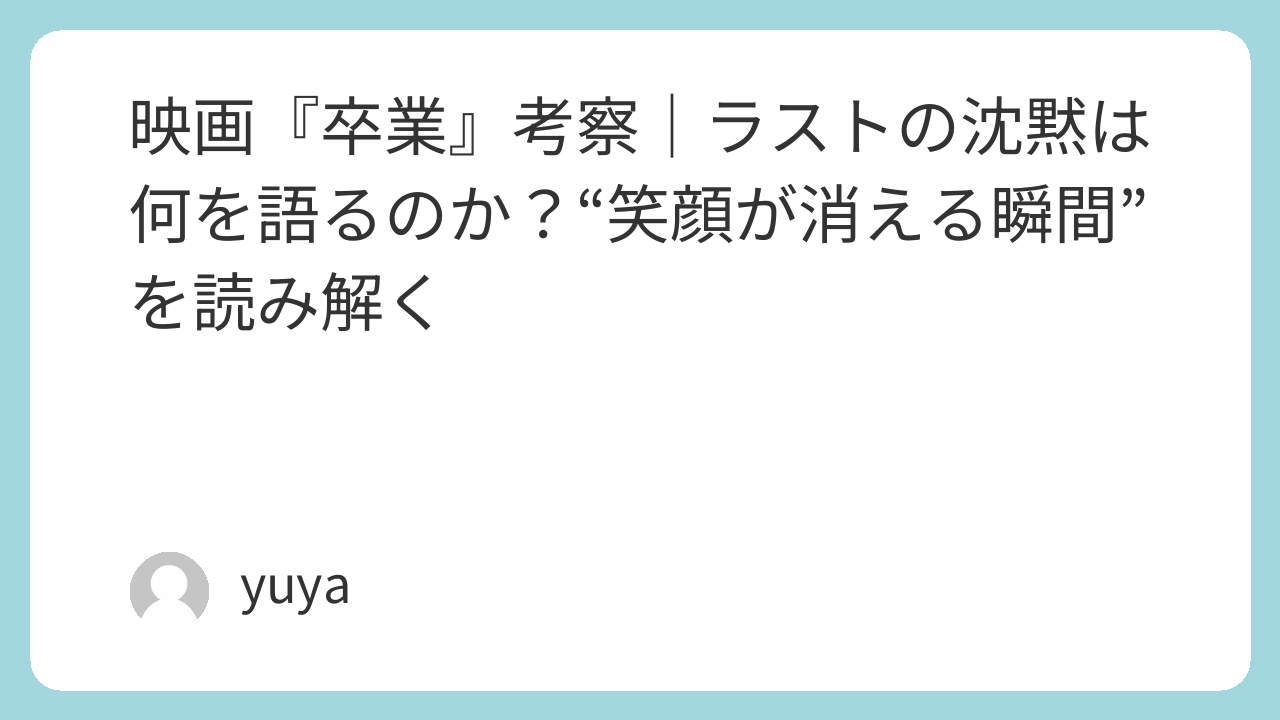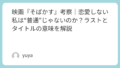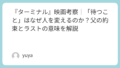1967年公開の名作『卒業』は、不倫や駆け落ちを描いた恋愛映画としてだけでなく、**「自分の人生を自分で選ぶとはどういうことか」**を突きつける作品です。
なかでも有名なラスト、バスの中でふたりの笑顔が消えていく数十秒は、多くの観客に「これはハッピーエンドなのか?」という問いを残しました。
本記事では、ベンジャミンの空虚さ、ミセス・ロビンソンの人物像、名台詞「プラスチック」の象徴性、そしてサイモン&ガーファンクルの楽曲効果までを整理しながら、映画『卒業』の結末をネタバレありで考察します。
観終えたあとに残るあのざらついた感情の正体を、一緒に言語化していきましょう。
映画『卒業』考察:まず押さえたい基本情報と時代背景
映画『卒業』(原題 The Graduate)は1967年公開、マイク・ニコルズ監督作品です。主演はダスティン・ホフマン、アン・バンクロフト、キャサリン・ロス。若者の“卒業後の宙ぶらりん”を、恋愛劇の形で鋭く描いた一本として語り継がれています。
作品としての評価も高く、第40回アカデミー賞では7部門ノミネート、監督賞を受賞。後年には米国国立フィルム登録簿(National Film Registry)にも選ばれ、「時代を映した映画」として公式に保存対象となりました。
この映画が生まれた60年代後半は、価値観の転換期。親世代の「安定こそ正義」と、子世代の「それで本当に幸せか」の衝突がむき出しになります。だからこそ『卒業』は単なる不倫映画ではなく、世代の断層を映す青春映画として今も機能しているのです。
ベンジャミンはなぜ空虚だったのか――“卒業後”のモラトリアム心理
ベンジャミンは、いわば「成功コースに乗せられた優等生」です。けれど彼の内側には、達成感よりも空白がある。周囲は祝福しているのに、本人だけが自分の人生の“主語”を持てていない。ここに『卒業』最大の痛みがあります。
この感覚は、ブリタニカが本作を説明する際に使う「postgraduate malaise(卒業後の倦怠/不安)」という言葉が示す通り、当時の若者全体の症状でもありました。
つまり彼の問題は「恋がうまくいくか」以前に、何者として生きるかを決められないこと。だから彼の行動は一見大胆でも、実はずっと受け身のままです。この“動いているのに前に進んでいない”感じが、観る側の胸に残ります。
ミセス・ロビンソンは悪女か被害者か――大人社会の矛盾を読む
『卒業』を深くするのは、ミセス・ロビンソンが単純な悪役ではない点です。彼女は若者を誘惑する「脅威」として登場しますが、同時に、形式だけが残った結婚や体面主義の中で消耗していく大人の象徴でもあります。
ベンジャミン側から見れば、彼女は“自由への入口”のように見える。しかし実際には、彼を解放するどころか、同じ空虚へ引きずり込む存在でもある。ここに本作の皮肉があります。若者が嫌っているはずの世界に、若者自身が飲み込まれていく構図です。
だからミセス・ロビンソンは「悪女か、被害者か」の二択ではなく、壊れた価値観を生き延びるための仮面をつけた人物として読むと、映画全体の奥行きが一気に増します。
エレインとの恋は救済か逃避か――ベンジャミンの選択を検証
エレインとの恋は、ベンジャミンにとって「純粋な愛の回復」に見えます。母の世代との関係(ミセス・ロビンソン)から、同世代との関係(エレイン)へ移ることで、彼はやっと本当の自分を選んだ――そう読めるからです。
ただし別の見方をすると、これは“対象を変えただけの逃避”でもあります。進路や仕事、人生設計と向き合わないまま、恋愛というドラマで自分を救済しようとしている。ここが本作の厳しさです。
つまりエレインとの恋は、救済であり逃避でもある。二項対立ではなく、救済を求める逃避、逃避を通じた救済として重ねて読むのが、『卒業』考察の要点です。
名台詞「プラスチック」が象徴するもの――成功神話への皮肉
「Plastics(プラスチック)」という有名な一言は、『卒業』を代表する文化記号です。AFIでもこの台詞は作品を象徴する引用として扱われ、映画史的に繰り返し言及されています。
この言葉が刺さるのは、職業アドバイスを装いながら、実際には「大量生産・画一化・中身のない成功」への同調圧力を言い当てているから。ニューヨーカーでも、この台詞が当時の空気を象徴した語として論じられています。
『卒業 映画 考察』でこの台詞を軸にすると、単なる名シーン紹介では終わりません。作品全体に流れる「あなたは誰の価値観で生きるのか?」という問いに直結できるからです。
映像演出で読む『卒業』――構図・沈黙・視線が語る閉塞感
『卒業』は台詞よりも、“見せ方”で心理を語る映画です。批評でも、脚本の切れ味とキャスティングの精度、そして最終盤を含む演出の強さが高く評価されています。
例えば、人物を枠の中に閉じ込めるような構図、視線が交わらない会話、沈黙が伸びる間。これらは「言葉があるのに通じない世界」を可視化しています。だから観客はストーリーを理解するというより、閉塞感を“体感”することになるのです。
この作品を名作にしているのは、事件の大きさではなく、息苦しさの演出精度。そこにニコルズ演出の現代性があります。
ラストのバスシーンを考察――笑顔が消える瞬間の意味
教会からの“奪還”までは、古典的なロマンスの勝利に見えます。ところがバスに乗った直後、二人の笑顔はゆっくり消え、表情は曖昧に変わる。この転調こそ『卒業』の核心です。
このラストは、しばしば「ハッピーエンドの否定」や「自由の代償の可視化」として読まれます。実際、結末を断定しないことで、観客に“この先”を考えさせる構造になっています。
要するにあの表情は、「間違った」のサインではなく、選んだ瞬間に責任が始まることのサイン。青春の高揚を、現実の重さで受け止める一瞬なのです。
サイモン&ガーファンクルの楽曲は何を補強したのか
本作の音楽は、映像と同じくらい物語を動かします。公式情報でも、サウンドトラックには「The Sound of Silence」や「Mrs. Robinson」の断片などが使われ、映画テーマとの結びつきが強調されています。
特に「Mrs. Robinson」は映画版では未完成形に近い使われ方をし、のちに再録音版が広く浸透。さらにグラミーのRecord of the Yearを獲得し、映画と楽曲が相互に神話化されました。
つまり劇中音楽はBGMではなく、ベンジャミンの心情を“代弁”するもう一人の語り手。『卒業』が記憶に残るのは、映像だけでなく音の記憶が強固だからです。
『卒業』が今も刺さる理由――世代間ギャップと自己決定の普遍性
『卒業』は1967年の作品ですが、今の観客にも驚くほど近い。なぜならテーマが「就職」でも「恋愛」でもなく、自己決定の困難そのものだからです。
親の期待、周囲の正解、社会のテンプレ。これらに押されて自分の選択が見えなくなる感覚は、時代が変わっても消えません。だからベンジャミンの不器用さは、現代の私たちにも“痛いほどわかる”のです。
作品が長く評価され続ける背景には、映画史的な位置づけもあります。National Film Registryへの選定(1996年)やAFIでの上位評価は、その普遍性を制度的にも裏づけています。
まとめ:映画『卒業』の結末をどう解釈するべきか
『卒業』の結末は、成功でも失敗でもなく「開始」です。
二人は大人社会への反抗に一度は成功する。けれど同時に、そこから先の人生を自分で引き受ける段階に入る。あのバスの沈黙は、その境目を描いたものです。
だから本作は、
- 反体制の青春映画
- 恋愛の皮を被った世代論
- “自分の人生を選ぶ怖さ”の物語
として重層的に読めます。