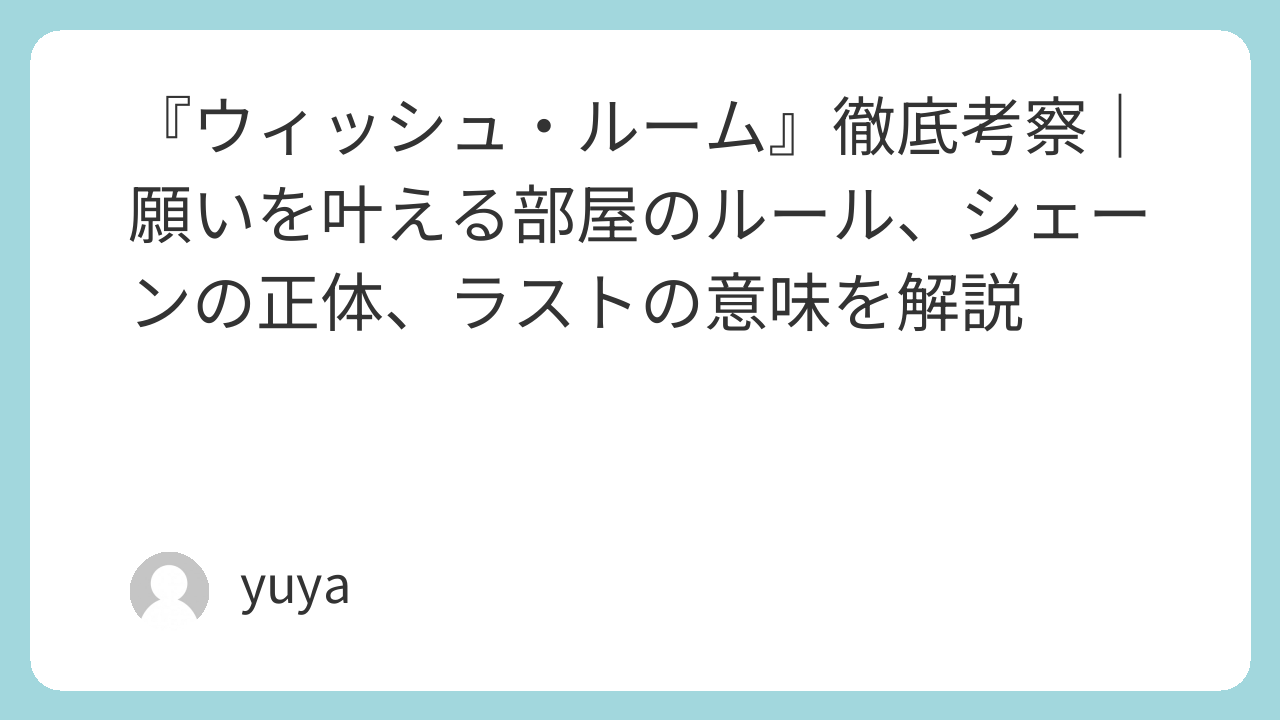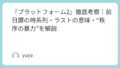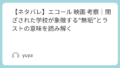「ウィッシュ・ルーム」は、“願いを叶える部屋”という魅力的な設定の裏側に、人間の欲望と家族の崩壊を描いた異色のサスペンスです。なぜ夫婦は破滅へ向かったのか、シェーンは何を象徴しているのか、そしてラストの妊娠反応と点滅は何を意味するのか。この記事では、作品のルールと伏線を整理しながら、ネタバレありで『ウィッシュルーム』を考察していきます。
『ウィッシュ・ルーム』の基本設定と物語の導入
『ウィッシュ・ルーム(原題:The Room)』は、願ったものを“実体化”できる隠し部屋を発見した夫婦の転落を描くサスペンス・スリラーです。作品情報としては2019年製作、上映時間は約99〜100分、フランス・ルクセンブルク・ベルギー合作で、主演はオルガ・キュリレンコとケヴィン・ヤンセンス。監督・脚本にはクリスチャン・ヴォルクマンが名を連ねています。
導入の巧さは、「夢のような願望充足」をあえて日常的な幸福の延長線上に置いた点にあります。最初はお金・宝石・ぜいたく品といった“わかりやすい欲望”から始まるため、観客も「もし自分なら?」と自然に物語へ参加してしまう。その参加感が、後半で“取り返しのつかなさ”に変わる構造が本作の強みです。
願いを叶える部屋の「ルール」が示すもの
本作の核心は、「この部屋が何でもくれる」ことではなく、**“くれるが、現実世界では維持できない”**という制約です。部屋由来のものは家の外で消滅する(灰になる)というルールが判明し、夫婦の万能感は一気に“監禁された豊かさ”へ反転します。
このルールが上手いのは、単なるホラー装置ではなく、テーマそのものになっている点です。つまり本作は「欲望が叶う恐怖」より、「叶った欲望が現実と接続できない恐怖」を描いている。だからこそ、豪奢な暮らしのシーンが幸福ではなく、むしろ空虚の前振りとして機能します。
シェーンという存在が突きつける“愛”と“所有”の境界線
物語が決定的に重くなるのは、夫婦が「子ども」を願ってしまう瞬間です。上位レビューでも繰り返し触れられるように、ここから映画は“モノの願望”から“命の願望”へ位相を変えます。
しかも、シェーンは「外に出ると急速に老化する/生存できない」という部屋の法則に縛られ、子どもでありながら“この家そのもの”に囚われた存在として育っていきます。MUBIや各種紹介文にもある通り、夫婦の喪失経験(流産)と結びついた願いであるぶん、倫理判断を単純化できないのが本作の痛みです。
このパートの考察ポイントは明確で、母性/父性の問題ではなく、「愛は相手の自由を許せるか」という問題です。愛しているから閉じ込めるのか、愛しているから解き放つのか。シェーンの悲劇は、夫婦の“善意”がそのまま暴力に変わり得ることを示します。
ジョン・ドゥの警告が意味する“欲望の歴史”
ジョン・ドゥという人物(過去の事件と接続する存在)は、世界観の説明役であると同時に、“この家では同じ悲劇が反復される”ことを示す予告装置です。夫婦の物語を個人的な失敗ではなく、システム(部屋)に組み込まれた構造的悲劇へ引き上げる役割を担っています。
考察的には、ジョン・ドゥは「未来の夫婦像」を先回りして見せる鏡です。願望が過剰になり、現実と切断され、最後に“人間関係そのもの”が壊れる。彼の警告はオカルト情報というより、欲望の取り扱いに失敗した人間の実例として読むと、作品の倫理軸がより鮮明になります。
終盤の空間トリックが示す“現実崩壊”の怖さ
後半では、部屋が生み出すのは物体だけでなく、空間認識や同一性(誰が本物か)そのものへ広がっていきます。終盤の“家の複製”や“見分けの揺らぎ”は、ジャンル的な見せ場であると同時に、夫婦の信頼が崩壊した心理状態の可視化でもあります。
ここで重要なのは、「怪物が外から来る」のではなく、「欲望が家の内側で増殖して怪物化する」こと。ワンシチュエーションの閉鎖感が強いぶん、外部脅威よりも“家庭の内部崩壊”が恐怖の中心になっているのが本作らしさです。
ラストシーン(妊娠検査薬と点滅)は何を意味するのか
ラストの妊娠反応と電灯の点滅は、本作最大の未確定要素です。物語上の事実として「妊娠が示される」「点滅が起きる」までは確定ですが、それが何を断定するかは明言されない。この“解釈の余白”が後味の悪さと考察性を同時に生んでいます。
興味深いのは、主演オルガ・キュリレンコのインタビューでも、結末は“決め切らない”魅力として語られている点です。彼女自身、観客がさまざまな方向へ推測することを作品の強みとして捉えていました。つまり本作は、答え合わせで終わる作品ではなく、観客の不安を持ち帰らせることで完成する作品だと言えます。
『ウィッシュ・ルーム』が描くテーマの結論
この映画の本質は、「願いは叶うか?」ではなく「叶った願いを人間は扱えるか?」にあります。物質的願望、家族願望、支配欲、承認欲が、閉じた空間で互いを増幅し、最終的に“幸福のはずだったもの”を恐怖へ変える。まさに“願望の逆流”を描いた作品です。
批評評価が割れる(Rotten Tomatoesでは批評家69%、観客53%)のも、この作品が整った謎解きより、心理的な不快感と倫理的グレーを優先しているからでしょう。好き嫌いは分かれても、考察記事との相性は非常に高い一本です。