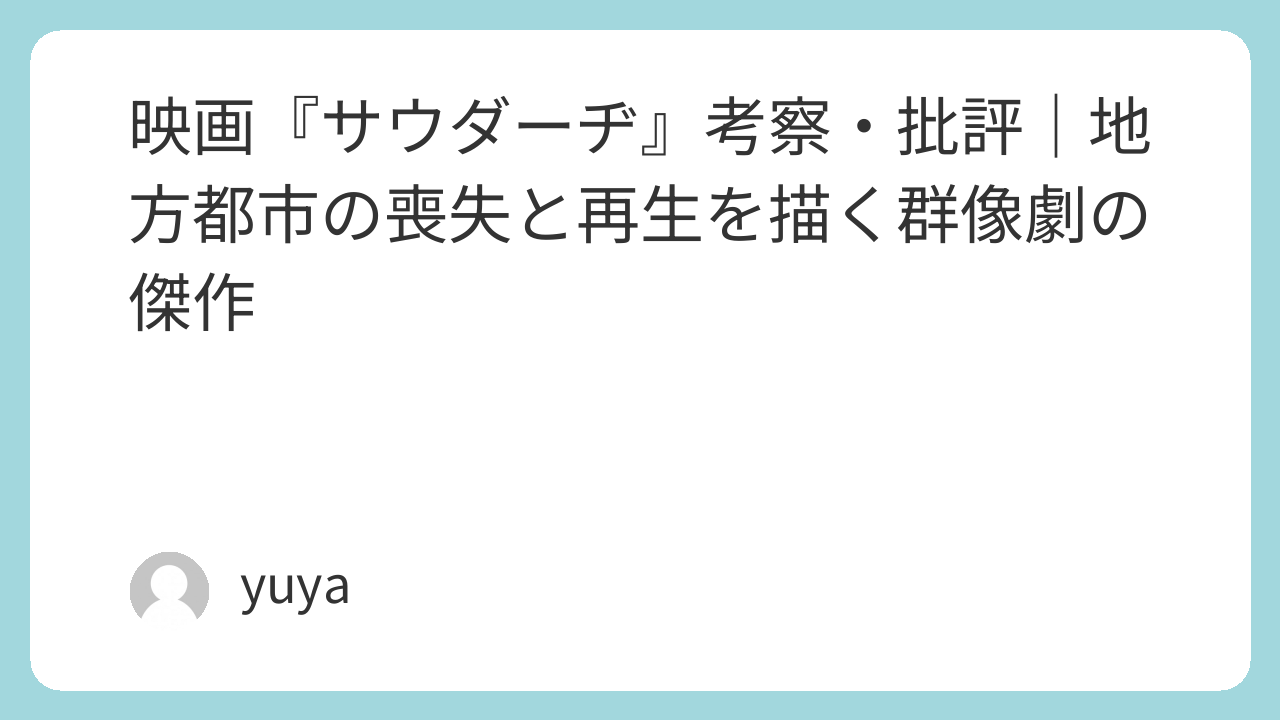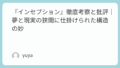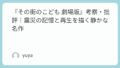「この町には、何もない。」
そんな言葉が観る者の心を刺す映画『サウダーヂ』(2011年、富田克也監督)は、山梨県甲府市を舞台に、地方都市のリアルな現在を生々しく切り取った作品です。
この映画は、単なる社会派ドラマでも、単なる青春映画でもありません。失われた地域経済、共生を模索する多文化社会、未来に希望を持てない若者たち…さまざまな断片が複雑に重なり、見る者の心にざらついた痛みを残します。
本記事では、本作を多角的に掘り下げていきます。
地方都市・甲府の「リアル」としての風景描写
『サウダーヂ』はまず何より、「風景」が主役の映画だと言えるでしょう。
舞台となる甲府市は、映画の中でまるで“失われた都市”のように描かれます。空き地、シャッター商店街、工事現場、誰も歩いていない歩道橋、静まり返る住宅地…。これらの描写はフィクションのために誇張されたものではなく、私たちがよく知る「今の地方都市」の姿です。
とくに印象的なのは、工事現場で働く日雇い労働者たちの姿が、ドキュメンタリー的なリアリズムで撮られている点です。カメラは引きの構図を多用し、風景の中に埋もれるような人物たちの存在を際立たせています。
つまり、本作は都市の衰退をただ描くだけではなく、その都市で「生きている」人々の生活の手触りを真摯に捉えているのです。
移民・外国人労働者の存在と格差:共生か断絶か
本作の重要なテーマの一つが、多文化社会における「断絶」と「接続」です。
映画にはタイ人女性やブラジル系労働者などが登場しますが、彼らは単なる背景ではありません。日本人の若者たちと同じように、生活に苦しみ、言葉にならない感情を抱えて生きています。
とくに、タイ人女性ナムが登場する場面では、恋愛感情や文化的な齟齬が複雑に絡み合い、「本当に理解し合うことは可能か」という問いが浮かび上がります。
この映画は、単なる多文化礼賛や排外主義とは無縁であり、むしろその中間で揺れ動く「曖昧な共生」のリアルを映し出しているのです。
群像劇としての主人公たちの葛藤と絶望/希望
物語には明確な主人公は存在しません。代わりに、精司(ヒップホップ活動をする若者)、猛(建設現場の労働者)、ナム、さらには地元の暴力団関係者や無職の若者など、様々な立場の人々が登場し、それぞれの生活が交差していきます。
精司は地元の友人とラップグループを組むものの、現実は厳しく、希望を語る声すら虚しく響きます。
猛は、仕事をしても稼げず、心の空白を埋めるように酒に溺れます。
彼らの生き方はバラバラですが、共通するのは「未来が見えない」ことです。
しかし、そこにはかすかな光もあります。絶望の中にあっても、音楽、友情、愛情…そうした小さなつながりが、彼らを少しだけ前に進ませます。
映像表現・編集のスタイル:時間、モンタージュ、錯綜するカット
『サウダーヂ』は2時間47分という長尺でありながら、観客に退屈を感じさせない不思議なテンポがあります。それは、編集・映像の「間」の使い方に理由があります。
例えば、何気ないシーンが長回しで撮られることで、登場人物の感情の微細な揺れを捉える一方、会話の断絶や風景カットの多用によって「時間がすり抜けていく感覚」が醸し出されます。
また、時系列もあえて曖昧にされており、どこからどこまでが現実で、どこからが過去なのかが不明瞭になる場面も。
この映像言語は、地方都市の“停滞”と“断続性”をそのまま表現しているとも言えます。まるで映画そのものが、町の「記憶装置」になっているかのようです。
「サウダーヂ」というタイトルが示すもの:郷愁と憧れの層
「サウダーヂ(Saudade)」とは、ポルトガル語で「郷愁」「失われたものへの憧れ」「戻らない過去への切なさ」を意味する言葉です。
本作はその言葉通り、「今ここにないもの」への思いに満ちています。
それはかつての活気ある甲府の街かもしれないし、若者たちが夢を持っていた過去かもしれない。あるいは、自分のルーツや愛した人への記憶かもしれません。
しかし『サウダーヂ』は、単なる懐古主義には陥りません。むしろ、この「郷愁」が現実逃避ではなく、「今をどう生きるか」を問い直す契機となっているのです。
まとめ:『サウダーヂ』が映す“わたしたちの現在地”
『サウダーヂ』は、地方都市に生きる若者、外国人労働者、高齢者など、普段映画では描かれることの少ない人々の生活を、真正面から描いた作品です。
その描写は時に荒々しく、時に繊細で、何よりも真摯です。
この映画は、地方都市のリアリティを知るうえで貴重な作品であり、日本という国の“今”を問う鏡でもあります。
不確かで不安定な日常の中で、それでも人は関わり、生きていく。そんな小さな希望を、『サウダーヂ』は静かに、しかし確実に描いています。