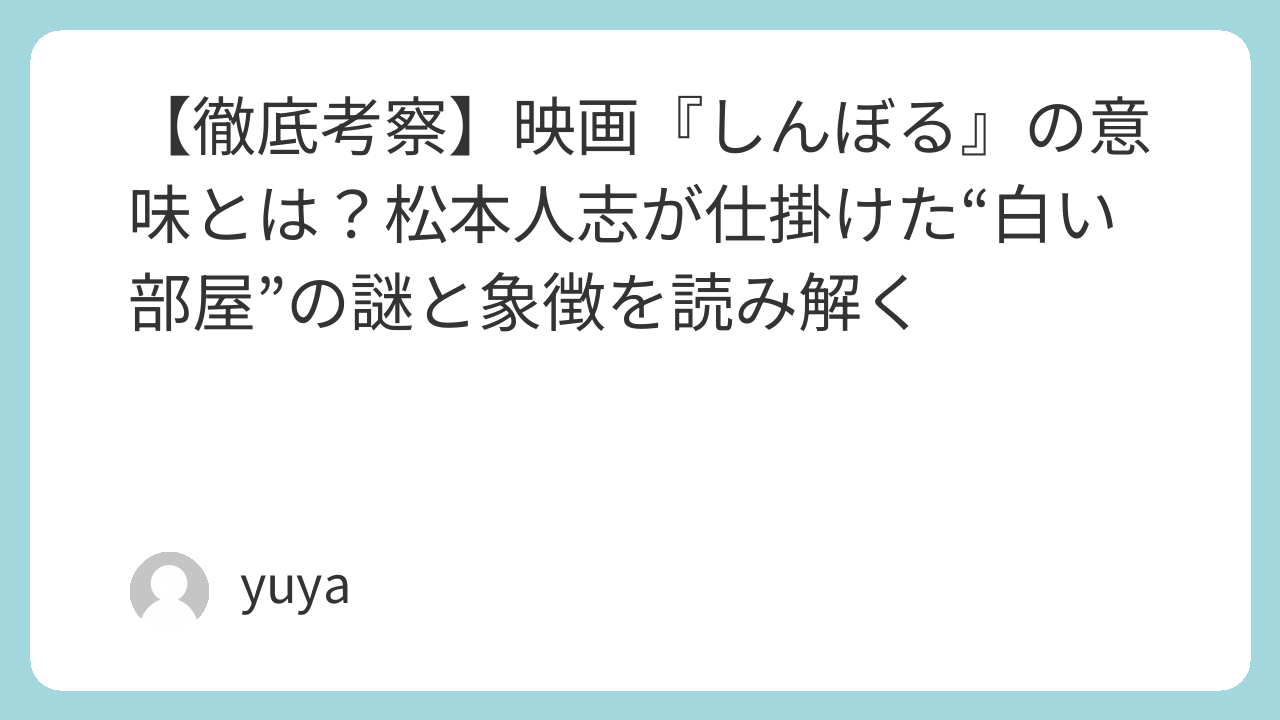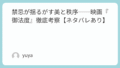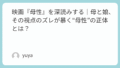松本人志が監督・主演を務めた映画『しんぼる』(2009年)は、その独特すぎる構成と抽象的な描写から、「意味がわからない」との声が多い一方で、熱心なファンや考察好きにとっては“考えること自体が面白い”一作となっています。
本記事では、本作の魅力と謎を深掘りし、様々な視点からその意味を探っていきます。
本作の概要と構造 ―「密室パート×ルチャリブレ」2本立ての作劇
『しんぼる』は、二つのまったく異なるパートから構成されています。一方は、白い密室で目を覚ました男(松本人志)が、意味不明な“突起物”を押すことで部屋を変化させていく無言劇。そしてもう一方は、メキシコの中年レスラー「エスカルゴマン」とその家族の生活が描かれたリアルな日常劇です。
この二つの物語は交互に描かれ、物語終盤である種の“交点”を迎えるものの、決して明確な説明はなされません。観客は、その関係性や意味を自ら解釈するよう促されます。この自由度の高さこそ、本作が“考察向き”とされる理由の一つです。
象徴/シンボルの読み解き ―「壁・スイッチ・寿司・羽」などイメージの意味
タイトル通り、本作には様々な「シンボル=象徴」が散りばめられています。白い部屋の壁に現れる突起物は、その一つを押すたびに新たなアイテムや状況を呼び込む“スイッチ”として機能します。出現するアイテムは多岐に渡り、寿司、歯ブラシ、天使の羽、など、意味を読み取るのが困難なものばかりです。
たとえば、寿司は「日本文化」、羽は「神格化」や「天上界との接点」、スイッチは「選択肢」や「運命の転換点」とも解釈できます。これらの象徴は、観る人の視点によって意味が異なり、解釈の多様性を生んでいます。
登場人物・空間・設定の意図 ―監督 松本人志 が描きたかったもの
本作における「白い部屋」は、現実ではなく、どこかメタフィジカル(形而上)的な空間です。主人公である“目覚めた男”は、何らかの神的存在としての目覚めを経験しているのかもしれません。一方でメキシコのレスラーの物語は、日常的でありながら、どこか寓話的でもあります。
松本人志はインタビューなどで「自分の頭の中をそのまま映像にした」と語っています。つまり、筋の通った物語よりも、思いつきの発想や連想を重視した作品と言えるでしょう。そこに観客が意味を付加していく構造は、むしろ「体験型アート」に近いかもしれません。
批評と反響 ―「意味が分からない」「自由解釈歓迎」の両側面
公開当時、『しんぼる』は賛否両論を巻き起こしました。「意味がわからない」「笑えない」といった否定的な評価もあれば、「唯一無二」「松本人志らしい挑戦」といった高評価も多く見られます。
特に批評家からは、「観客に解釈を委ねすぎている」との指摘もある一方で、「現代アートのような構造で新しい映像体験を提示している」と好意的に評価する声もあります。まさに“見る人を選ぶ作品”ですが、だからこそ考察の余地があるのです。
私なりの考察 ―「成長/世界への作用/神格化」というモチーフ変遷
筆者自身の解釈では、『しんぼる』の主人公は、「無意識の世界での覚醒と成長」を体験しているのだと考えます。突起物=選択を繰り返し、試行錯誤の果てに“操作”できる範囲が広がっていく様は、まさに人生や創造の比喩のように思えます。
終盤では“世界そのものに影響を及ぼす存在”へと昇華し、神格的な位置に至る姿が描かれます。それは、ただのギャグやナンセンスではなく、「人間の可能性」や「創造主としての自己」への問いかけとも受け取れます。
Key Takeaway
『しんぼる』は、“意味を与える力”が観客側に託された作品です。そのぶん敷居は高いかもしれませんが、自分なりの視点で象徴を読み解くことで、全く異なる意味が浮かび上がってきます。松本人志の挑戦的な試みにこそ、この映画最大の魅力があるのです。