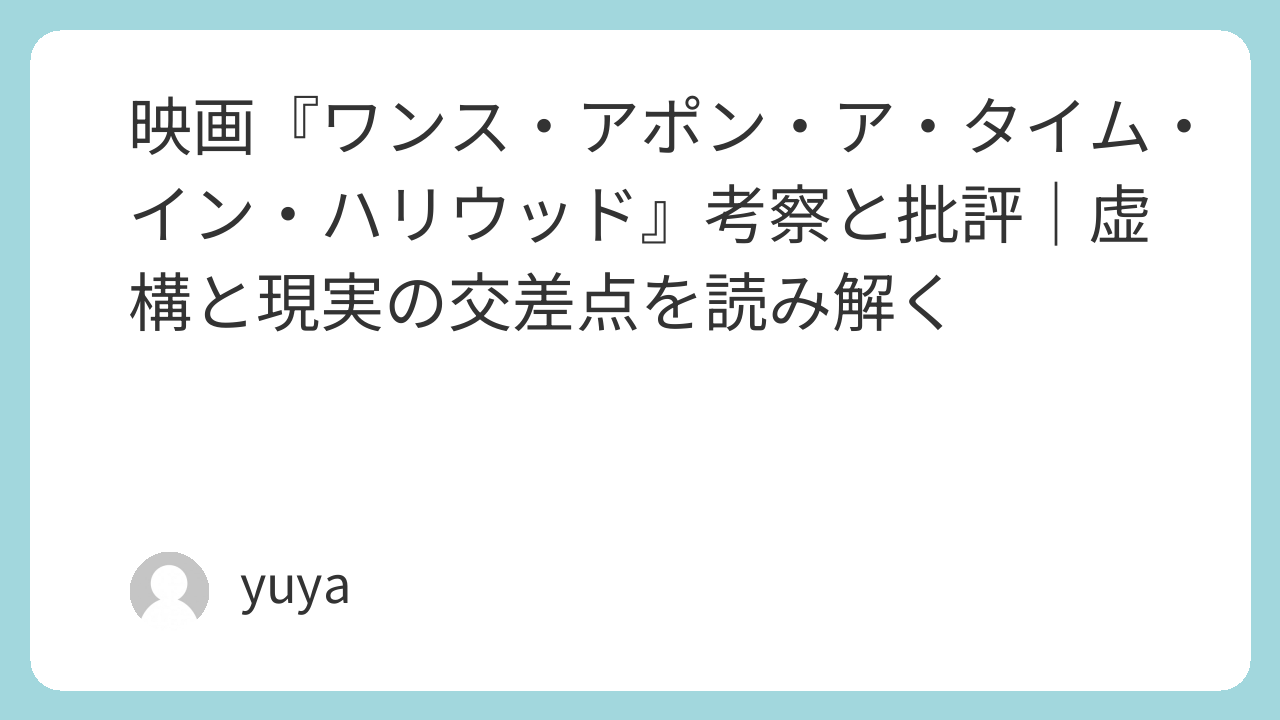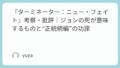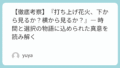クエンティン・タランティーノが監督・脚本を務めた『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019年)は、1969年のロサンゼルスを舞台にした“オルタナティブ・ヒストリー(もう一つの歴史)”映画です。実在の女優シャロン・テートと、彼女を襲った凄惨な事件を軸にしつつ、フィクションである二人の男、リック・ダルトンとクリフ・ブースの友情が描かれます。
この作品は、ただの“映画愛”の詰まったノスタルジー作品にとどまらず、現実と虚構の境界を問い、暴力と正義、メディアと記憶の関係性を描き出す深いテーマを含んでいます。本稿では、物語構造やキャラクター分析、演出面から本作を多角的に考察・批評します。
物語構造と時系列の崩し — フィクション×実話の交錯
本作では、実際に起きた「シャロン・テート殺害事件」を背景にしながら、フィクションであるリックとクリフの物語が並行して進行します。時系列はおおむね順行していますが、細かく挿入される劇中劇や回想シーン、テレビ番組のパロディといった演出により、観客は「どこまでが現実か?」という感覚を揺さぶられます。
特に注目すべきは、「史実をなぞる」のではなく、「歴史を改変する」点です。シャロンが殺されないという結末は、タランティーノ流の“映画的正義”の表明とも言えます。史実を壊すことで、失われた未来を取り戻そうとする意志すら感じられます。
シャロン・テート事件の扱いと創作の“改変”
1969年に起きたシャロン・テート殺害事件は、アメリカ社会に深い衝撃を与えました。映画ではこの事件がメインではなく、“起こらなかった事件”として描かれています。マンソン・ファミリーの犯行は、リックとクリフによって偶然阻止され、シャロンは生き延びるのです。
この結末は賛否を呼びましたが、「映画という夢の力で歴史を書き換える」という強烈なメッセージが込められています。犠牲者を暴力から“救う”ことで、タランティーノは一種の追悼を行ったとも取れます。実際に、シャロンは映画内で一切暴力の対象にならず、むしろ「象徴的な平和の存在」として描かれています。
キャラクター分析:リック、クリフ、そして“傍観者”としてのシャロン
リック・ダルトンは過去の栄光にすがる落ち目の俳優。対するスタントマンのクリフ・ブースは、過去に殺人の噂もあるが、忠誠心と静かな強さを持つ男。この2人の関係性は“男の友情”という古典的テーマの再解釈とも言えます。
一方、シャロン・テートはあくまで傍観者として描かれ、彼女自身の視点が語られることはありません。これは一見して受動的な役割に見えますが、「悲劇を未然に防がれる未来の象徴」として、終盤で彼女が語りかける「Would you like to come in for a drink?」という一言は、歴史の可能性を開く“鍵”のようなものです。
映像表現・演出技法に見る“ハリウッド礼賛”と“過去への郷愁”
本作の魅力のひとつは、60年代末のハリウッドを細部にわたって再現した映像美にあります。ポスターやテレビ番組、ラジオ、車、看板のすべてが時代考証に基づいて再構築されており、観客はまるで当時の街を歩いているかのような没入感を味わえます。
また、劇中劇の撮影シーンを通じて、“作られた演技”と“素の現実”の対比を強調しており、これは「映画とは何か?」というメタ的な問いかけにもつながります。古き良き時代の“黄金のハリウッド”に対するノスタルジーと、それをスクリーンに焼き付けようとする執念が感じられます。
ラストシークエンスの意味とメッセージ — “おとぎ話”としての再構築
クライマックスのシーンでは、現実世界で起きた悲劇が、全く異なる形で描かれます。クリフの超人的な戦闘能力によって、マンソン・ファミリーの襲撃は失敗に終わり、リックとシャロンの未来が仄めかされます。
この結末は、まさに「ワンス・アポン・ア・タイム(昔々)」というタイトルが意味する“おとぎ話”の再構築であり、現実を超えて理想を描く「映画の力」の象徴です。タランティーノはこの作品を通して、映画が歴史を癒す手段になりうることを静かに語りかけているのです。
総括:フィクションの中にある“癒し”と“再生”
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は、ただの映画ファン向けの娯楽作ではなく、失われた時間へのオマージュであり、癒しの物語でもあります。タランティーノは暴力や栄光、友情と喪失といった要素を織り交ぜながら、私たちが忘れかけた“物語を信じる力”を再認識させてくれるのです。