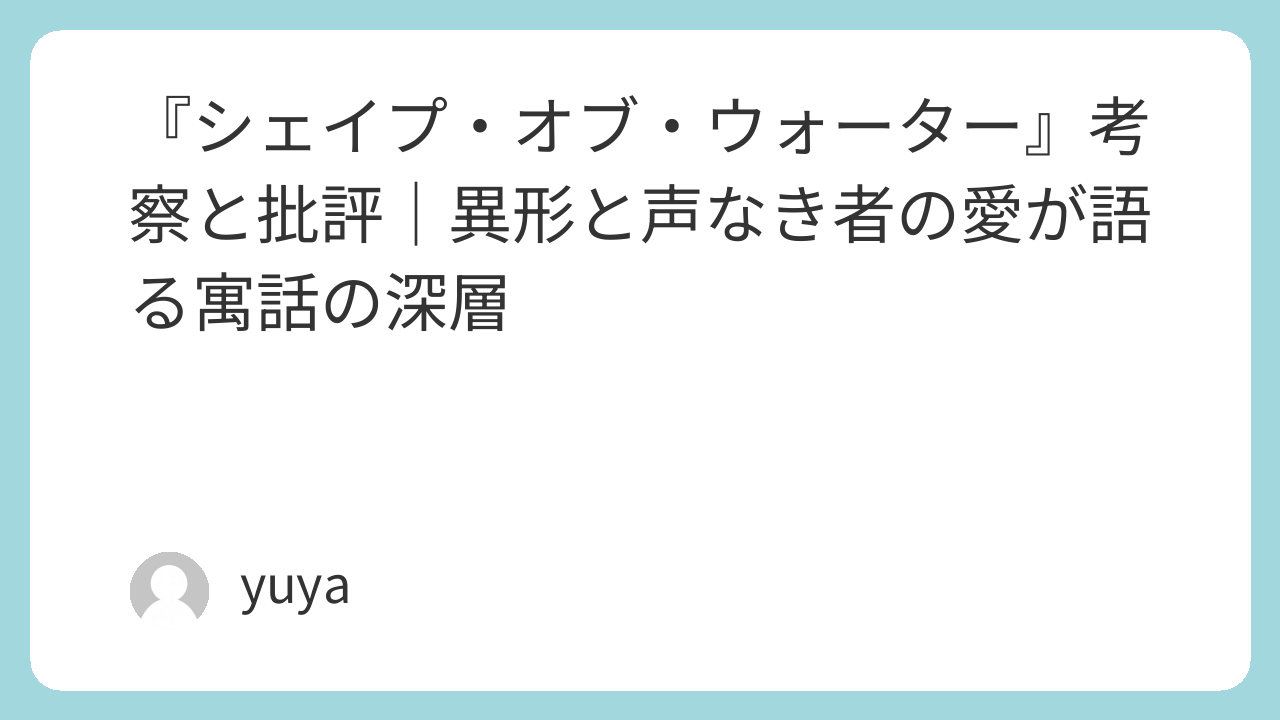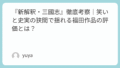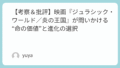ギレルモ・デル・トロ監督の映画『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017年)は、第90回アカデミー賞で作品賞・監督賞を含む4冠に輝いた傑作です。本作は、冷戦時代のアメリカを舞台に、言葉を持たない清掃員の女性と不思議な半魚人との間に芽生える愛を描いていますが、その背後には「声なき者」たちへの深い共感、そして寓話的な構造が緻密に仕込まれています。
本記事では、映画のテーマ性、象徴性、映像表現、キャラクターの意味などを深く掘り下げていきます。
物語構造と寓話性 ― “おとぎ話”としての再解釈
本作は単なるラブストーリーではなく、明確に「おとぎ話」の構造を踏襲しています。ナレーションの導入、閉鎖空間の世界観、善悪の明確な対立、そして異種間の愛という設定は、古典的なファンタジーに見られる形式を持っています。
デル・トロは過去作品『パンズ・ラビリンス』でも現実の暴力と幻想を重ね合わせ、寓話的構造で深い社会批評を行いました。本作も同様に、「愛は形を持たない」「言葉ではない理解」というメッセージをファンタジー形式で観客に伝えています。
「声なき者たち」の視点とマイノリティ表象
『シェイプ・オブ・ウォーター』は、社会的に「語られることのない者」たちの物語です。主人公イライザは発話ができず、ゼルダは黒人女性、ジャイルズは同性愛者、そして半魚人は「異形の存在」として実験対象にされる存在です。
それぞれが周縁化された立場にありながら、物語の中心で互いを理解し支え合う姿は、現代社会におけるマイノリティの象徴でもあります。彼らの視点が世界を語ることで、「普通とは何か?」という問いが観客に突きつけられます。
タイトル「水の形」の意味と象徴性
“Shape of Water”というタイトルは一見矛盾したようにも感じますが、「形を持たない水=あらゆる形になれる柔軟性」と読み解くことで、その深い象徴性が見えてきます。水は包容力、流動性、変化、そして生命の源としての意味を持ちます。
この比喩は、イライザと半魚人の関係にも当てはまります。言語や種族の壁を越えた彼らの愛は、社会的枠組みに縛られない「水のような愛」そのものであり、形なきがゆえに本質的とも言えるのです。
イライザと“彼”の関係性/正体考察
物語の中で多くは語られませんが、イライザ自身の出自には神秘的な要素が仕込まれています。首元の傷、そしてラストで彼女が水中で呼吸を始める描写から、「彼女もまた人間ではないのでは?」という考察が成り立ちます。
この説を裏付けるように、彼女と半魚人の間には言葉を超えた強い結びつきが描かれ、彼女は水中で“本来の姿”に戻ったとも解釈できます。つまり、これは「異形の者同士」の再会であり、人間社会からの解放でもあるのです。
映像・色彩・性表現によるテーマ表現とその限界
本作の映像美は高く評価されており、青緑を基調とした冷たい色彩は水の世界や孤独感を見事に演出しています。反対に、敵役ストリックランドの登場シーンでは赤や黄が強調され、対照的な価値観を際立たせます。
また、性的描写に関しても大胆な表現が使われています。イライザの自慰描写や、半魚人との性愛シーンは、彼女の「人間性」や「欲望」を強く肯定するものでもあります。ただし、こうした描写に不快感を覚える観客もおり、評価が分かれる要素でもあります。
結論:『シェイプ・オブ・ウォーター』が問いかけるもの
『シェイプ・オブ・ウォーター』は、異形の者同士が築く愛の物語を通じて、「他者理解」「社会からの排除」「愛の本質」といったテーマに切り込んだ作品です。おとぎ話の形式を借りつつ、現代社会に潜む差別や孤独を鋭く描写するこの映画は、表面的な美しさ以上に多くの意味を内包しています。