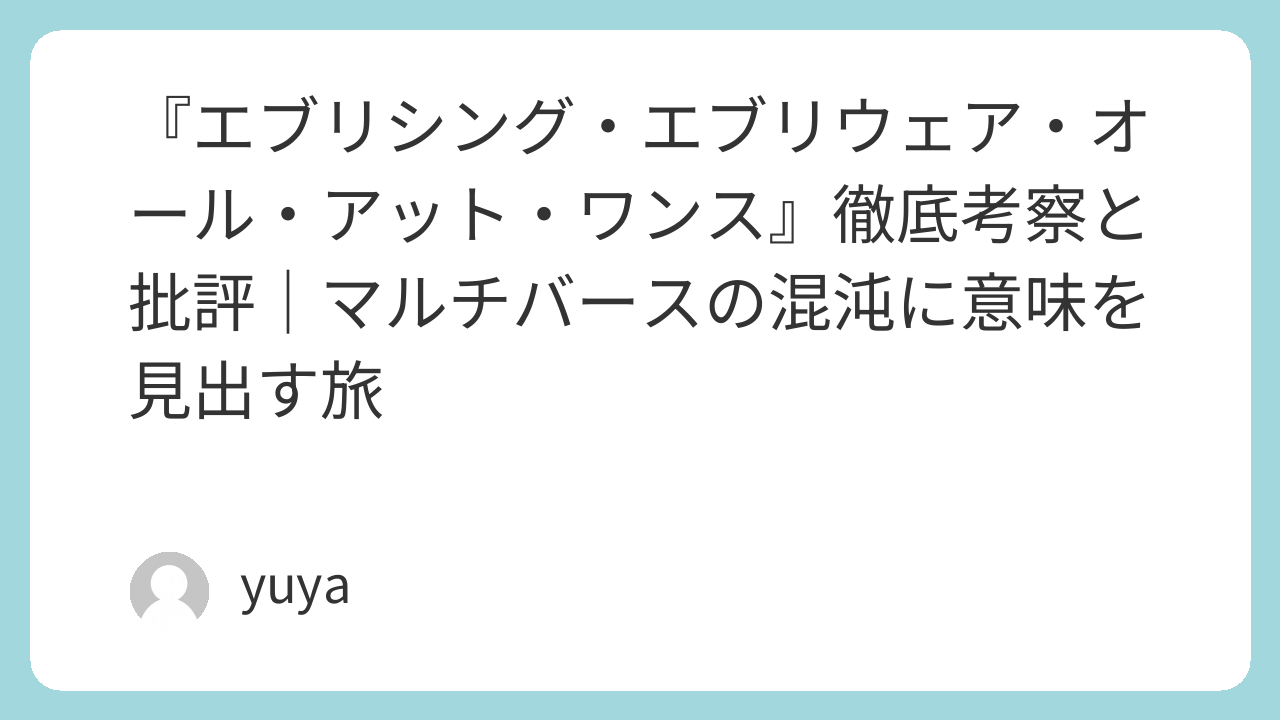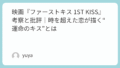2022年に公開され、アカデミー賞を含む数々の映画賞を受賞した『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』は、奇抜な演出と深いテーマ性で世界中の観客に強烈な印象を与えました。
一見カオスに満ちたこの映画は、ただのSFやアクション作品にとどまらず、「意味のある人生とは何か」「家族とは何か」といった根源的な問いを観客に投げかけてきます。この記事では、本作を深く掘り下げ、「考察」と「批評」の両面からその魅力と課題を検討します。
本作の基本情報とあらすじ:視点と構造を押さえる
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(原題:Everything Everywhere All at Once)は、ダニエルズ(ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート)監督による作品で、主演はミシェル・ヨー。舞台はアメリカに住む中国系移民一家の日常から始まり、突如、無数のマルチバースの世界へと物語が広がっていきます。
物語の軸は、主人公エヴリンが国税庁の監査を受けるところから始まり、やがて彼女が「多元宇宙を救う使命」を背負った存在であることが明かされます。ジャンルとしてはSF、アクション、コメディ、ファミリードラマと多彩でありながら、物語全体は「自己と他者の関係性」という一貫したテーマの上に成り立っています。
マルチバース構造と象徴モチーフの読み解き
本作を語るうえで欠かせないのが、マルチバースという構造的仕掛けです。エヴリンは並行世界の無数の自分自身とリンクし、それぞれの能力を獲得しながら戦います。これは表面的にはアクションの舞台装置ですが、裏には「人生の無限の可能性」と「選択と後悔」のメタファーが込められています。
象徴的なモチーフとして挙げられるのが「ベーグル」です。ジョブ・トゥパキ(娘ジョイの別人格)が作った“すべてを飲み込む黒いベーグル”は、意味や秩序を失った現代の世界観を象徴しており、同時に自己の虚無感も示唆しています。
一方、エヴリンが自ら選ぶ「目玉のステッカー」や「紙切れのような戦い」などの視覚的モチーフも、意味の構築と再生を暗示しており、映画全体を通して「秩序と混沌のせめぎ合い」が描かれています。
親子/家族関係とアイデンティティの葛藤
本作の核心は、エヴリンと娘ジョイの関係性です。世代、文化、価値観の断絶が彼女たちを遠ざけ、マルチバースでの対決はその象徴的な衝突となっています。とりわけジョイが抱える“何者にもなれない”不安と、“母親に認められたい”欲求は、多くの現代人が共感できる感情です。
また、エヴリン自身も「理想の人生を歩めなかった」という後悔を抱えており、それが彼女を多くの並行世界へと走らせます。夫ウェイモンドの優しさや父親との葛藤も、個人のアイデンティティ形成に強く影響しており、「家族」という閉じた空間がいかに複雑で、かつ救いとなるかが丁寧に描かれています。
虚無・混沌・意味の探求:ベーグルと虚無主義
先述の“すべてのベーグル”は、物語後半で虚無主義(ニヒリズム)の象徴として強く機能します。あらゆる可能性がある一方で、どれもが決定的な意味を持たない——この感覚は、現代社会に生きる私たちの漠然とした不安とよく重なります。
しかし、本作は単なる絶望には終わりません。エヴリンは虚無を受け入れたうえで、「小さな優しさ」や「今ここの選択」にこそ価値があると気づきます。これは、ニヒリズムを乗り越える一つの処方箋として、多くの観客に深い余韻を残しました。
批評的視点:評価の分かれるポイントとその理由
絶賛を受けた一方で、本作には否定的な意見も存在します。特に次のような点が批判対象となることがあります:
- 過剰な情報量とカオスな構成により、視聴者が置いてけぼりになる
- コメディとシリアスが混在し、トーンが不安定
- 説教的と感じるテーマの押し付けがましさ
一方で、これらの特徴こそが“現代的”であり、“すべてが一度に起こる世界”を体現した表現であるという擁護もあります。アート作品としての挑戦性と、一般観客との接続性、その両立の難しさが本作の議論を呼ぶポイントとなっています。
🔑 Key Takeaway
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』は、混沌と秩序、家族と孤独、意味と虚無といったテーマを、マルチバースという大胆な構造を通じて描いた野心的な作品です。
視覚的にも構造的にも過剰であるがゆえに、観る者に深い問いを投げかけ、観るたびに新しい発見がある映画です。
「人生の意味とは?」「小さな選択にこそ価値があるのでは?」といった問いを抱えるすべての人に、ぜひ一度体験してほしい一作です。