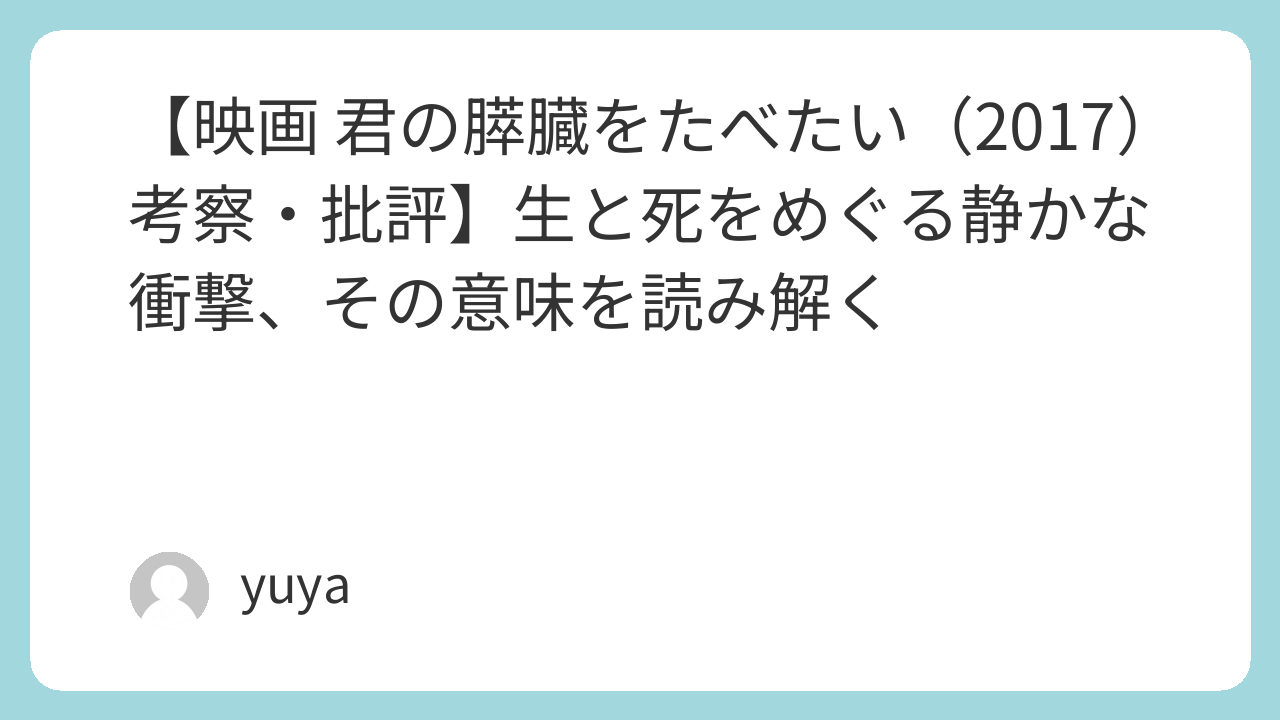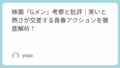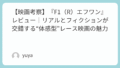2017年に公開された映画『君の膵臓をたべたい』(通称「キミスイ」)は、住野よるによる同名小説を原作とし、儚くも鮮烈な高校生2人の交流を描いた青春ドラマです。タイトルのインパクトに引かれて観た人も多いでしょうが、観終えた後には「死とは何か」「生きるとはどういうことか」と深く考えさせられる作品でもあります。
本記事では、原作との違いを踏まえつつ、登場人物の心理描写、構造的な演出、映像と演技、そして批判的な視点からも掘り下げて、「映画 君の膵臓をたべたい(2017)」の本質に迫ります。
原作 vs 映画:改変点とその効果を読み解く
映画版『キミスイ』の大きな特徴の一つは、原作にはない“12年後の僕”という未来パートが挿入されている点です。これは小説には存在しない要素であり、映画オリジナルの改変です。
- 原作では高校時代の回想のみで完結しているが、映画では現在の“僕”が母校を訪れるシーンから始まり、過去との対比がなされている。
- 12年後の“僕”が教師として再び過去と向き合う構造により、「記憶の中の桜良」から「未来に活きる桜良」へと昇華されている。
- 映画独自の演出によって、“僕”が桜良から受け取ったメッセージをどう活かしたかが明確になり、観客への訴求力が高まっている。
この改変は賛否あるものの、映画という時間的制約のあるメディアで「成長」を視覚的に伝える手法としては成功しているといえるでしょう。
登場人物の心理とモチーフ:死・時間・後悔の響き
この物語の根幹にあるのは、桜良の死を巡る時間との対峙、そして“僕”の心の変化です。
- 桜良は膵臓の病気を抱え、余命が限られていることを悟りながらも明るくふるまう。それは死を受け入れる強さであり、生を楽しむ意志の現れ。
- 一方で“僕”は、人と関わらないことを選んできた孤独な存在。桜良の死によって初めて「つながること」の価値を痛感する。
- タイトルの「君の膵臓をたべたい」は、古代の言い伝えを通じて「相手の命を受け継ぐ」寓意が込められている。
桜良の手紙には、“僕”という存在が彼女にとって特別だったという真実があり、その事実が“僕”の生き方に強く作用していく様が、非常に繊細に描かれています。
語り構造と時間軸:回想・現在描写の演出を考察する
映画版『キミスイ』は、過去と現在の時間軸が交錯する構成を採用しており、物語のテーマ性をより強く浮かび上がらせています。
- 現在パートでは教師となった“僕”が母校を訪れ、桜良との記憶に再び触れることで物語が動き出す。
- 回想シーンは桜良との出会い、図書館での交流、旅行、そして別れまでを丁寧に積み重ねており、観客は“僕”と共にその記憶を追体験する。
- 特にラストの手紙のシーンでは、時間が一気に巻き戻り、感情のピークを迎える構造が用いられている。
この時間軸の操作は、観客に「記憶とは何か」「時間が人をどう変えるか」といった問いを自然に投げかける巧みな演出となっています。
映像演出・キャストの力量:表現と説得力を問う
映画としてのクオリティを支えているのは、映像美と俳優陣の演技の説得力です。
- 小栗旬演じる未来の“僕”と、北村匠海演じる高校時代の“僕”のキャスティングは好対照でありながら自然な連続性を感じさせる。
- 浜辺美波が演じる桜良は、原作の“明るさ”と“繊細さ”を見事に体現しており、視線の使い方や声のトーンなどに細やかな感情が込められている。
- 映像は非常に抒情的で、特に旅行先の風景や学校での光の描写が“儚さ”を強く印象づける。
また、主題歌であるMr.Childrenの「himawari」も、本編と感情的にシンクロしており、映像体験を一層深める要素となっています。
批評視点:感動押し・ご都合主義・観客への訴求を検証する
一方で、感動を狙いすぎているとの批判や、物語構造の不自然さを指摘する声も少なくありません。
- 桜良の死が「通り魔によるもの」という点は、ご都合主義的で唐突という評価もあり得る。
- 12年後のパートが蛇足に感じる人もいて、物語の純粋性が損なわれているという意見も存在。
- また、「泣かせよう」という意図が前面に出過ぎていて、観客にとっては押し付けがましく感じる場合もある。
こうした批判も踏まえると、映画は決して“完璧”ではないものの、感情と演出のバランスを保ちながら、多くの観客に届く普遍性を持っているといえるでしょう。
まとめ:『君の膵臓をたべたい』が私たちに遺すもの
『君の膵臓をたべたい』という作品は、単なる感動作ではありません。死を前提とした人生の中で、誰かと心を通わせることの尊さ、そしてその記憶が未来にどう影響を与えるのか――。
生と死の対話、生きる意味、時間の流れ。これらを一つの青春物語の中で丁寧に描き出した本作は、観る人の心に深く刻まれる映画であることは間違いありません。