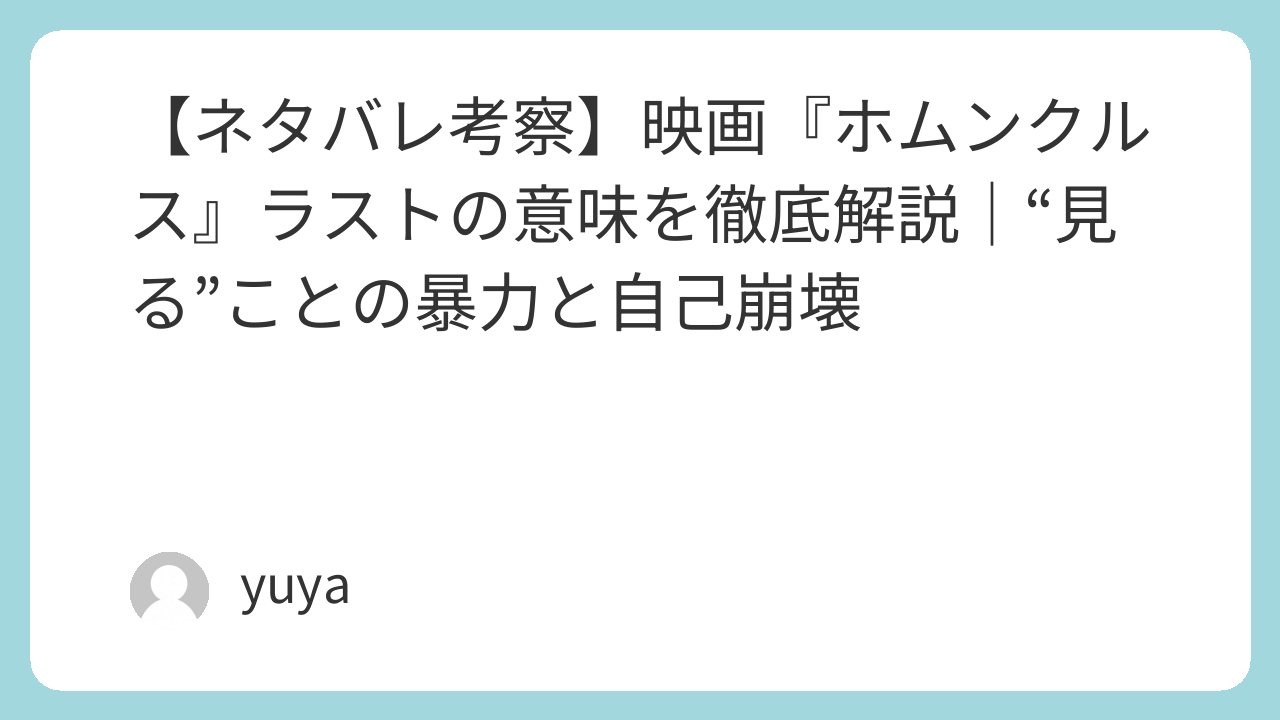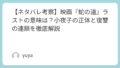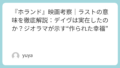映画『ホムンクルス』は、トレパネーションをきっかけに「人の内面が異形として見える」ようになった名越進を通して、私たちの“視線”そのものを問い直す作品です。
本記事では、タイトルが示す意味、ホムンクルスの象徴表現、名越と伊藤の関係性、そして賛否が分かれるラストシーンまでをネタバレありで整理。さらに原作漫画との違いにも触れながら、映画版が最終的に何を描こうとしたのかを深掘りしていきます。
「結局あの結末は救済なのか、破滅なのか?」と感じた方は、ぜひ最後までご覧ください。
映画『ホムンクルス』の基本情報とあらすじ
『ホムンクルス』は、山本英夫の同名漫画を原作にした実写映画で、2021年4月2日に公開されたサイコミステリー作品です。主演は綾野剛、監督は清水崇。上映時間は115分、PG12指定です。
Netflixでも作品ページが公開されており、ジャンルはホラー/サスペンス/ミステリーとして整理されています。
物語は、車上生活を送る記憶喪失の男・名越進が、医学生の伊藤学に“トレパネーション(頭蓋骨に穴を開ける施術)”を持ちかけられるところから始まります。報酬は7日間で70万円。手術後、名越は右目を閉じて左目で見ると、人間が異形に見える現象を体験し始めます。伊藤はそれを「深層心理の視覚化」だと説明し、その異形を“ホムンクルス”と呼びます。
この導入が秀逸なのは、「現実を見ているつもりの私たち」に対して、そもそも“見える”とは何かを最初から揺さぶってくる点です。以降の展開は、サスペンスでありながら自己認識の物語へと重心が移っていきます。
タイトル「ホムンクルス」が示す意味とは?
“Homunculus”はラテン語由来で「小さな人」を意味し、歴史的には錬金術・生物学・神経科学など複数の文脈で使われてきた語です。
映画ではこの語が、単なる怪異の名前ではなく、人間の内面が歪んだかたちで立ち上がる存在として再定義されています。
つまり本作の「ホムンクルス」は、モンスターではなく“心の翻訳結果”です。
他人の中に見える異形は、見られる側の問題であると同時に、見てしまう側(名越)の問題でもある。この二重構造が、作品全体の不気味さを生みます。
タイトルをこう読めると、本作は「超常現象の映画」ではなく、視覚化された心理劇だと理解しやすくなります。怖さの本体は幽霊ではなく、説明しづらい劣等感・羞恥・抑圧です。
トレパネーション(穿頭)が物語で果たす役割
作中の起点になるトレパネーションは、医学史上も“頭蓋骨に孔を開ける処置”として知られる概念です。歴史的にも古くから記録があり、現代医療では適応を伴う外科的処置として位置づけられます。
映画でも「頭蓋骨に穴を開ける手術」という設定が明確に示されています。
ただし本作で重要なのは医学的正確性そのものではなく、“頭に穴を開ける”という境界突破のメタファーです。
理性のフタが外れ、社会的に整えられた自己像の下にある生々しい衝動や傷が露出してしまう。手術はそのスイッチとして機能しています。
言い換えると、トレパネーションは“能力獲得イベント”ではなく、自分の見たくないものまで見えてしまう地獄の入口。ここをどう読むかで、作品の印象が大きく変わります。
名越進という人物の正体と「空白の自己」
名越は記憶を失い、社会的な座標も曖昧なまま生きています。さらに「車上生活だが金はある」という不自然な状態で、最初から“所属不能”な人物として描かれます。
この設定が、彼を「観察者」であると同時に「被観察者」にしているのが巧みです。
彼が他人の深層心理を見るたび、実は逆向きに自分の深層へ追い詰められていく。
他人を診断しているようで、自分の亀裂をなぞっている――この反転が中盤以降の推進力になります。
名越の魅力は、ヒーロー性ではなく“空白”にあります。
善悪や常識に回収されない存在だからこそ、観客は彼に自己投影しやすい。結果として「私が見たくない私」を突きつけられる体験になっていきます。
伊藤学は“案内人”か“扇動者”か
伊藤は名越に手術を提案し、現象を理屈づける役回りを担います。物語上、彼は科学的説明の窓口でありながら、同時に主人公を危険領域へ押し込む触媒でもあります。
この両義性が、伊藤を単なる相棒にしない理由です。
彼を“研究者”として読むと、物語は人体実験スリラーになります。
一方、“救済を求める者”として読むと、名越と伊藤は鏡像関係に見えてきます。どちらも自分の欠落を埋めるため、他者を装置化してしまうからです。
この人物の怖さは悪意の強さではなく、正しさへの執着です。
「解明したい」という欲望が倫理を越える瞬間、本作はホラーよりも現実的な恐怖を帯びます。
ホムンクルスのビジュアルは何を象徴しているのか
映画版のホムンクルスは、VFXや特殊スタイリングを使って具体的な異形として提示されます。スタッフ情報にも特殊スタイリストやVFX担当が明記されており、“見える恐怖”を設計していることがわかります。
つまり本作は、心理描写を抽象で逃がさず、あえて具象化する戦略をとっています。
ここで大事なのは、「正解当て」をしすぎないことです。
各異形は一対一の記号ではなく、羞恥・怒り・依存・自己否定といった複数の感情が混ざり合った像として見る方が、作品の温度に合います。
ホムンクルスの造形は、観客の中にも“解釈の鏡”を作ります。
同じシーンでも「かわいそう」と感じる人と「怖い」と感じる人が分かれるのは、観客自身の内面が反応しているからです。ここに本作の面白さがあります。
ラストシーンの考察:救済か、さらなる迷宮か
終盤の名越は、真実へ近づくほど安定を失っていきます。
これは「知ることは自由」という常識を反転させる設計です。見えるようになるほど、人は必ずしも楽にならない。むしろ“見えた後をどう生きるか”という、より重い問いが始まります。
ラストを救済と読むなら、名越は“虚構に守られた自己”から降りる決断をした、と言えます。
反対に破滅と読むなら、現実と幻の境界を失い、戻れない場所へ踏み込んだとも解釈できます。
本作が優れているのは、どちらか一方に固定しない点です。
観客の状態によって結末の明度が変わる――この“可変するラスト”こそ、ホムンクルス的な終わり方だと思います。
原作漫画との違いと映画版オリジナル要素
原作は山本英夫による長編で、公式情報でも全15巻とされています。
一方、映画は115分という尺に圧縮されるため、人物の背景や心理の掘り下げは“選択と集中”で再構成されています。
映画.comの関連ニュース欄でも、映画版に原作にないオリジナル展開があることが示されています。
このため、原作ファンほど「省略」と「改変」を気にしがちですが、映画は映画としてテーマを一点突破させたと見るのがフェアです。
要するに、原作が“長距離走”だとすれば、映画は“短距離走”。
同じゴールを目指すのではなく、別メディアとして同じ核心(人間の深層)を別角度から撃ち抜く作品になっています。
『ホムンクルス』が突きつけるメッセージ
この映画の本質は、「怪物がいる」ではなく「怪物に見えてしまう心がある」です。
他者理解のつもりで行っていることが、実は自己防衛や支配欲かもしれない。そんな不快な可能性を観客に返してきます。
だから本作は、視聴後に“答えが出る映画”ではありません。
むしろ「自分は他人をどんな目で見ていたか」を反芻させる映画です。見終わってから効いてくるタイプの一本だと言えます。
ブログ読者向けに締めるなら、次の一文が刺さります。
「ホムンクルス」とはスクリーンの中の異形ではなく、私たちの日常の視線そのものなのかもしれない。