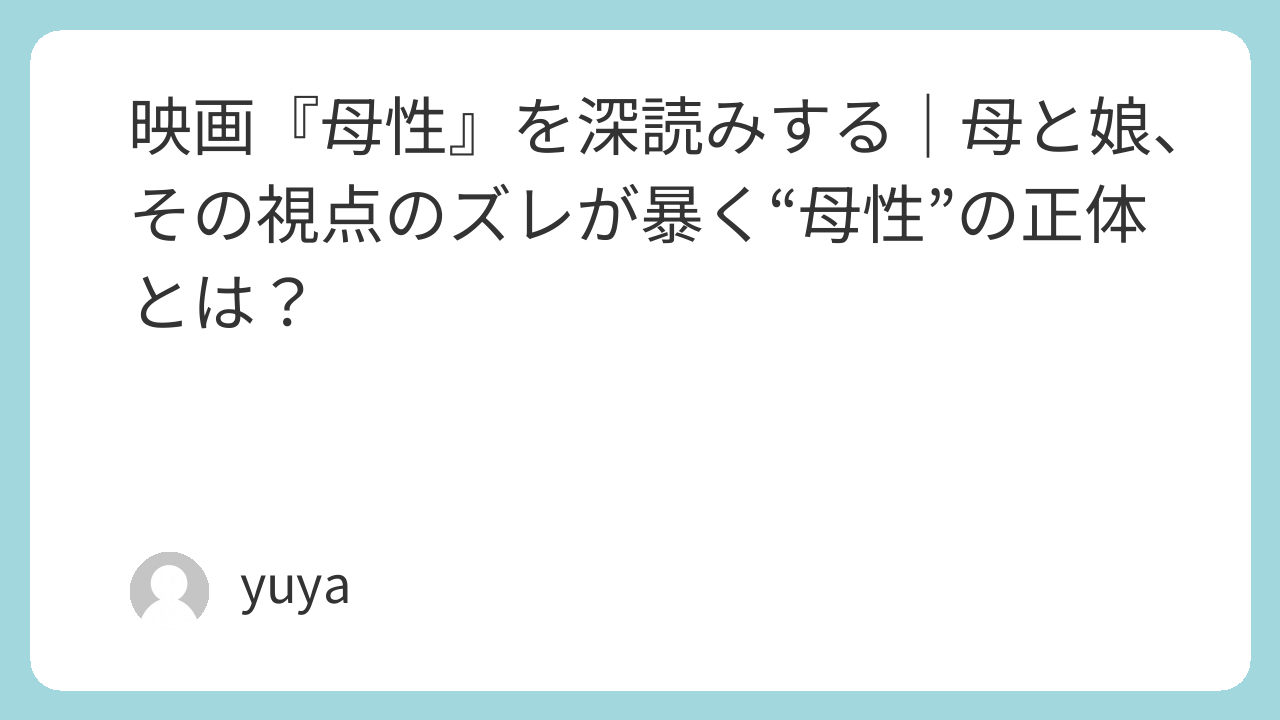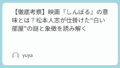「母性」とは、一見して普遍的な愛の形のように語られます。しかし、映画の中で描かれる「母性」は常に揺らぎ、時には暴力や呪縛として立ち現れることもあります。2022年に公開された映画『母性』(原作:湊かなえ)をはじめ、多くの映画がこのテーマに挑んでいます。本記事では、映画作品における母性の多面性を読み解いていきます。
母性をめぐる映画での〈語り手・視点〉の構造
『母性』の大きな特徴は、母親と娘の両方の視点から物語が語られる点にあります。章ごとに母と娘が交互に語り手を務める構成は、同じ出来事の“真実”が誰の視点かによって全く異なるという構造的トリックを成立させています。
この視点の交錯は、母性という概念が「一方的に押し付けられるもの」ではなく、「関係性の中で立ち現れるもの」であることを示唆しています。母は自分の行為を「愛」と認識していても、娘にとっては「支配」として受け取られる。観客はそのズレを通して、母性の複雑さと危うさに直面するのです。
“母/娘”関係における母性の変奏―愛・無償・コントロール
映画で描かれる母性の代表的なモチーフのひとつが、“無償の愛”という美名の裏に潜むコントロールの構図です。『母性』において、母親は娘を心から守ろうとする一方で、無意識のうちに自らの価値観を押し付け、娘の人生の自由を奪っていきます。
これは『八日目の蝉』『誰も知らない』など、他の邦画作品にも共通するテーマです。母親の「こうあるべき」という価値観は、時として子どもの成長を妨げます。それでも母親自身はそれを「愛」と信じて疑わない――そこに母性の盲点が存在します。
このように、映画は母性の一側面を“加害”としても描くことによって、私たちに問いを投げかけます。それは「本当に無償の愛など存在するのか?」という普遍的なテーマに接続しているのです。
「母性とは何か?」―母であること/母になることを超えて
映画『母性』の最大の問いは、「母親であること」と「母性を持つこと」が必ずしも一致しないという点です。作中、母は「母になりきれなかった自分」に苦悩しながらも、その役割を演じ続けます。そこには、社会的・文化的に求められる“理想の母像”が影のようにつきまとっています。
また、「母性は生まれながらに備わるものではなく、後天的に学ぶものだ」というテーマも印象的です。つまり、母性は本能ではなく、時に矛盾し、葛藤し、社会に規定される「役割」であることが示されているのです。
この視点は、「母になること」に不安を抱く多くの女性にとって、救いとなる可能性があります。母であることを義務とせず、母性を“選択可能な態度”として考えることが、新しい生き方の提案となるのです。
映像表現・構成が語る母性の“ズレ”と“呪縛”
映画『母性』は、その構成と演出を通して、言葉では語られない母性の「重さ」を表現しています。章ごとの視点切り替えや、寒色系で統一された映像美、カメラの静止的な画作りなどが、観る者に不穏な空気を伝えます。
たとえば、母親の語りの場面では柔らかく光を取り入れ、娘の視点では冷たさと疎外感が際立つ構図にすることで、同じ家庭内の空気がまったく異なるものとして描かれます。こうした演出により、母性というテーマは視覚的にも“異物”として浮き彫りになります。
また、ラストに向けて語られる「真実」もまた、多くを語らず観客に想像させる余地を残します。この“空白”こそが、母性というテーマの複雑さを最も雄弁に語っているのかもしれません。
鑑賞後に残る問い―観客としての“あなた”と母性の関係
本作を観終えた後、最も残るのは「自分だったらどうするだろう」「私の母はどうだったか」という、個人的な問いです。これは単なる“他人事の物語”ではなく、自らの経験や記憶を照らし返す「鏡」のような作品なのです。
母親との関係に悩んだことのある人、親になることに不安を抱える人、あるいは過去の家族とのすれ違いを思い出す人――『母性』はそれぞれの心の奥に、そっと言葉にならない問いを置いていきます。
このように、観客それぞれの人生経験によってまったく異なる解釈が生まれる作品こそが、「母性」というテーマの豊かさと奥行きを証明しています。
まとめ:母性とは「与えるもの」ではなく、「問い直すもの」
「母性 映画 考察」というテーマを通して見えてくるのは、「母性」は一枚岩の概念ではないという事実です。それは時に優しさであり、時に重荷であり、そして何より“語られ方”によって形を変えていく存在です。
映画は、私たちに「母性とは何か?」を答えとしてではなく、“問い”として提示してくれます。その問いにどう向き合うかは、観客一人ひとりの生き方と深く関わっているのです。