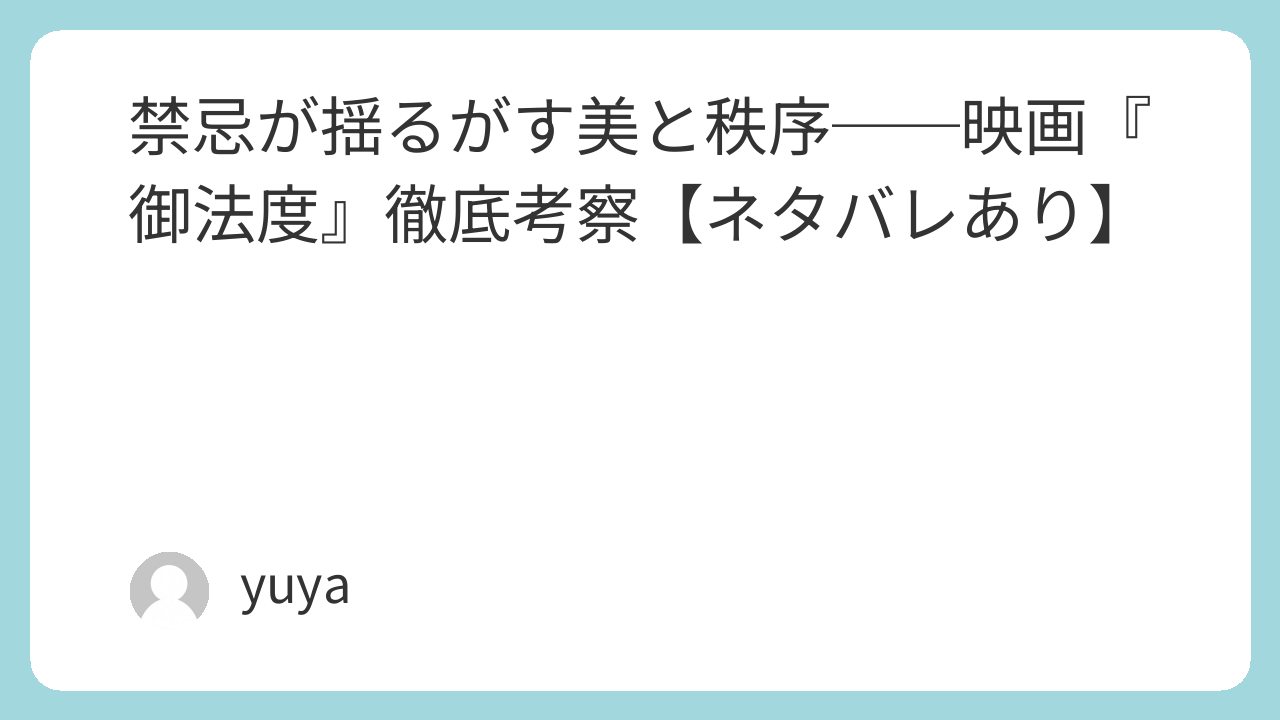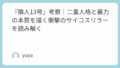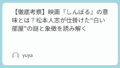1999年に公開された大島渚監督の映画『御法度』は、新選組を舞台にした時代劇でありながら、一般的な“剣と忠義”の物語では終わりません。そこに描かれるのは、男色=衆道という禁忌の関係、そしてそれをめぐる欲望、嫉妬、そして崩壊へのプロセスです。本記事では、『御法度』の魅力とその奥深い主題を、5つの観点から考察していきます。
新選組という組織空間を舞台に──あらすじと登場人物の役割
物語の舞台は幕末の京都。厳格な掟を持つ新選組に、美貌の若者・加納惣三郎(松田龍平)が入隊することで、物語は始まります。彼の存在が、既存の隊内秩序を揺るがせる契機となるのです。
・土方歳三(ビートたけし)は組織の掟を重視する冷徹な指導者。
・沖田総司(武田真治)は明朗で人気のある人物ながら、惣三郎に心を乱されていく。
・田代彪蔵(浅野忠信)は、惣三郎に対し敵意と執着を抱く複雑な存在。
このように、『御法度』は単なる歴史劇ではなく、「閉鎖的な男性集団に異物が投じられることで内部崩壊が起こる」という心理劇としての構造を持っています。
「衆道/男色」が掘り下げる権力・欲望・抑圧の構図
『御法度』の主題の一つが“衆道(しゅうどう)”――武士同士の男色文化です。特に惣三郎をめぐる男たちの反応は、単なる性愛を超えた政治的・心理的な意味を持ちます。
・沖田の惣三郎への親密さは、無邪気であるがゆえに危うい。
・田代の嫉妬心は、自己抑圧と同性愛への葛藤を映し出す。
・土方の冷酷さには、組織維持のために情を切り捨てる論理がある。
このように、惣三郎は“美”の象徴であると同時に、“秩序を破壊する存在”でもあります。映画の原題「御法度(ごはっと)」=“掟破り”は、まさにこのテーマの核心を突いています。
桜の木、赤白袴、髪型…象徴としての映像・衣装・肉体
大島監督は、台詞よりも視覚的な象徴性を重視する演出家です。本作でも、シーンの随所に美術的・象徴的なモチーフが織り込まれています。
・惣三郎が最初に現れる桜の木の下──“死と美”の予兆。
・赤と白の袴の対比は、純粋と欲望、聖と俗の緊張関係を表す。
・髪型や所作のディテールが、各人物の内面や立場を映し出す。
特に松田龍平演じる惣三郎の“無垢な肉体”の描き方は、見る者の欲望をも映す鏡となっており、鑑賞者自身の視線をも問う構造です。
ラストシーンの意味と「切断/再生」のモチーフ
終盤、惣三郎と沖田は命を落とし、新選組内部のバランスは大きく崩壊します。このラストは、単なる悲劇ではなく、「再構築される秩序と新たな禁忌の成立」を示唆します。
・惣三郎の死によって、隊の崩壊は防がれたのか?
・沖田の死に際しての微笑みには、何が込められていたのか?
・土方の「御法度」としての断罪は、本当に正しかったのか?
観客に残るのは、単純な結論ではなく、「この社会において本当に守るべきものは何か?」という問いかけです。
映像・演出・音楽で味わう異色の時代劇――監督・俳優・撮影陣の技法
『御法度』は、大島渚監督の遺作であり、その演出には老練かつ挑発的な美学が凝縮されています。
・照明と陰影の使い方による心理の映像化。
・坂本龍一による音楽は、時代劇の枠を超えた前衛性を与える。
・キャスティングの妙(若き松田龍平とベテラン俳優の対比)が緊張感を生む。
特に、セリフに頼らない“空白”や“静寂”の演出は、映画全体に張り詰めた緊張をもたらしており、時代劇でありながらも現代的な芸術映画の趣を持っています。
【まとめ】『御法度』が描いたのは「欲望と秩序」の普遍的な対立構造
『御法度』は単なる時代劇ではなく、美・欲望・禁忌といった普遍的なテーマを掘り下げた作品です。男性のみの閉鎖空間に“異物”が現れることで引き起こされる破壊と再生のドラマ。その構造は現代にも通じる寓話性を帯びています。
映画を通して見えてくるのは、「社会における掟とは誰のためのものなのか」「美はなぜ破壊をもたらすのか」という深い問いです。ぜひ多くの視点で、この映画の持つ奥深さに触れてほしいと思います。