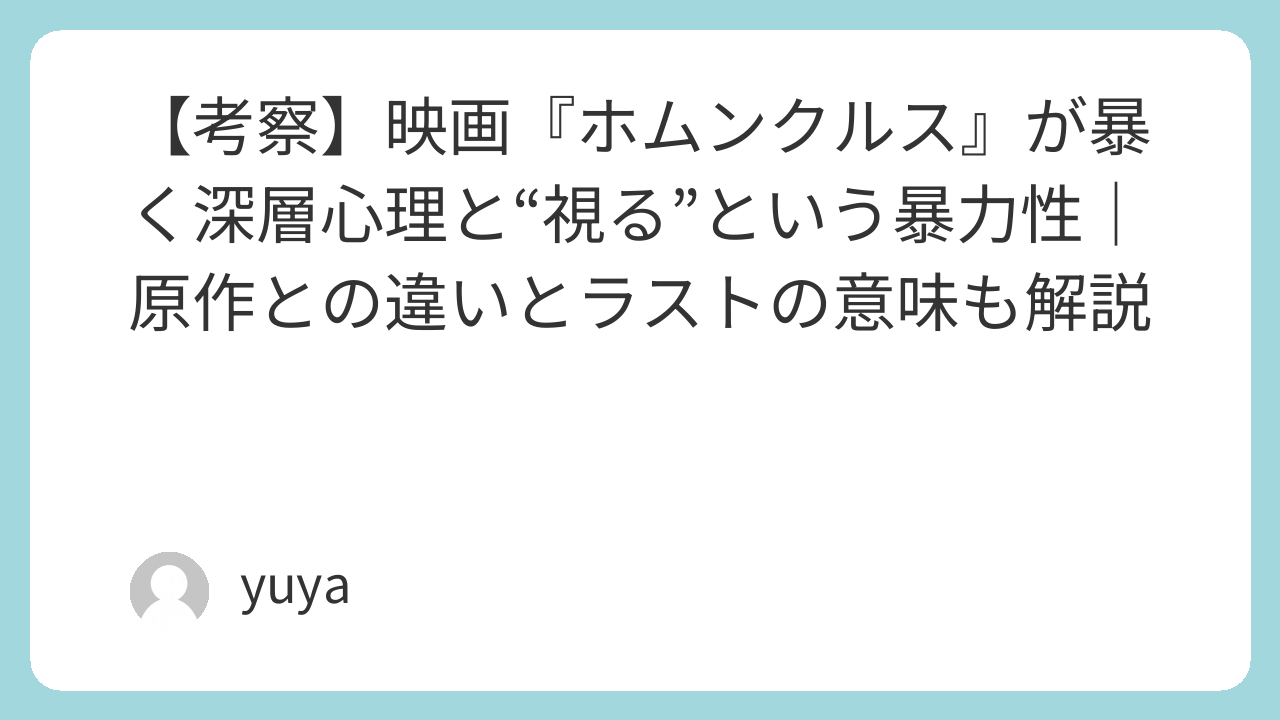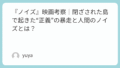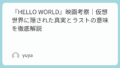2021年に公開された映画『ホムンクルス』は、山本英夫による同名の漫画を原作とし、綾野剛を主演に迎え、Jホラー界の巨匠・清水崇監督が手がけた異色のサイコサスペンスです。「人間の深層心理が視覚化される」という大胆な設定と、トレパネーションという実在の医療行為を題材にしたストーリーは、多くの観客に衝撃と混乱を与えました。本記事では、映画『ホムンクルス』を多角的に考察し、原作との違いや映像表現、ラストの解釈などについて掘り下げていきます。
「トレパネーション」手術という装置:映画における“穴を開ける”意味とは?
物語の発端となるのは、主人公・名越進が頭蓋骨に穴を開ける「トレパネーション」の手術を受ける場面です。これは実在する古代からの治療行為であり、現代でも一部では“意識の拡張”を目的に行われることがあります。映画では、この手術を受けたことにより、名越は人間の心の奥底に潜む“ホムンクルス”を見ることができるようになります。
トレパネーションが象徴するのは、「理性の殻を破ること」、あるいは「社会的常識からの逸脱」です。名越が見る異形の人々は、彼らのトラウマや抑圧された感情の投影であり、現実と幻想の境界が曖昧になっていきます。この“穴”は、視覚の変容だけでなく、名越自身の人格の崩壊をも暗示しているのです。
原作漫画と映画版の対比:何が省略/改変されたかを読み解く
原作の『ホムンクルス』は全15巻からなる長編であり、映画版ではそのうちの一部のみが描かれています。大きな違いの一つは、物語の結末に向かう展開の省略です。原作では名越の過去や、ホムンクルスを“見る力”がもたらす影響、人間関係の複雑な変化が丁寧に描かれていましたが、映画では短い尺の中での収束を余儀なくされています。
特に、原作の伊藤との関係や、名越の“深層心理へのダイブ”があっさりと終わる印象を受ける観客も多かったでしょう。映像作品として再構築するために大胆な編集がなされたことは理解できますが、その分、テーマの深掘りが浅くなってしまったという声も少なくありません。
“見る/見られる”という視覚モチーフ:ホムンクルス=深層心理の可視化
映画『ホムンクルス』の核心にあるのは、「視覚」の問題です。名越が他人のホムンクルスを見るという能力は、実際には“深層心理を可視化する”という超常的な行為であり、そこには「観察する者」と「観察される者」の非対称性が存在します。
ホムンクルスたちは象徴的な造形で描かれます。たとえば、自分の存在価値を否定する女性はガラスの人形のような姿をしており、名越の視線がその“形”を暴くことで、その人物のトラウマが露呈します。これは、観察することで対象を支配しようとする近代的な“まなざし”への批判とも取れます。
同時に、名越自身もまた“見られる側”に変化していきます。伊藤や奈々子との関わりの中で、彼の視覚は次第に暴走し、現実を歪めてしまう。視ることの傲慢さ、そしてそこに潜む暴力性が浮き彫りになっていきます。
ラストの解釈と余白:名越・伊藤・奈々子の関係性をどう読むか?
映画の終盤では、名越の精神状態が臨界点に達し、現実と幻覚の区別がつかなくなります。伊藤との関係も対立的になり、彼を“ホムンクルス”として見るようになる展開は、名越が完全に常軌を逸していることを示唆します。
奈々子という存在もまた象徴的であり、名越が彼女に執着する姿勢は、自身の過去と罪への投影ともいえます。ラストシーンにおける彼の選択は、救済なのか破滅なのか、観客の解釈に委ねられた“余白”が残されており、それが本作の余韻を深めています。
映画が提示するのは「正解のない問い」そのものであり、視聴者が自らの感性で読み取ることを前提としているのです。
映像・演出・キャスト考察:綾野剛×清水崇が描く“歪んだ世界”の魅力
主演の綾野剛は、抑圧された感情と狂気の狭間に揺れる名越を見事に演じ切っています。目の奥に潜む不穏なエネルギーは、ホムンクルスという存在を“視る者”としての説得力を与えていました。
監督の清水崇は『呪怨』などで知られるホラーの演出家ですが、本作ではホラー演出を抑えつつも、陰鬱で不安定な空気感を巧みに作り上げています。映像の色調、間の取り方、音響設計が“精神の歪み”を映像的に表現しており、観る者に不快さと魅了を同時に与えます。
また、伊藤役の成田凌や、奈々子役の石井杏奈も、映画の不穏な世界観にリアリティを与える重要な存在となっています。
【まとめ:Key Takeaway】
映画『ホムンクルス』は、視覚と精神の関係性、そして人間の深層心理に鋭く切り込む作品です。トレパネーションという極端な装置を通じて「他者の本質を見ること」の危うさを描き出し、原作の哲学的テーマを映像ならではの手法で再構築しています。改変や省略により賛否は分かれるものの、「見る」という行為の本質と、そこに潜む暴力性を問う本作は、観る者の心にも“穴”を開けるような体験となるでしょう。