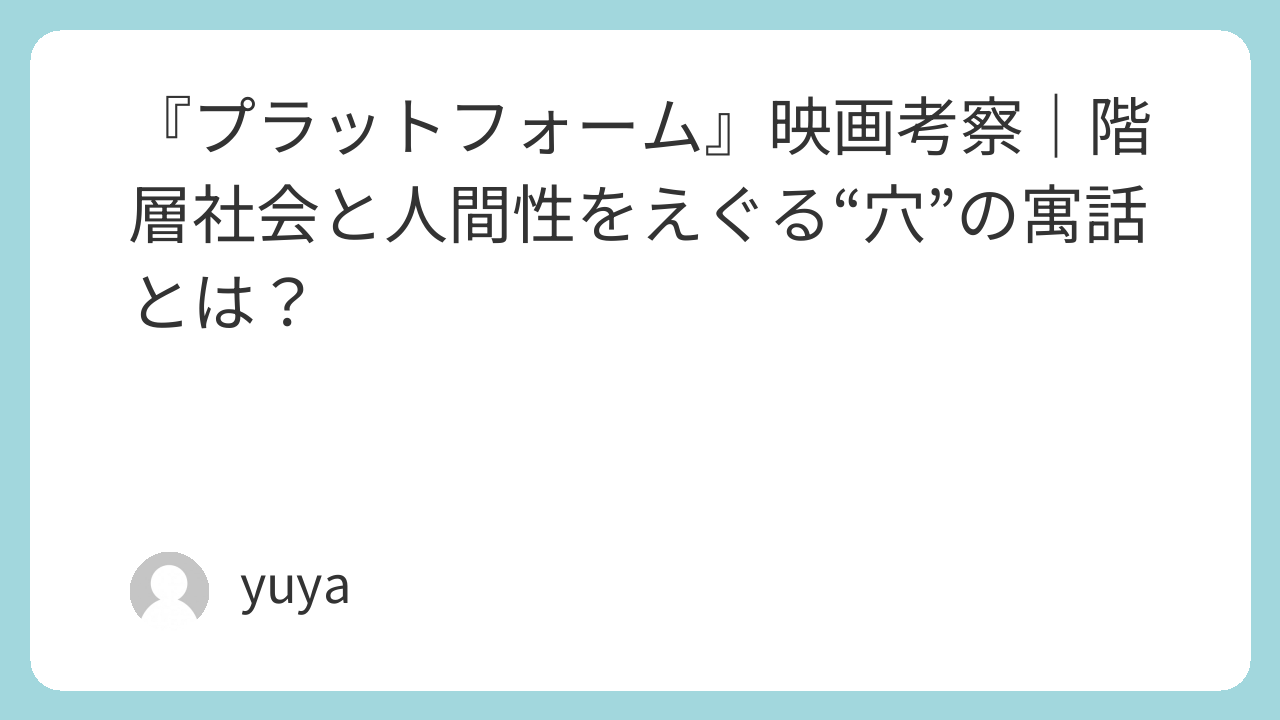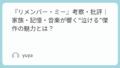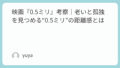Netflixで配信されたスペイン映画『プラットフォーム』(原題:El Hoyo)は、シンプルな舞台設定ながらも、深く哲学的で象徴的なテーマが詰まった作品です。
上下に連なる階層と、中央に空いた「穴」。その中で繰り広げられるのは、生き延びるために人間がどこまで堕ちるかという極限のドラマです。この記事では、映画『プラットフォーム』の構造や象徴を丁寧に読み解きながら、私たちの社会や生き方を改めて考えるための考察を展開していきます。
あらすじ再確認:穴(プラットフォーム)という構造の意味
映画の舞台は、中央に縦穴が貫かれた「縦型の牢獄」。各階層には2人ずつが収容され、毎日一度、上階から下階へと豪華な食事が乗った“プラットフォーム”が降下していきます。上層は贅沢三昧、下層には何も残らない――。
この仕組み自体が、本作の重要なメタファーであり、階層社会・貧富の格差・消費主義の風刺です。観客は、主人公ゴレンと共に“下へ下へ”と落ちていく体験を通じて、社会の不条理さと自身の在り方を突きつけられます。
階層社会と資本主義の風刺としての本作の読み解き
この作品が描いているのは、単なるサバイバルではありません。最上階の者が贅沢を享受し、下層の者には何も届かない――このシステムは、まさに現在の資本主義社会の縮図です。しかも、毎月ランダムに階層が変わるというルールは、「生まれつきの不平等」ではなく、「運」と「環境」に支配される現代社会の姿をより強く反映しています。
また、どの階層にいても人間の本質は変わらず、自分の利益のために他人を犠牲にする姿も描かれます。それがこの作品の残酷さであり、リアルさでもあります。
主要キャラクターと象徴:ゴレン、ミハル、子ども、そしてナイフ
・ゴレン(主人公):理想主義的で本を持ち込む人物。彼は「理性」や「知識」の象徴として描かれています。
・トリマガシ:初期のルームメイト。彼は暴力と功利主義の象徴であり、「弱肉強食」を体現しています。
・ミハル:娘を探して穴の中をさまよう謎の女性。彼女は「母性」と「狂気」、そして「救済者」としての側面を併せ持ちます。
・子ども:映画の終盤で登場する少女。この子は「希望」や「次世代」の象徴であり、ラストで“伝言”として上へと送られる存在です。
・ナイフ:選べる持ち物の一つとして多くのキャラクターが選ぶこのアイテムは、「自己防衛」や「攻撃性」、そして「選択の結果」を象徴しています。
登場人物一人ひとりが、単なるキャラではなく、社会や人間性を象徴する存在として機能しているのが、本作の面白さの一つです。
ラストシーンと“伝言”の意味:希望か絶望か?
物語のクライマックスでは、ゴレンと仲間が下層へ食事を届けながら降下していきますが、最終的に到達するのは最下層にいた“子ども”です。彼女が「伝言」としてプラットフォームに乗せられ、上へと送り返される――。
このシーンの解釈はさまざまです。「子ども=純粋さ、未来への希望」と見る向きもあれば、「彼女すら犠牲になるのでは」という厳しい見方もあります。結末を観客の解釈に委ねるスタイルが、本作の考察の余地を大きく広げています。
続編を含むシリーズ展開と、本作が問いかけ続けるもの
2023年には続編『プラットフォーム2』も登場し、さらに階層や社会の構造についての考察が進んでいます。続編では、より高度なメッセージ性と、構造の複雑さが加わり、「誰が権力を持つべきか」「伝言は届いたのか」といった問いが再び浮かび上がります。
本シリーズが一貫して問いかけているのは、「人間とは、そして社会とは何か?」という根本的な問題です。私たちは分かち合えるのか、それとも奪い合うしかないのか――。
Key Takeaway(まとめ)
『プラットフォーム』は、縦型の監獄という極限状況を通じて、現代社会の構造と人間の本質を鋭く問いかける哲学的な作品です。
単なるサバイバル映画に留まらず、社会風刺、宗教的象徴、倫理的ジレンマが詰まったこの作品は、見るたびに新しい発見があります。映画を観た方も、これから観る方も、本記事を通して改めてその深さに気づいていただければ幸いです。