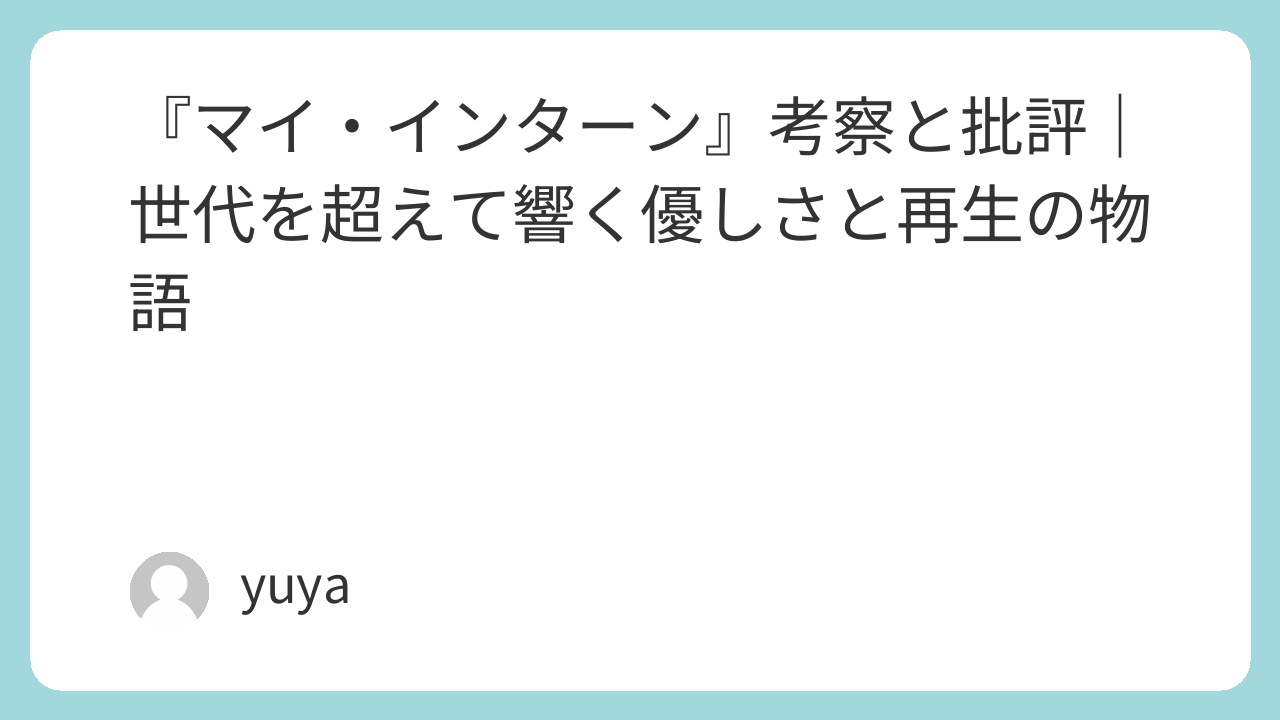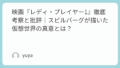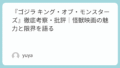近年、職場やキャリア、ライフスタイルをめぐる価値観の変化が急速に進む中で、『マイ・インターン(The Intern)』は、そんな現代的テーマをユーモラスかつ温かく描いた作品として多くの支持を集めました。ロバート・デ・ニーロ演じる“シニア・インターン”のベンと、アン・ハサウェイ演じる若き女性CEOジュールズの関係を軸に、年齢・性別・キャリアの壁を乗り越える人間ドラマが展開されます。
この記事では、『マイ・インターン』をただの“癒し映画”として終わらせず、その背後にある構造やテーマに深く切り込んだ考察・批評を試みます。
年齢の壁を越える──ベンと若手社員との関係性の深化
ベンは、かつて電話帳会社の副社長まで勤め上げ、70歳を越えた今、定年退職後の空虚さから「シニア・インターン」という制度に応募します。最初は「おじいちゃんが来た」と戸惑っていた若手社員たちも、彼の真摯な姿勢、穏やかさ、そして実務的なスキルに触れるうちに、徐々に敬意と信頼を寄せるようになります。
ここで描かれるのは、ただの“癒し”ではなく、価値観の再評価です。忙しなく働く若者たちが見失っていた“余裕”や“礼節”といったものを、ベンは静かに提示します。それが説教臭くならないのは、彼が「教える」のではなく、「寄り添う」姿勢を貫いているからでしょう。
「働く意味」と定年後の再出発:ベンのモチベーションを読む
この映画で非常にユニークなのは、「働く理由」が年齢によって異なることに着目している点です。ベンは生活のために働くわけでも、出世のためでもなく、人生に目的を持つために職場へ戻ります。
定年=終わりではなく、“次の始まり”と位置づけるこの描写は、日本社会のように定年退職後の生きがい喪失が社会問題化している国にとっても示唆的です。シニア世代が再び社会とかかわる姿勢は、職場に多様な価値をもたらす可能性があることを、本作はそっと教えてくれます。
ジュールズという存在:CEO/母/女性としての葛藤
ジュールズは若くしてファッション通販サイトのCEOとして成功を収めながら、家庭との両立や夫婦関係に悩む現代女性の象徴です。彼女の抱えるジレンマは、「仕事か家庭か」といった古い問いを超えて、「両方を選んでもなお生じる葛藤」に焦点を当てています。
社会的には成功しているが、パートナーとの関係がすれ違っていく様子は、多くの働く女性が共感できるリアルな側面を持ちます。また、ベンとの交流を通じて、彼女が少しずつ心を開き、感情を言語化できるようになる過程もまた、興味深い心理描写です。
信頼と距離感:コミュニケーション描写のリアリズム
本作では、ベンとジュールズの関係が「恋愛」に発展しないことも重要なポイントです。年齢差を“壁”として扱うのではなく、経験の違いを“架け橋”にして、互いの考えや感情に触れていく様子は、現代における理想的な信頼関係のモデルともいえるでしょう。
職場における“距離のとり方”を学ぶうえで、本作のコミュニケーション描写は非常に参考になります。特に、ベンが無理に馴染もうとせず、しかし真摯に相手を観察し、必要なタイミングでそっと手を差し伸べる姿勢は、年齢・立場を問わず見習うべき姿です。
評価と限界:この作品が抱えるテーマの深さ・浅さを問う視点
一方で、『マイ・インターン』に対する批判的な声も無視できません。たとえば、「すべてがうまくいきすぎていてリアリティがない」「社会的課題を描くには表層的すぎる」といった意見も一定数存在します。
確かに、夫婦関係の修復や職場の人間関係など、あまりにも“うまく収まりすぎる”展開には、ご都合主義的な印象を受ける面もあります。しかしそれでも、この作品が多くの視聴者に「癒し」や「励まし」を与える力を持っているのは、ポジティブであることが“逃避”ではなく“希望”として描かれているからではないでしょうか。
総括:『マイ・インターン』が現代に投げかける問い
『マイ・インターン』は、世代・性別・価値観の違いが交錯する現代において、互いを理解しようとする姿勢こそが何よりも大切だと語りかけてきます。決して大きなドラマが起こるわけではありませんが、日常の中にある違和感や孤独をすくい取り、丁寧に描くことで、多くの人の共感を呼ぶ作品となっています。
ビジネスや人生に迷う人、キャリアと家庭の間で悩む人にとって、本作は一つのヒントを与えてくれる、静かで力強いメッセージ映画といえるでしょう。