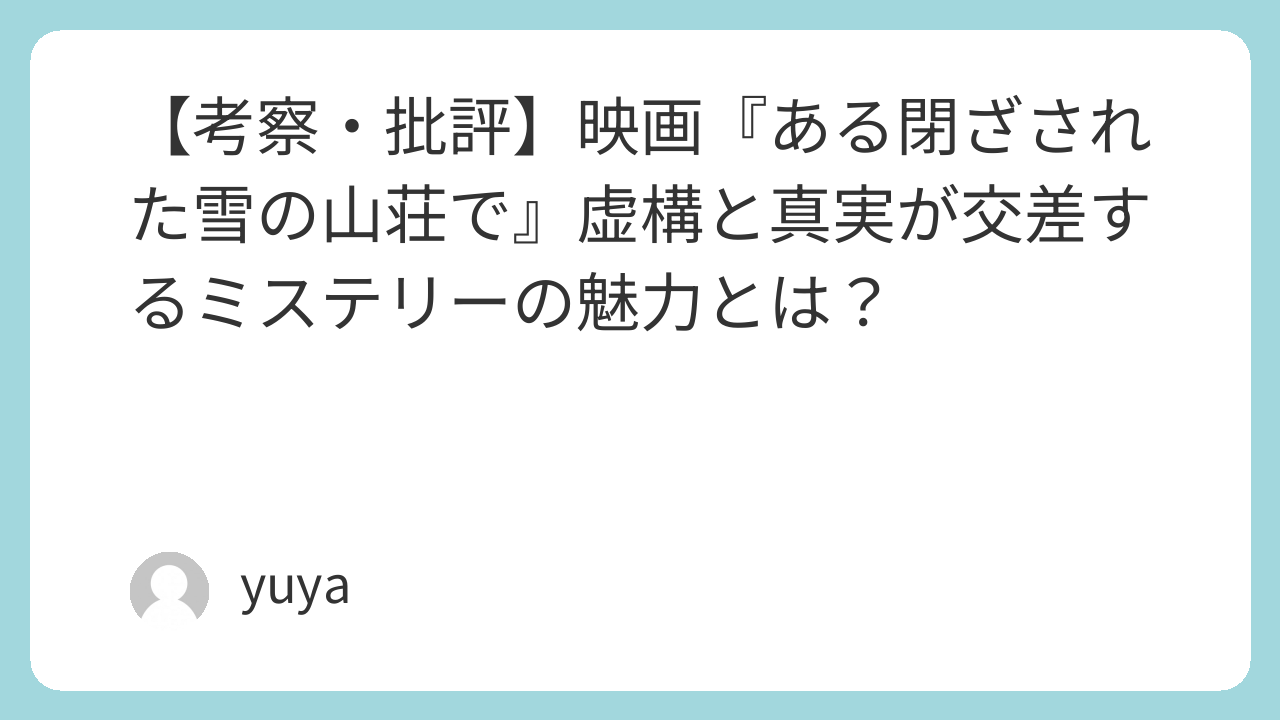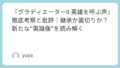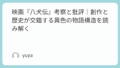2024年公開の映画『ある閉ざされた雪の山荘で』は、東野圭吾原作の同名小説を基にした密室サスペンスです。演劇オーディションのために集められた7人の俳優たちが、雪に閉ざされた山荘で奇妙な「芝居」を演じながら、やがて一人また一人と姿を消していく…という物語。
本作は「役者が役を演じる俳優たち」という設定と、「舞台なのか現実なのか分からない」入れ子構造が観客に強烈な知的挑戦を突きつけてきます。本記事では、映画の構造・演出・批評的観点から掘り下げ、本作の本質に迫ります。
物語の三重構造:真実・演技・虚構の境界を読み解く
『ある閉ざされた雪の山荘で』は、物語の中に「演技」「虚構」「現実」が幾層にも折り重なる構造を持っています。
- 第一層は「登場人物が体験している事件」。
- 第二層は「登場人物たちが“芝居”として演じているフィクション」。
- 第三層は「観客が観ている映画そのもの」。
つまり観客は、登場人物たちが事件を体験しているのか、それとも“演じている”のか、あるいは“観客を騙すための演出”なのか、常に揺さぶられることになります。
特に終盤、現実と思われた場面が「演出」だったと明かされるくだりでは、観る者の認識が根底から覆され、ミステリでありながらメタ的な映画体験に引き込まれる構造です。
密室/雪の山荘という舞台装置の意味と限界
「外界と断絶された雪山の山荘」という設定は、密室サスペンスの古典的手法です。しかし本作では、あえてその“使い古された装置”を再利用しながら、次のような機能を果たしています:
- 登場人物たちが“劇中劇”から逃れられない閉鎖性
- 通信手段・脱出手段がないことで生じる緊張感
- 雪に包まれた静寂と美しさが、事件の不穏さを際立たせる
一方で、この設定は一部の観客から「現代設定にしてはやや強引」「ご都合主義では?」という批判も受けています。山荘という舞台の閉鎖性は、現実味よりも“演劇的虚構”を強調するための装置とも解釈できるでしょう。
“俳優が役者を演じる”――キャラクターの演技性と本心
本作の最大の魅力は、「俳優が俳優を演じる」という自己言及的なキャラクター構造です。
- 登場人物たちは、“劇中”で自分自身を偽り、他人になりきろうとする
- それにより、誰が本音で語っているのか分からなくなる
- 誰もが“俳優”であるがゆえに、「演技」をやめる瞬間が存在しない
特に主演の重岡大毅をはじめとしたキャストの演技が巧妙で、「このセリフはキャラの本音なのか、芝居なのか?」と観客を迷わせます。
この“演技性の多重性”は、事件解決のトリックにも関わるため、観る者に常に緊張を強います。ミステリと同時に、「人間の本心とは何か?」という心理劇の要素も色濃く含まれているのです。
映画版改変と原作とのズレ:何が追加・省かれたか
原作ファンにとって気になるのが、映画版での改変です。いくつかの点で原作と映画は大きく異なります。
- 映画は現代のSNS文化やスマートフォンなどを登場させ、舞台をアップデート
- 原作では文字中心で描かれた“演技の違和感”を、映画では表情や演出で表現
- 映画独自の伏線や“カメラの視点”が真相に大きく関わる構成へと変更
一部の登場人物の役割や背景も変更されており、結末の「どんでん返し」の演出にも違いがあります。ただし、この変更が“賛否”のポイントにもなっており、「映像化として成功」と評価する声もあれば、「原作のほうが筋が通っていた」という声も見られます。
賛否両論と批評視点:本作の魅力・弱点を冷静に見る
『ある閉ざされた雪の山荘で』は、非常に挑戦的な映画であり、観客によって評価が大きく分かれています。
魅力と強み:
- 入れ子構造による知的スリル
- 俳優たちの高水準な演技と演出の妙
- 虚構/現実の境界を問い直す構成
弱点と課題:
- 説明不足な部分が多く、“置いてけぼり感”を抱く観客も
- ミステリとしてのカタルシスが薄いとの指摘
- 一部キャラクターの動機や行動が曖昧
批評的に見ると、本作は「物語体験の枠組みそのものを揺るがす」ポストモダン的な試みともいえます。純粋な推理小説の映画化を期待した観客にはやや難解かもしれませんが、構造派映画やメタフィクションが好きな層には深く刺さる作品でしょう。
総括:本作が問いかける「真実とは何か」
『ある閉ざされた雪の山荘で』は、単なる“誰が犯人か”という枠に収まらない、複雑で多層的な映画です。本作の真のテーマは、「演技と現実の境界線」「観客が“信じたもの”は果たして真実なのか」という問いかけにあります。
一見ミステリでありながら、人間の本質に迫る心理劇・メタ劇でもある本作。何を信じ、何を疑うか――あなた自身の感性が試される映画です。