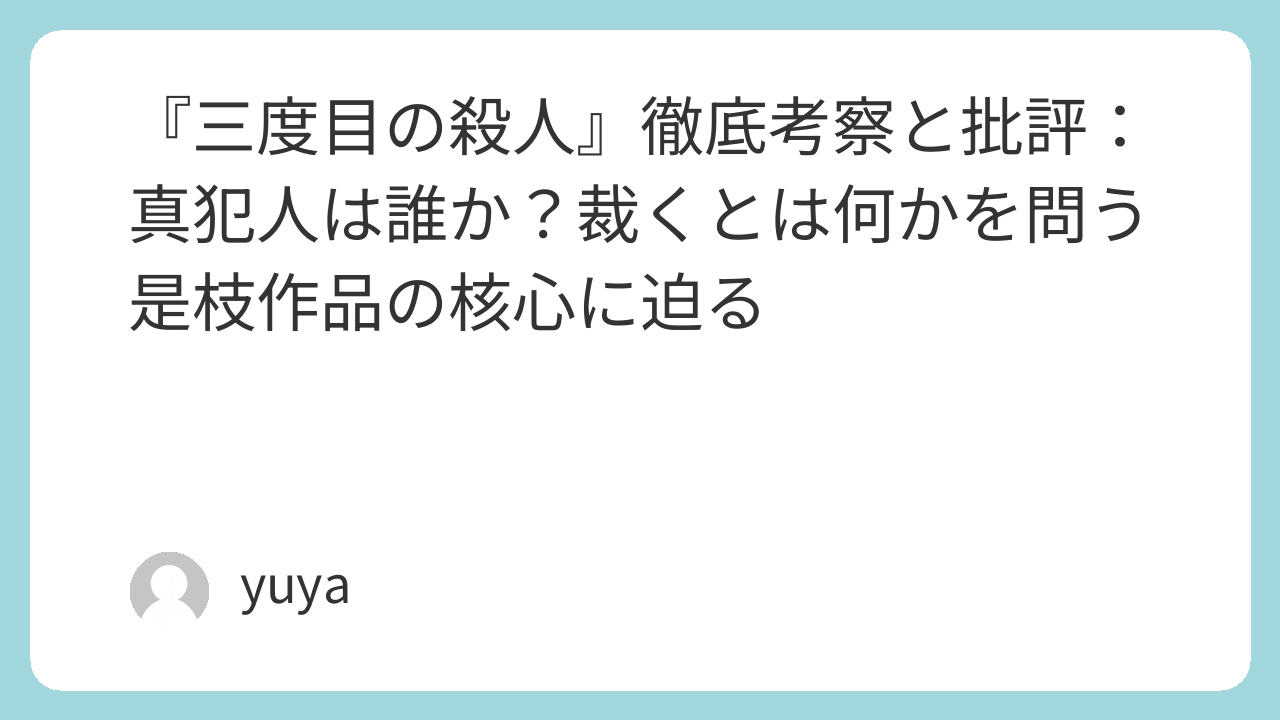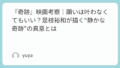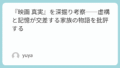是枝裕和監督が手がけた法廷サスペンス映画『三度目の殺人』は、その重厚なテーマ性と繊細な演出によって、多くの観客に強い印象を残しました。本作は単なる殺人事件の解明にとどまらず、「人を裁くとはどういうことか」「真実とは何か」「正義はどこにあるのか」といった、現代社会が抱える根源的な問いを私たちに突きつけます。この記事では、『三度目の殺人』について、物語構造から登場人物の心情、隠されたメッセージ、そして賛否両論あるラストに至るまで、深く考察・批評していきます。
本作のあらすじと構造:三度目の「殺人」とは何か
映画は、すでに一度殺人を犯し服役した男・三隅が再び殺人を犯したとされる事件から始まります。彼は殺害をあっさり自供しますが、供述は次第に食い違い、嘘か真か判別がつかなくなっていきます。弁護士・重盛は事件の真相を追ううちに、彼自身の倫理観や価値観までもが揺さぶられていきます。
タイトルの「三度目の殺人」は、物理的な三度目の犯行を意味するだけでなく、法廷や社会制度によって「もう一度人が殺される」こと、あるいは人間の尊厳が殺される過程を象徴しているとも解釈できます。このように、物語構造そのものが「真実とは何か」を巡る問いになっているのです。
真犯人論争と供述変遷:観客を惑わせる意図
三隅は物語の中で供述を何度も変えます。当初は殺意を持って犯行に及んだと語りますが、その後、被害者の妻に依頼されたとも、自分は罪をかぶっただけとも言い出します。これにより、観客は「誰が本当の犯人なのか」という疑問を常に抱き続けることになります。
しかし本作の本質は、真犯人を暴くミステリーではありません。供述の変遷を通じて浮かび上がるのは、人間が語る「物語の脆さ」です。人は自己を正当化するため、あるいは他者の思惑に応えるために、真実を捻じ曲げて語ることがあります。三隅の変化する言葉は、そのまま「人間の嘘」と「信じたいものしか信じられない世界」の象徴ともいえるのです。
伏線・隠喩・モチーフの読み解き:器・十字架・雪など
本作には多くの象徴的なモチーフが散りばめられています。たとえば「器」。三隅が弁護士に語る「自分は空っぽの器で、人の思いを映すだけ」という言葉は、彼自身の人物像、そして社会が個人に何を求めるかという構造を示唆します。
また、「十字架の影」がガラス越しに重盛の顔に映る場面は、「彼もまた裁かれる存在」であることを暗示しています。さらに、雪のケーキや白い景色は「罪の清算」や「無垢さの再生」を象徴しており、それが三隅の最終的な動機や行動ともリンクしていきます。
こうした視覚的・言語的な暗喩が、観客の無意識に訴えかけることで、物語に多層的な奥行きを持たせています。
裁く者 vs 裁かれる者:正義・裁判・共感の視点
『三度目の殺人』では、裁判という制度の中に潜む「非人間性」にも焦点が当てられています。重盛は当初、被告の人間性に関心を持たず、ただ無罪を勝ち取るための「駒」として三隅と接します。しかし、事件を追ううちに彼は揺らぎ、ついには「人を裁くことの意味」に直面するのです。
被告・弁護士・裁判官という役割を超えて、登場人物は皆、どこかで「裁く者」と「裁かれる者」の立場を行き来します。これは、私たち観客自身にも問いを投げかけてきます。「自分だったらこの人をどう裁くか?」「そもそも裁くことができるのか?」
是枝監督が描くのは、冷静な法制度の中に流れる「情」の側面であり、法と人間の間にある深い断絶と接点を炙り出しているのです。
評価と批判:モヤモヤの是非/視点の受容性
本作は結末に明確な解答を与えません。そのため、「すっきりしない」「結局、何が言いたいのかわからない」という批判も少なくありません。一方で、このモヤモヤこそが作品の本質であると高く評価する声も多くあります。
特に、2回目、3回目の鑑賞で印象が変わるというレビューが目立ちます。細部に仕込まれた演出、台詞の含意、登場人物の目線やしぐさに注意を向けることで、まったく違う物語が見えてくる──それがこの映画の最大の魅力です。
受け手の成熟度や経験によって感じ方が変わる「余白のある作品」として、『三度目の殺人』は観る者自身を試すような、静かな衝撃を持っています。
まとめ:真実を裁くことの不可能性と、観客への問いかけ
『三度目の殺人』は、「真実とは何か」「正義とは誰が決めるのか」といった、重くも普遍的なテーマを、静かで緻密な演出で描き出した異色の法廷映画です。派手な展開や明快な結末を求める観客には物足りなさを感じさせるかもしれませんが、だからこそ、深く考える余地を与えてくれます。
重盛や三隅だけでなく、私たち自身が「真実と向き合う責任」を持っていることを、映画は静かに訴えているのかもしれません。