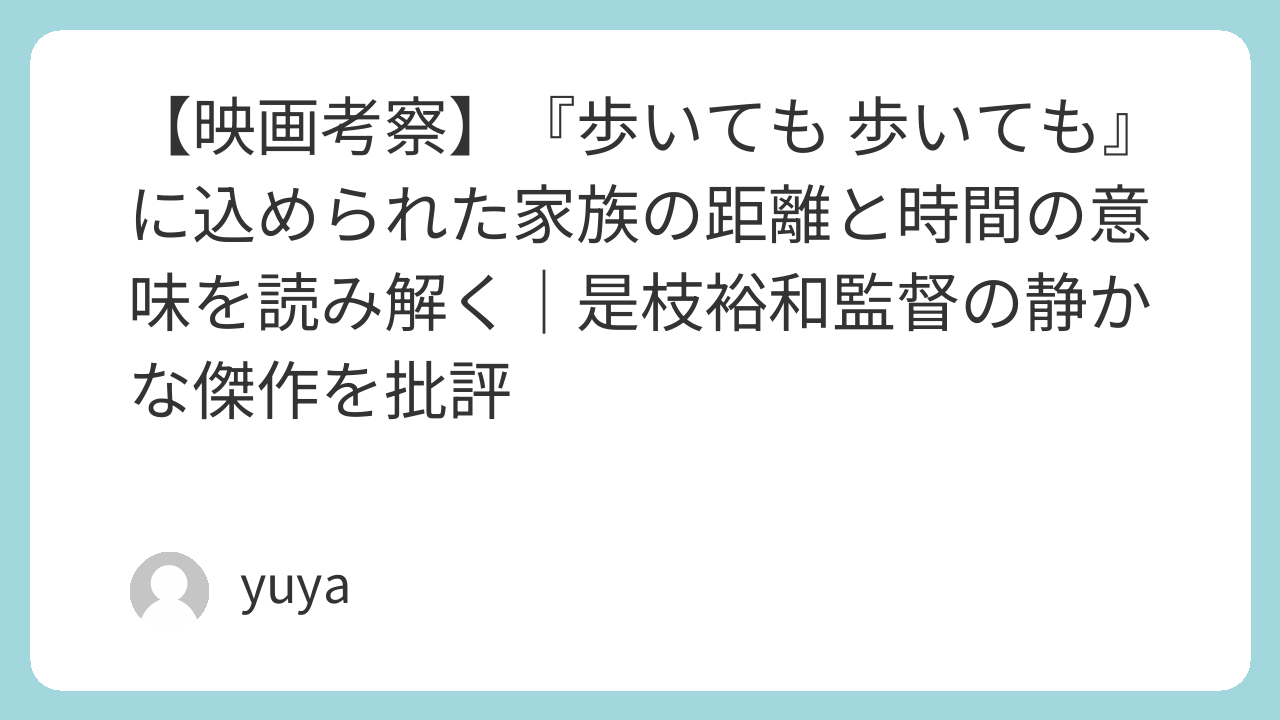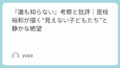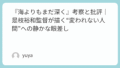是枝裕和監督による2008年の映画『歩いても 歩いても』は、一見すると何気ない家族の一日を描いた作品ですが、その中に刻まれた感情の揺らぎ、過去と現在の交差、そして人と人との微妙な距離感は、観る者の心を深く揺さぶります。本記事では、この作品に込められた意味やメッセージを丁寧に読み解いていきます。
物語概要と登場人物
『歩いても 歩いても』の物語は、ある夏の日、横山家に次男・良多一家が帰省するところから始まります。横山家では、15年前に亡くなった長男・順一の命日を毎年家族で偲ぶのが恒例となっています。
- 父・恭平(元開業医)は頑固で保守的な性格。次男に対しては冷たく当たりがち。
- 母・とし子は明るく世話好きで、家族をつなぎとめようとする存在。
- 次男・良多は絵画修復の仕事に就くが定職には就いておらず、母子家庭の妻・由佳里と再婚。
- 息子・あつしは、良多と由佳里の再婚により新しい家族として受け入れられている少年。
このように、表面上は静かな日常を描いているものの、その裏には過去の喪失、家族間の葛藤、言葉にできない感情が流れています。
家族の距離感と共有の歴史:ズレの構図
この映画の中で最も印象的なのは、家族であるはずの人々がどこか他人のように見える「距離感」です。
- 父と次男の間には「順一ではない」という失望感が拭えず、会話の端々に棘がある。
- 母とし子は明るく振る舞いながらも、実は家族の誰にも心の奥底を開いていない。
- 良多は親に褒められた記憶もなく、自分の人生選択にどこか後ろめたさを感じている。
- 息子のあつしに対しても「義理の孫」として線を引くような描写があり、血縁の重さと壁が感じられる。
このズレは決して劇的な対立として描かれるのではなく、むしろ台所での会話や、夕食後の沈黙、何気ない視線の交差といった日常の中で静かに表現されています。
それぞれの葛藤:死・比較・親子・継承
『歩いても 歩いても』には、それぞれの登場人物が抱える内面的な葛藤が繊細に描かれています。
- 父・恭平は「長男が継ぐはずだった医者」という夢が潰えたことで、次男への期待も失い、頑なな態度を取ります。
- 母・とし子は、順一の死をきっかけに「家族の形」が崩れたことを認識しつつ、何とか繋ぎ止めようとしています。
- 良多は、兄と常に比較されてきた人生の中で「自分には何も残されていない」と感じている。
- そして再婚相手の由佳里も、義両親との関係の築き方に戸惑いながらも、家族としての一歩を踏み出そうとします。
このように、映画は“誰かが悪い”という構図を作らず、誰もが何かを失い、何かを諦め、何かを引きずっている様を描き出します。
タイトル「歩いても歩いても」の意味と時間観
本作のタイトル「歩いても 歩いても」には、人生における“間に合わなさ”や“埋まらない溝”が象徴されています。
- 良多が何度帰省しても、父の評価は変わらず、親子の距離も縮まらない。
- 時間がいくら経っても、順一の死の痛みも、親の期待も、記憶も、薄れはしない。
- 「歩く」という行為は前に進むことを意味する一方で、前に進んでいるようで、同じ場所をぐるぐる回っているような感覚も与える。
まるで人の人生そのものが「歩いても歩いても」届かない何かを追い続けるものなのだ、と問いかけているようです。
演出・映像・是枝監督の手法・評価と批判
是枝裕和監督は、この作品でも彼特有のリアリズム演出を用いています。
- 台詞はあくまで自然体。あえて説明的なセリフは使わず、「空白」や「沈黙」が多くを語ります。
- 映像は淡く柔らかい光に包まれており、ノスタルジックで懐かしい家庭の雰囲気を醸し出す。
- 食事のシーンや虫の音、蝉の声といった音の演出が、時間の流れや季節感を強く印象付けています。
批評的な視点からは、「過剰なリアリズムゆえに物語が動かない」「ドラマ性に欠ける」との指摘もありますが、それもまた“日常”を描くという本作の方向性に基づく必然であると言えるでしょう。
おわりに
『歩いても 歩いても』は、劇的な出来事のない一日を描くことで、人間関係の本質や、家族というものの複雑さ、そして人生の切なさを浮き彫りにする名作です。観終わったあと、きっと誰もが「自分の家族」を思い浮かべ、どこか胸が詰まるような余韻を抱えることでしょう。