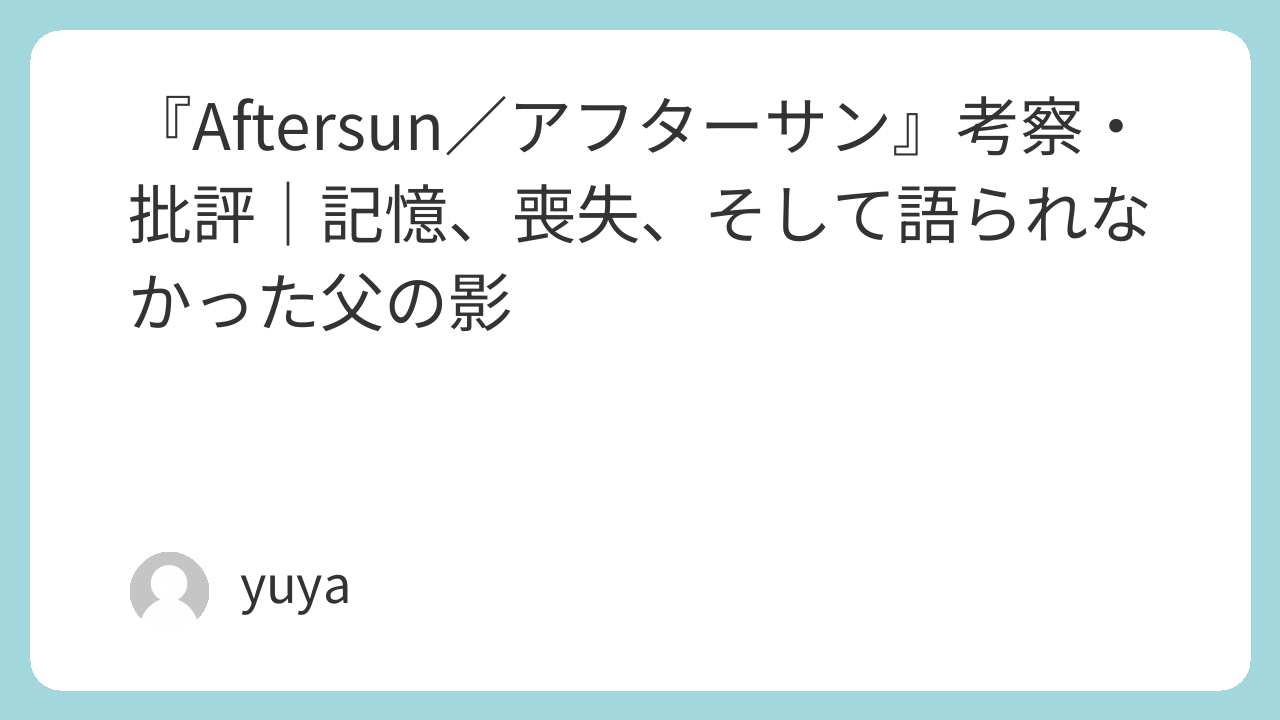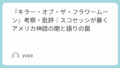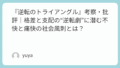『Aftersun/アフターサン』(2022)は、スコットランド出身のシャーロット・ウェルズ監督が手掛けた長編デビュー作でありながら、極めて繊細かつ詩的な映像体験を提供する傑作として高く評価されています。一見すると父娘の穏やかなバカンスの記録ですが、その奥には記憶の歪み、抑圧された感情、語られぬ苦悩が静かに潜んでいます。
本記事では、「映画 aftersun アフターサン 考察 批評」というテーマで、以下の5つの観点から作品を深掘りします。物語の仕掛け、キャラクターの造形、映像と音響の手法、そして死と記憶の詩学まで、読後には本作の見え方が変わるかもしれません。
物語と記憶の間を揺らぐ構造:Aftersunの語り口を紐解く
『Aftersun』は、主人公ソフィの回想を通じて語られる物語です。しかし、その「回想」はあくまで主観的な記憶であり、事実ではないかもしれないという含みを常に残しています。断片的な映像や、8ミリカメラの映像、夢のようなクラブのシーンなどが挿入されることで、観客は「これは本当に起きたことなのか?」という疑念を抱く構造になっています。
この記憶の不確かさは、ソフィ自身が成長した後に父を回想する中で、自ら再構成した「物語」でもあることを示唆しています。つまりこの映画は、単なるバカンスの記録ではなく、「喪失と再構築の物語」なのです。
父・カラムという人物像:苦悩、抑圧、そして影の存在
父・カラム(ポール・メスカル)は、優しく、娘想いの父親として描かれています。しかしその笑顔の裏には、深い孤独と抑圧された感情が隠れています。作中では、カラムが鬱病に苦しんでいる描写がいくつも見られます。例として、誕生日を祝われた直後にホテルのベッドで泣くシーン、静かに海に沈んでいくシーン、そして自らの腕を骨折させようとするような不穏な行動などです。
カラムは、ソフィの前では「明るい父親」を演じていますが、その仮面は少しずつひび割れ、観客には彼の苦悩が透けて見えるようになっています。この抑圧された人物像は、ソフィにとっての父の理解を複雑化させ、映画全体に深い哀しみを漂わせます。
クィア・リーディングと隠された性/アイデンティティの読み解き
本作には明示的な「性的指向」に関する描写はありませんが、一部の観客・批評家の間では、カラムに対してクィア・リーディング(LGBT的視点)を適用する考察が見られます。例えば、カラムが女性との関係に消極的であること、彼の振る舞いや表情に「何かを隠している」ニュアンスがあることがその根拠です。
このような読みは、「ソフィに本当の自分を見せられなかった父」という悲劇性をさらに強調します。作品における沈黙や曖昧な表現の中に、語られなかったアイデンティティの断片が潜んでいるのかもしれません。
映像表現と音響の詩性:記憶を映す装置としての映画
『Aftersun』における映像と音響は、単なる演出を超えて「記憶の具現化」として機能しています。特に印象的なのは、ホームビデオのような8ミリ映像、反復的に登場するクラブのシーン、そしてノスタルジックな色調です。これらの視覚要素は、ソフィが父との時間を記憶し、反芻している感覚を観客にもたらします。
また、音楽の選曲も極めて重要です。Queenの「Under Pressure」、Blurの「Tender」、R.E.M.の「Losing My Religion」などの90年代楽曲は、感情と記憶をつなぐ媒体として強く機能し、ソフィの内面を音で語る役割を果たしています。
“死の匂い”と終末感:昏い予感が作品に与える余韻
映画は直接的にカラムの「死」を描いてはいません。しかし、多くの観客が彼の自殺を暗示として読み取ります。その要因は、全体を覆う沈黙、疲弊、そして未来を語らない彼の言動にあります。終盤でソフィがカラムに手を振り、彼が扉の向こうへ消えるシーンは「永遠の別れ」を暗示しているかのように描かれています。
この「死の匂い」は、ソフィにとっての喪失体験であり、今なお癒えぬ傷でもあります。『Aftersun』というタイトルの持つ「陽のあとの影」という語感にも、喪失と残像の意味が込められているように感じられます。
Key Takeaway
『Aftersun/アフターサン』は、表層的には父娘のひと夏の思い出を描いた映画に見えますが、その奥には深い悲しみと記憶、語られなかった思いが幾層にも重なっています。曖昧さと余白の多い構成が、観客一人ひとりに異なる解釈と感情を呼び起こす、極めてパーソナルな映画体験を提供します。特に「親という存在の不可解さ」や「子供時代の記憶の再解釈」というテーマに響く人にとっては、心に長く残る作品となるでしょう。