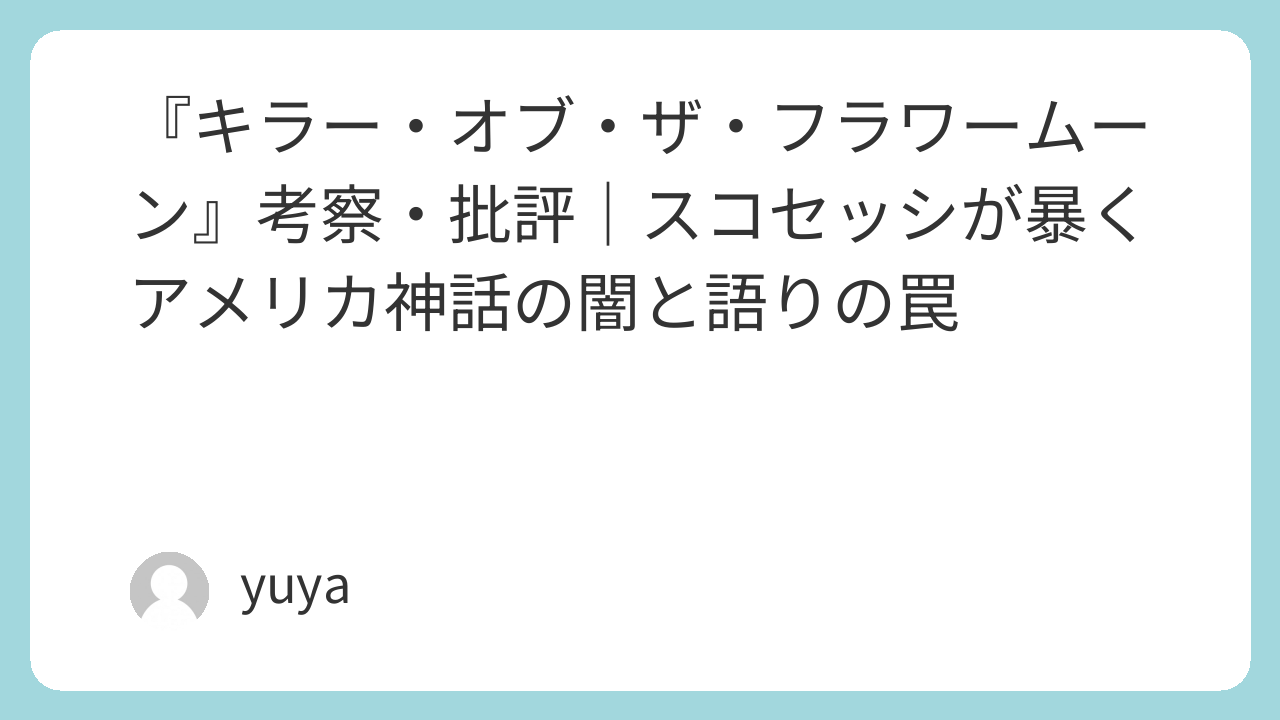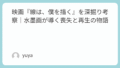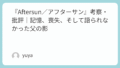マーティン・スコセッシ監督が手がけた2023年の大作映画『キラー・オブ・ザ・フラワームーン』は、単なる犯罪ドラマではありません。1920年代、オクラホマ州で実際に起きたオーセージ族連続殺人事件という史実を元に、アメリカという国家の構造的暴力と人間の業を描いた本作は、スコセッシ作品の集大成とも評されています。
本記事では、この映画の核心に迫るべく、歴史的背景から語りの構造、キャラクター分析、映像表現、さらには批判的観点まで、多角的に考察・批評していきます。
作品概要と題材の背景:史実と映画の狭間
『キラー・オブ・ザ・フラワームーン』の原作は、ジャーナリスト、デヴィッド・グランによるノンフィクション作品。舞台は石油で富を得たオーセージ族の地。彼らが次々と不可解な死を遂げ、最終的にFBI(当時はBOI)の介入を受けるという、20世紀初頭のアメリカで実際に起きた事件を描いています。
- 石油によって巨万の富を得たネイティブ・アメリカンが、白人たちの策略によって命を狙われていく過程は、アメリカ史における搾取と差別の縮図。
- スコセッシはこの史実を、単なる被害者と加害者の物語としてではなく、愛や裏切り、無知と加担といった複雑な人間ドラマとして再構築。
- 映画は「アメリカン・ドリーム」の裏側を暴き出す“反神話”として機能している。
物語構造と語りの視点:誰が語るか、何を語るか
映画の語り口は緻密かつ大胆です。当初はFBIの捜査官からの視点が軸になると見せかけて、観客を“当事者たちの内部”へと引き込んでいきます。
- 主人公のアーネスト(レオナルド・ディカプリオ)の視点から描かれることで、観客は加害の内側に立たされる構造。
- 被害者であるモリー(リリー・グラッドストーン)視点が意図的に省略されており、物語の語りが「白人男性中心」であることを逆説的に浮き彫りに。
- 最終的にスコセッシ自身が登場し、ラジオドラマ風の演出で物語を締めることで、「語られる歴史」の形式と限界を示唆。
このようなメタ的語りは、映画の持つ歴史再現性と同時に、観客自身の立場を問う装置として機能しています。
キャラクター分析:アーネスト、モリー、ヘイルらの動機と葛藤
本作の中心には、アーネストとモリーの“愛”と“裏切り”があります。アーネストは加害者でありながら、妻モリーを愛しているという矛盾を抱えています。
- アーネストは、無知と従属により犯罪に手を染める「日常的な悪」を体現。
- モリーは、冷静さと内に秘めた怒りを持つ人物として描かれ、リリー・グラッドストーンの静かな演技が高く評価されている。
- ヘイル(ロバート・デ・ニーロ)は、善意を装った“構造的加害者”として描かれ、近代資本主義と植民地主義の化身のような存在。
キャラクターそれぞれの動機が単純な善悪に還元されないことで、本作は深みを増しています。
映像美・演出技法・音響演出:物語を支える映画言語
スコセッシは名匠ロドリゴ・プリエトを撮影監督に迎え、時代の空気感を圧倒的なリアリズムで再現しています。
- 空撮やロングショットで描かれるオクラホマの大地は、美しさと同時に暴力の沈殿を感じさせる。
- ろうそくの灯りを使った屋内シーンでは、人物の内面の葛藤を“陰影”として映し出す演出が光る。
- 音楽はロビー・ロバートソン(ザ・バンド)が担当。ネイティブ・アメリカンの伝統と現代的なロックが融合し、時代の裂け目を音で表現。
映像・音響ともに、物語のテーマをより深く体感させるための装置として非常に効果的に機能しています。
批判的視点と限界:白人中心性、人種表象、ジェンダー視点の視座
本作は高く評価される一方で、いくつかの批判的観点も存在します。
- 物語の視点が加害者であるアーネストに偏っており、被害者であるオーセージ族の主体性が弱くなっているとの指摘。
- モリーの視点がもっと描かれていれば、映画はよりバランスの取れたものになった可能性がある。
- スコセッシ自身もこの批判を意識しており、終盤の語りに「誰が物語を語るのか」という問いを仕掛けている。
これらの批判は、本作が扱うテーマの複雑さ、そして歴史の“語り方”そのものへの問題提起を示唆しています。
🔑 Key Takeaway
『キラー・オブ・ザ・フラワームーン』は、単なる歴史映画ではなく、アメリカという国の深層にある暴力、差別、裏切りを描いた“語りの映画”です。その語り口は意図的に不安定で、観客に問いを突きつけ続けます。批評的に見れば、作品自体が「誰が歴史を語るのか」という根源的な問題に挑戦しているとも言えるでしょう。