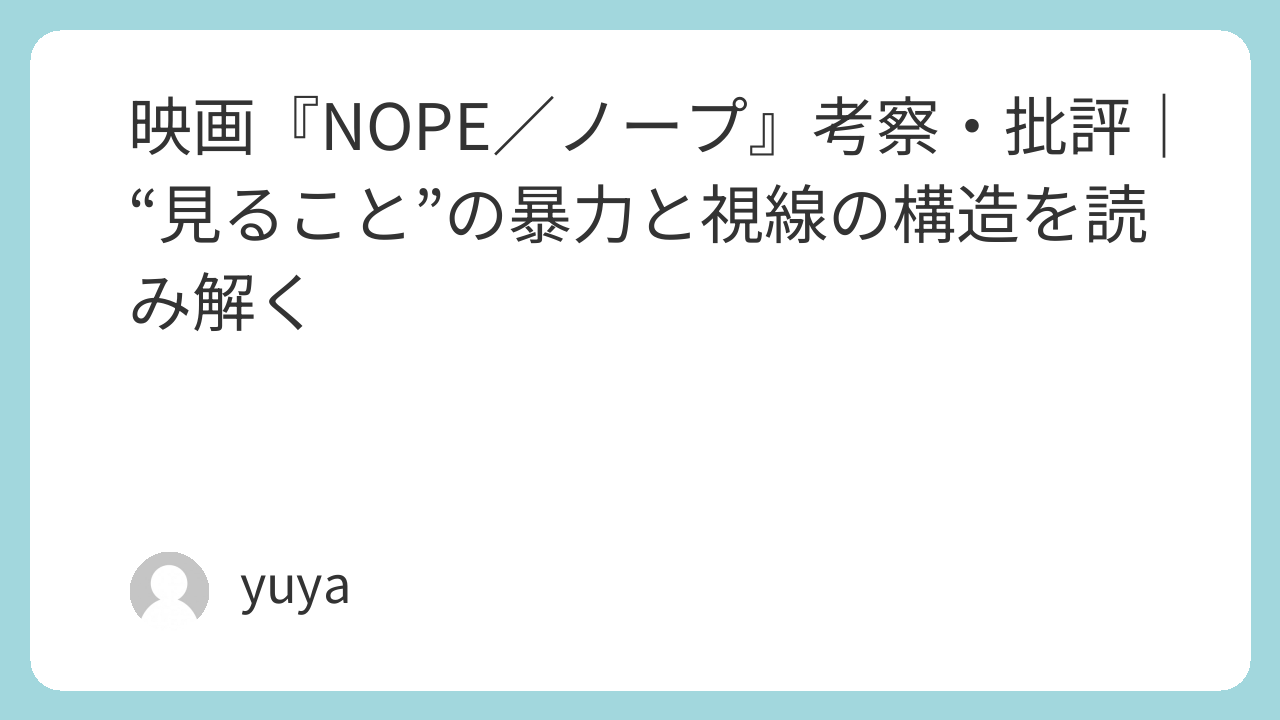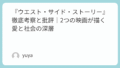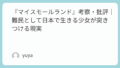ジョーダン・ピール監督による映画『NOPE/ノープ』(2022)は、単なるSFホラーやスリラーの枠に収まらない、非常に多層的なメッセージを内包した作品です。「見られること」「見ること」に対する執着、暴力、そしてそれを撮影し収益化するエンタメ産業への鋭い批評性——その一つひとつが、観客に問いを投げかけてきます。
この記事では、作品のメッセージや象徴性、映画的装置、批評的観点を深掘りしていきます。
『NOPE/ノープ』のあらすじと基本情報:鑑賞前の準備ガイド
『NOPE/ノープ』は、アメリカの広大な荒野を舞台に、謎の“何か”をめぐって繰り広げられるサスペンスです。
- 監督:ジョーダン・ピール(『ゲット・アウト』『アス』など)
- 公開年:2022年
- 主演:ダニエル・カルーヤ、キキ・パーマー、スティーヴン・ユァン
- ジャンル:SF/ホラー/ミステリー
物語は、馬のレンタル業を営む兄妹OJとエメラルドが、牧場の上空に現れるUFOの存在に気づき、それを“撮影”することで一攫千金を狙おうとする展開から始まります。しかし、物語が進むにつれて、その“何か”の本質と、それを「見ること」「見せること」が持つ暴力性が浮かび上がっていきます。
「見る/見られる」というメタファー — 支配・視線・権力の構造
本作の主題の一つは、「視線」の問題です。
- UFO(正式名:ジーン・ジャケット)は、“空飛ぶ円盤”ではなく、有機的な生物であり、「見られると襲う」存在。
- OJは、「見つめ返さない」ことで身を守る術を知る。この行為が“視線の拒否”であり、支配構造の否定を意味している。
- 見世物としての映像文化——カメラが“暴力の媒体”であるという皮肉。
- 「オプラ・ショット」(大金を稼げる決定的瞬間の撮影)を狙う行動自体が、スペクタクルへの欲望と倫理のなさを露呈する。
つまり『NOPE』は、「見ること/見せること」がもたらす暴力と、それを当然のように消費する観客(=私たち)への批評でもあるのです。
“ゴーディ事件”と動物表象の意味:暴力・抑圧・共感
劇中に挿入されるチンパンジーの“ゴーディ事件”は、本筋とは一見無関係のように見えますが、作品の根幹を支える象徴的エピソードです。
- ゴーディは撮影現場で突如暴走し、人間を襲う。
- 「動物=支配される存在」「人間=見る側」という構図の崩壊。
- ジュープ(演:スティーヴン・ユァン)は、事件を“感動的な思い出”に再構築し、過去のトラウマを“ショー化”してしまう。
これは、“見世物”として搾取された存在(動物、黒人、労働者など)が、いつか暴発するという予兆を描いています。ゴーディもUFOも、支配構造への無言の反撃と捉えることができます。
映画史・映像技術へのオマージュと批評性
『NOPE』には、映画の起源や映像装置への愛と同時に、その危うさへの批評が込められています。
- 冒頭で紹介される「動く馬」のフィルム=“映画の始まり”のメタファー。
- 馬の調教師という設定も、映画産業と“動物”の関係を想起させる。
- 古典的な映像技術(手回しカメラ)によるUFO撮影=「見る」装置への回帰。
- 映画とは、他者の苦しみを“見る”ことで成り立つものだという根本的問い。
本作は、ハリウッド的スペクタクルへの批判であると同時に、観客の欲望にも鋭く切り込んでいます。見ることが暴力であるならば、映画とは何か——という逆説的なメッセージが内包されています。
批評・評価を読み解く:賛否と議論点まとめ
『NOPE』は、その難解さや象徴性ゆえに、評価が大きく分かれた作品でもあります。
肯定的評価:
- 「見ること」へのメタ批評が見事(批評家・映画ファン層)
- 社会的メッセージとジャンル融合が秀逸
- ジョーダン・ピールの映像詩的センスが光る
否定的評価:
- 展開がわかりづらく、SFとしての爽快感に欠ける
- 象徴やメッセージが多すぎて整理できない
- 中盤の“ゴーディ事件”が本筋と離れている印象
多層的なメッセージを持つ作品であるがゆえに、観る人の知識や価値観によって受け取り方が大きく異なります。その“ズレ”こそが、この作品の面白さとも言えるでしょう。
【Key Takeaway】
『NOPE/ノープ』は、表層的にはUFOを巡るサスペンスでありながら、その奥には「視線」「搾取」「スペクタクル」「映画産業批判」といった深遠なテーマが幾重にも込められています。“見られる”ことの暴力性、そしてそれを消費する私たちの倫理——ジョーダン・ピールはそれらを問い続けることで、「映画とは何か?」という根本的な命題に挑戦しているのです。