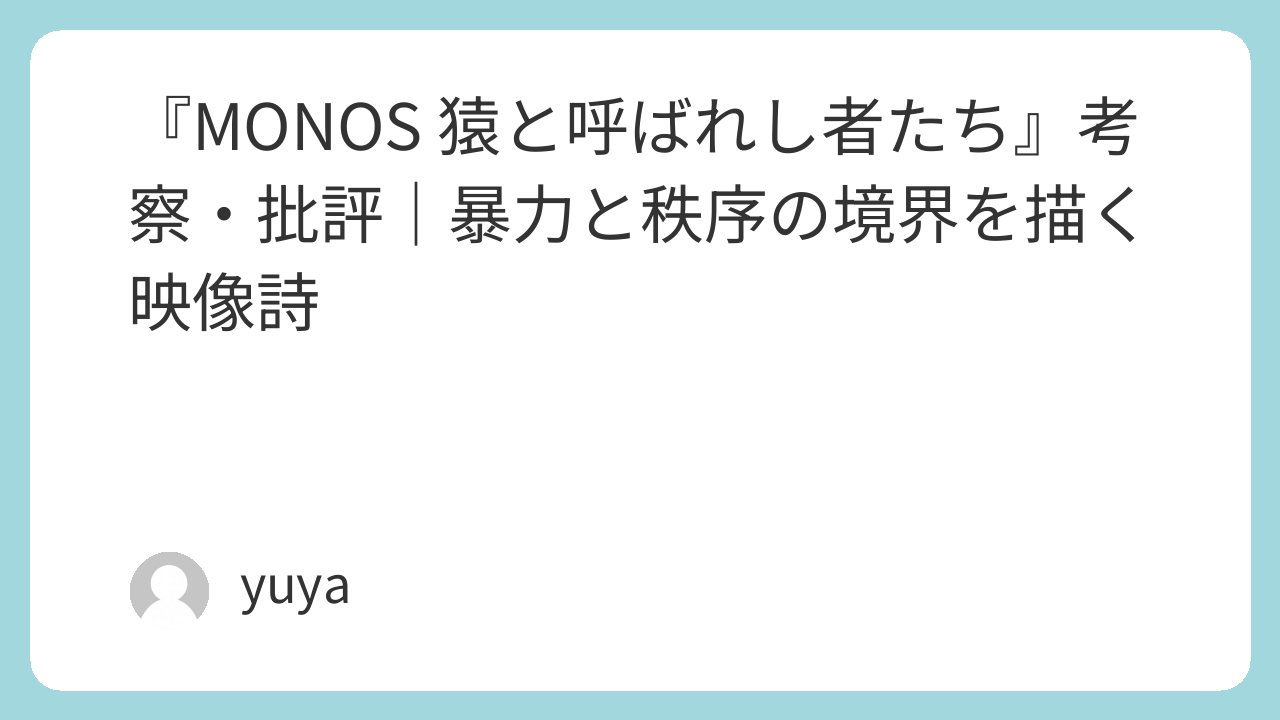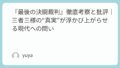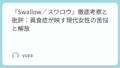南米の高原とジャングルを舞台に描かれる、少年兵たちの閉ざされた世界。 映画『MONOS 猿と呼ばれし者たち』(2019)は、アレハンドロ・ランデス監督による衝撃的な作品です。本作はジャンル映画の枠を超え、寓話的な世界観と詩的な映像美で世界中の映画祭を席巻しました。
本記事では、物語の構造・演出・主題を深く掘り下げていきます。
あらすじと設定:モノスという寓話世界の構築
物語は、名もなき高原地帯に集められた8人の少年少女兵士たちが「組織」の命令を受けて行動するというシンプルな構造を持ちます。彼らはコードネームで呼び合い、社会的アイデンティティを剥奪された存在です。
彼らの任務は、アメリカ人女性人質の監視と牛の管理。しかし日々の訓練と衝動的な行動、突発的な事故によって共同体の秩序が崩れ始めます。
この「どこでもなく、どこにでもある」空間設定は、コロンビアの実在する紛争と地続きでありながら、具体的な国家や政治背景をあえて排除することで、寓話的な普遍性を持たせています。つまり、これはあらゆる戦争・暴力の縮図として描かれているのです。
映像美・音響・演出の力:圧倒的な映画体験としての魅力
『MONOS』を語る上で欠かせないのが、映像と音響の圧倒的な力です。撮影監督ヤスペル・ウルバインのカメラは、自然光を活かしながら高原とジャングルの過酷な風景を詩的に捉え、観客に視覚的な没入体験を与えます。
一方、音楽はミカ・レヴィ(『アンダー・ザ・スキン』などで知られる)が担当し、ノイズや拍動のようなリズムが緊張感を高めます。これらの要素は物語の説明不足を補完するだけでなく、「感じさせる映画」としての側面を強調しています。
監督の演出も非常に抑制的で、台詞よりも表情・動作・沈黙が多くを語ります。視覚と聴覚を通じて観客に深層心理を訴えかける手法は、まさに映像詩と呼ぶにふさわしいものです。
暴力・秩序・アニミズム:人間性と野生性の境界線
作品全体に通底するテーマのひとつが「暴力の無垢性」です。少年兵たちは命令を忠実に守る軍人であると同時に、子供らしい無邪気さと残虐さを併せ持っています。この二面性は、暴力を「教育されるもの」として描く社会批評でもあります。
また、自然との関係も注目すべきです。高原やジャングルという大自然の中で、人間社会の秩序は簡単に崩れ去ります。人間の行動が自然に翻弄されるさまは、アニミズム的な視点すら感じさせます。
つまり、『MONOS』は人間と動物、理性と本能の境界線を曖昧にすることで、文明と野生の対比を浮き彫りにしているのです。
主体と他者、関係性の崩壊:家族/社会のモチーフ分析
この作品は、家族や社会といった「関係性」の崩壊も描いています。登場人物たちは擬似家族的な集団に属していますが、それはあくまで命令系統に基づくもので、真の信頼や愛情は希薄です。
人質として捕らえられたサラ・ワトソン博士との関係もまた、主体と他者の曖昧な境界を示しています。彼女は最初こそ「捕虜」として扱われますが、やがて精神的にも肉体的にも彼らの世界に取り込まれていきます。
このように、『MONOS』では「誰が誰を支配しているのか」「誰が人間らしさを保っているのか」という問いが、絶えず入れ替わる構造になっており、観客の倫理観を揺さぶります。
限界と欠落:脚本・物語構造への批評的視点
一方で、本作には賛否の分かれる点も存在します。物語の説明が極めて少ないことにより、観客の解釈に大きく委ねられる構成は、映像体験としては成功しているものの、物語性を重視する観客には不親切と映ることもあるでしょう。
また、個々のキャラクターの内面描写が断片的であるため、感情移入しづらいという指摘もあります。しかし、それこそが監督の意図であり、「一人ひとりが“記号”として機能している」という視点に立てば、それは物語の欠陥ではなく、批評性の高さと言えるかもしれません。
Key Takeaway
『MONOS 猿と呼ばれし者たち』は、映像・音響・演出によって観客の五感に訴える、比類なき映画体験を提供する作品です。暴力と秩序、文明と野生、主体と他者の曖昧な境界を浮き彫りにしながら、現代社会の歪みや人間性の深層を寓話的に描いています。
その抽象性ゆえに賛否が分かれるものの、観る者に問いを投げかけ、思考を促す点で、非常に価値のある一本と言えるでしょう。