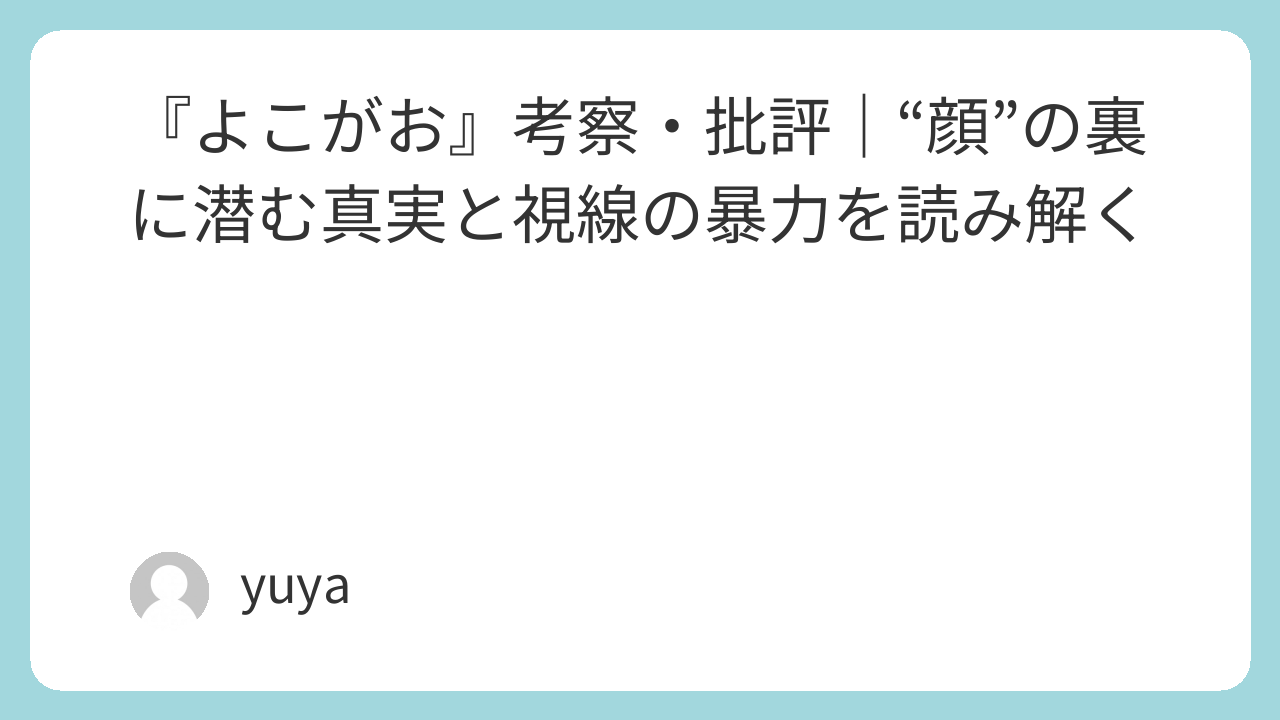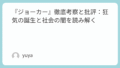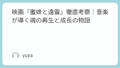深田晃司監督による2019年公開の映画『よこがお』は、「顔」や「視線」、そして「加害と被害」という現代社会が抱えるテーマに鋭く切り込んだ一作です。ある事件をきっかけに“善良な市民”から転落していく一人の女性を通じて、観る者に「正義とは何か」「本当の顔とは何か」を問いかけてきます。
この記事では、物語の構造や人物描写、映像表現、道徳的ジレンマ、ラストの意味など、さまざまな角度から本作を読み解きます。
あらすじと初見の印象:物語の構造とテーマの提示
物語は訪問看護師の市子(筒井真理子)が、ある事件をきっかけに人生を狂わされる様子を描いています。彼女は、家族のように接していた少女・基子との関係がきっかけで、ある犯罪事件に巻き込まれ、「誘拐犯」として社会から糾弾されます。
初見では、非常にシンプルな「転落劇」に見えるかもしれません。しかし、物語は時間軸を巧みに行き来し、「市子視点」→「洋子という別人としての彼女」として描かれることで、観客自身の視点も試されていきます。
この構造により、「我々が誰かを一面だけで判断していないか」という問いが浮かび上がるのです。
登場人物の“表と裏”:市子・基子・洋子の内面と関係性
市子は「善人」として描かれていたにもかかわらず、物語の中盤からは「加害者」としての姿が強調されます。一方で、少女・基子の証言や態度も、観客に一種の違和感を与える存在として描かれており、「被害者らしさ」に疑問を投げかけます。
また、「洋子」という別人になりすます市子の姿は、彼女が“過去の自分”を否定しながらも、それを乗り越えられない内面の葛藤を象徴しています。
ここに、表情の変化、口数の少なさ、視線の動きなど、役者たちの繊細な演技がリアリティを与え、人物の「よこがお(横顔)」、すなわち“他者から見た印象”と“本人の内面”のギャップが明確になります。
映像・音響・色彩の表現:監督が仕掛ける暗示と象徴
『よこがお』では、映像と音響が非常に重要な役割を担っています。例えば、極端に少ない音楽、長回しのカット、そして陰影の強い画面構成が、市子の孤独や社会との断絶を強調します。
色彩についても、前半は自然光が印象的な「暖色系」のトーンで始まるのに対し、事件後の市子は「寒色系」の冷たい色調で撮られており、彼女の心の変化を視覚的に訴えています。
特に、タイトルにもなっている“横顔”のショットは、人物の真正面や後ろ姿よりも感情の読みにくさ、つまり「他者からは見えない内面」を象徴しています。
加害者/被害者の境界:正義・復讐・責任の揺らぎ
この映画が最も観客に突きつける問いは、「加害者とは誰なのか?」ということです。市子が社会から糾弾される原因は、必ずしも彼女の明確な悪意によるものではなく、むしろ社会の“正義感”や“偏見”が暴走した結果とも言えます。
また、後半で彼女が取る行動は「復讐」とも取れますが、その動機には共感の余地もあるため、単なる報復ではない複雑さがあります。
このように、誰もが「加害者」にも「被害者」にもなりうる現代社会において、その境界がいかに曖昧で危ういものかを、本作は丹念に描いています。
ラストのラフな余韻:結末と観客の想像力に委ねられる部分
『よこがお』のラストは非常に静かで説明的な要素が少なく、「これから市子がどう生きるのか」を観客に委ねる形になっています。ある意味で“投げっぱなし”とも言えるこの結末こそが、作品のテーマを象徴しています。
社会や他者の視線から逃れられない現代において、自分の「顔=アイデンティティ」をどう守るか、あるいはどう壊されてしまうのか。それは、観る者自身の問題として跳ね返ってきます。
その余韻が、観た後も長く心に残るのです。
【総括】「よこがお」が問いかける、見ること・見られることの暴力性
『よこがお』は、非常に静かな演出とリアリスティックな演技によって、“視線”の持つ暴力性と、“顔”にまつわる同一性の問題をあぶり出す作品です。
我々が「他者をどう見ているか」、そして「自分が他者からどう見られているか」に無自覚である限り、この映画が示すような「境界の揺らぎ」に巻き込まれる危険性は誰にでもあるのです。