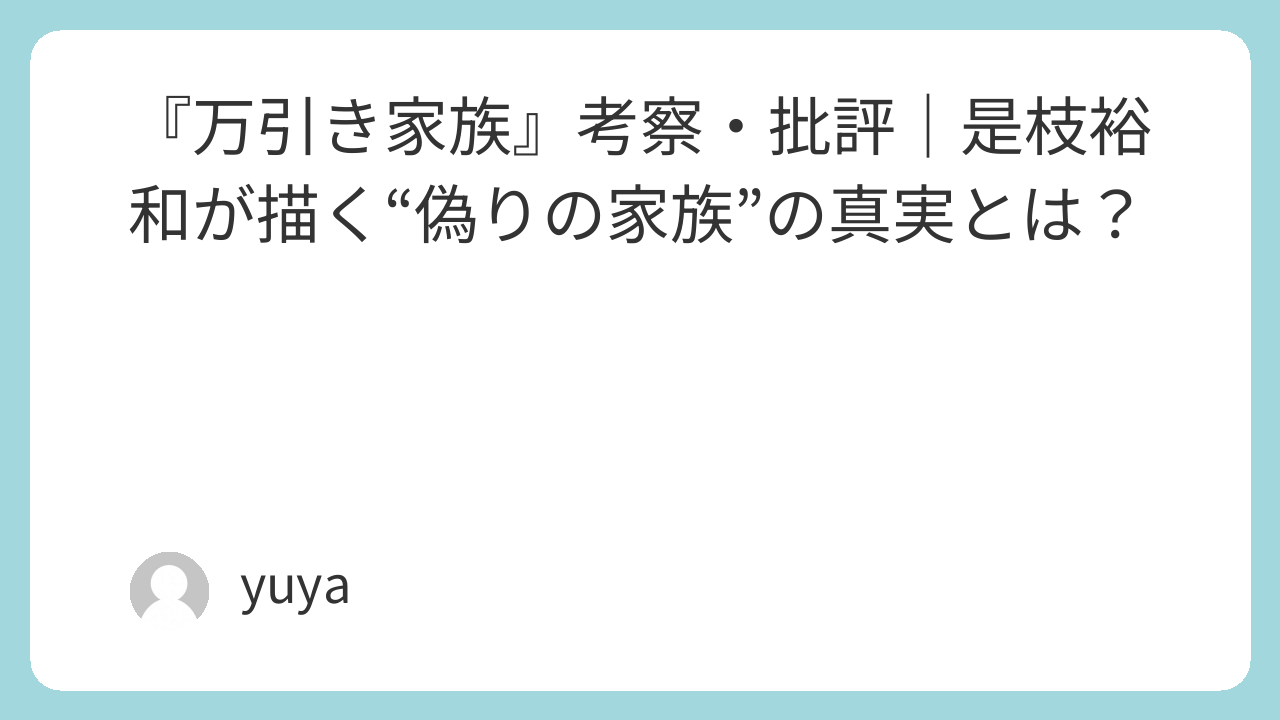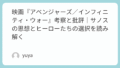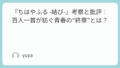2018年、是枝裕和監督による映画『万引き家族』は、カンヌ国際映画祭で最高賞であるパルム・ドールを受賞し、世界中で高い評価を受けました。その一方で、日本国内では「気持ちが悪い」「家族として共感できない」といった否定的な意見も見られ、賛否が分かれる作品でもありました。
本記事では、この作品が投げかける問いや登場人物の描写、社会的背景、演出技法、ラストシーンの意味に至るまで、深掘りしていきます。
登場人物分析:信代・治・初枝・亜紀・祥太──“家族”を構成するそれぞれの立場と苦悩
『万引き家族』の魅力の一つは、血縁ではなく選び取った「擬似家族」の中にある複雑な人間関係です。
- 信代(安藤サクラ):パートの仕事をこなしながら家庭を支える母的存在。感情表現に乏しいが、芯のある人物。
- 治(リリー・フランキー):父親としての責任感は薄いが、子どもたちとの距離は近い。無職で軽犯罪を繰り返す。
- 初枝(樹木希林):年金を頼りに生計を支えるが、家族にとっては経済的な基盤でもある。家族の中で唯一の年長者。
- 亜紀(松岡茉優):元風俗店勤務の若者。家族に居場所を感じながらも、外の世界に対する憧れと不安を抱える。
- 祥太(城桧吏):子どもながらに家庭の異常性に気づき、「家族」への疑念を深めていく存在。
この5人+ジュリ(りん)という構成は、それぞれが何かしらの“欠落”を抱えており、だからこそ互いに依存しあう関係性が生まれます。
映画的演出の巧みさ:伏線・象徴性・映像/音響で何を伝えているか
是枝監督の作品らしく、本作にも派手な演出はありません。しかし、細部に渡って演出意図が散りばめられています。
- 映像の静けさと距離感:カメラは登場人物に過度に近づかず、あくまで“観察者”としての視点を保ちます。これが逆にリアルさを醸し出している。
- 音の使い方:BGMをほとんど使わず、生活音や自然音だけで構成される場面が多い。これによりリアリズムが際立ちます。
- 伏線の回収:例えば、祥太が万引きを拒むようになる場面は、彼の内面の変化を象徴的に描いています。
- 窓や鏡の多用:隔たりや内面世界の象徴として機能しており、登場人物の孤独や矛盾が反映されます。
見落とされがちな演出にこそ、作品が伝えようとする本質が隠されています。
「家族とは何か」を問い直す──血縁ではない絆と社会規範の狭間で
本作の最大のテーマは「家族とは何か?」という問いです。法律や制度ではなく、感情や共生によって結ばれる関係性が、本当に「家族」と呼べるのかを問いかけています。
- 血縁がなくとも、人は家族になれるのか?
- 世間的に“犯罪者”であっても、子どもを愛する気持ちは本物だったのか?
- 社会が定めた「普通の家庭」像から外れた人々は、本当に“異常”なのか?
この問いは、現代社会における家族観の多様性や、「生きづらさ」とどう向き合うかにも通じます。
社会批評としての『万引き家族』:貧困・孤立・見過ごされる人々の声
『万引き家族』は、単なる家族ドラマではありません。現代日本が抱える社会問題への鋭い批評としても読めます。
- 貧困の連鎖:万引きを教える親と、それを学ぶ子ども。経済的選択肢のなさが倫理の崩壊を生む。
- 行政の無力さ:ジュリの家庭への介入の遅さや、家族の実態を見抜けない制度など、社会の機能不全が浮き彫りに。
- “見なかったことにする”社会:家族を装って生きる彼らの姿に、私たちの社会が持つ「無関心」が照らし返される。
この映画は、観客に社会の歪みを「見せる」のではなく「気づかせる」構造を持っています。
ラストの意味と観客の余韻──結末解釈とその曖昧さの意義
終盤、家族はバラバラになり、それぞれが現実に引き戻されます。このラストに対して、様々な解釈が存在します。
- 祥太が選んだ「本当の家族」:彼は敢えて戻らない道を選びました。それは「擬似家族」を超えて、自分の人生を歩む決断と取れます。
- 見上げる景色の先に何があるのか?:りん(ジュリ)が最後に見上げる視線には、彼女なりの「希望」や「問い」が感じられます。
- 観客に委ねられる結末:はっきりとした答えが示されないことが、本作の余韻と深みを生み出しています。
曖昧さこそが『万引き家族』の力。答えを与えないことで、観る者それぞれが自分自身の「家族」観と向き合わされるのです。
おわりに:答えは一つじゃない、それが『万引き家族』の強さ
『万引き家族』は、ただの感動作でもなければ、ただの問題提起でもありません。様々な視点を許容し、多くの余白を残したこの映画は、観る者に応じてまったく違う顔を見せてくれます。
血のつながり、経済、社会、倫理——そのすべてを通して「家族とは何か?」を問いかける、まさに現代の名作といえるでしょう。