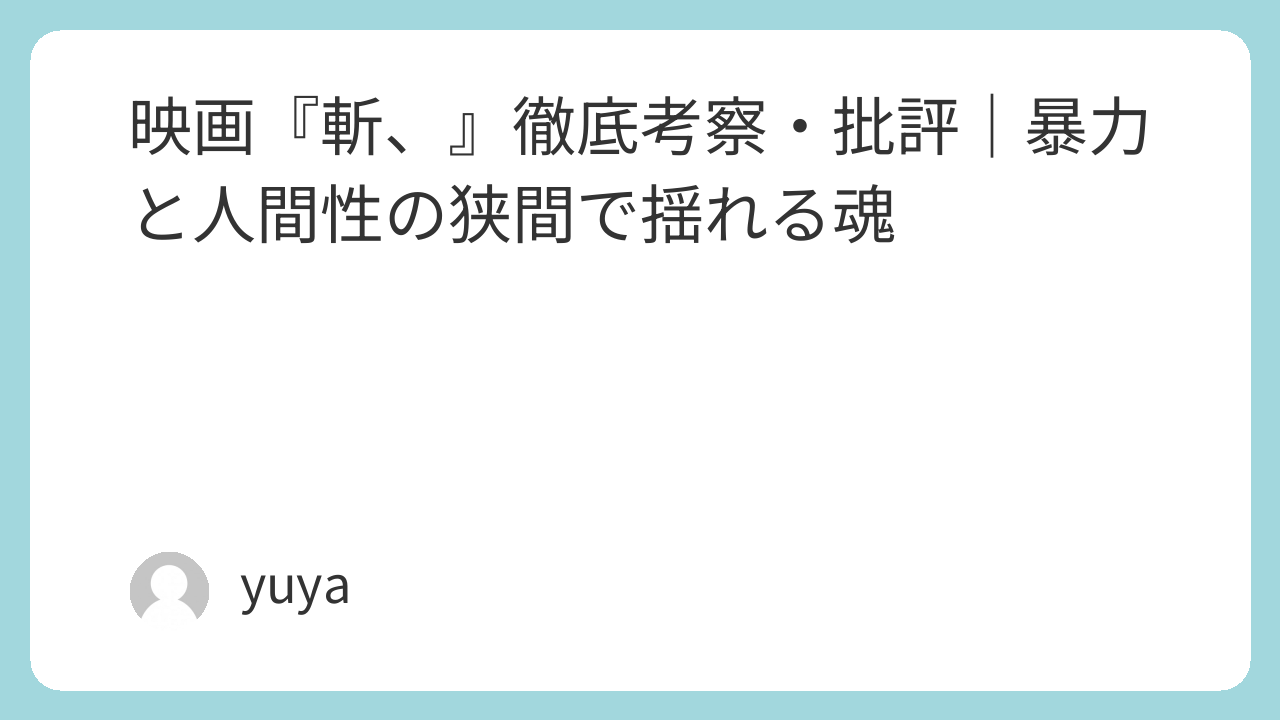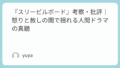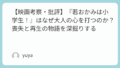2018年に公開された塚本晋也監督の映画『斬、』は、時代劇という枠組みに収まりながらも、その枠を大きく揺るがす異色の作品として多くの映画ファンに衝撃を与えました。人を「斬る」こと、暴力の本質、倫理と欲望、そして歴史の只中で生きる者の苦悩――本作が問いかけるテーマは決して過去のものではなく、現代を生きる私たちにも鋭く突き刺さります。
この記事では、この作品に込められた複雑な思想と演出意図を深掘りしていきます。
主人公の「斬る」という行為に潜む葛藤と暴力への誘惑
『斬、』の主人公・杢之進は元武士でありながら、一度も人を斬ったことがない男です。彼が抱えるのは、武士である自負と、人を斬ることへの恐怖と嫌悪。その葛藤が彼の行動と言動の端々に表れています。
彼の前に現れる市助や澤村らは、人を斬ることに対して異なる価値観を持っています。特に市助の存在は、暴力が日常に内在するという現実を象徴しています。暴力を忌避しつつ、どこかでその力に惹かれてしまう人間の矛盾が、杢之進の表情や行動から滲み出ています。
最終的に杢之進が「斬る」ことを選ぶ瞬間、それは自己保存か、復讐か、倫理の崩壊か。観る者に「人を殺すとは何か?」という根源的な問いを突きつけます。
定型を破る時代劇/侍像:『斬、』の形式と様式の再構築
一見すると『斬、』は時代劇の体裁をとっていますが、そこに描かれる「侍」はこれまでの時代劇に登場してきたヒーローではありません。むしろ、力なき存在としての武士像が前面に押し出されています。
例えば、決して美化されることのない戦闘。斬り合いはあくまでも痛みと死を伴う現実として描かれ、そこに様式美はありません。加えて、主人公の内面に徹底的に寄り添うカメラワークと編集は、観客に「この世界の中で生きる苦しさ」を体感させます。
従来の勧善懲悪や英雄譚から逸脱し、「人間の弱さ」そのものを描くという点において、『斬、』はまさに「反時代劇」と言えるでしょう。
光・闇・シルエット:映像美と演出の象徴性
塚本監督の持ち味ともいえる緻密な映像設計は、『斬、』においても存分に発揮されています。特に注目すべきは「光と闇」の使い方です。
夜の闇に浮かぶ灯り、焚火に照らされた顔、刀の反射光――これらは単なる視覚的効果を超え、登場人物たちの心理状態を象徴的に映し出しています。また、斬り合いの場面では、明確な輪郭を持たないシルエットが多用され、暴力が現実と幻想の狭間にあるような不安定さを醸し出します。
映像そのものが語るメッセージ性の高さは、本作を単なる時代劇以上の「映画作品」として際立たせる要素のひとつです。
キャラクターたちの倫理的境界線と「人間/怪物」の揺らぎ
登場人物たちはそれぞれ異なる立場と倫理観を持っており、その対比が物語をより重層的なものにしています。
澤村は一見、合理的な思想を持つ侍に見えますが、実は暴力への陶酔を隠し持っており、その冷静さは狂気の一歩手前とも言える危うさを孕んでいます。市助は庶民でありながら、最も本質的な暴力を体現しており、「武士だけが斬る」という特権的構造を否定する存在です。
杢之進は、その狭間で揺れ動く人間性の象徴です。人を斬ることで「怪物」になるのか、それとも「人間としての尊厳」を守るのか。その境界線が曖昧になっていく過程が、本作の最大のテーマのひとつです。
暴力、生、死:根源的テーマとしての意味と監督の視線
『斬、』は、単なる個人の物語ではなく、戦争という集団的暴力の予兆を描いた映画でもあります。幕末の動乱という歴史的背景は、現在の不安定な世界情勢と重ねて読むことができます。
塚本監督はインタビューで「暴力を描くことで、暴力を否定する」と語っており、その言葉通り、本作に登場する暴力は決して快楽的ではなく、むしろ不快で、痛みを伴うものです。
「生きるとは何か」「死とはどこからやってくるのか」「人間はなぜ人を斬るのか」。こうした根源的な問いが、全編を通じて私たちの心に投げかけられ続けます。
【まとめ】映画『斬、』は、観る者の倫理と感情を試す「現代の黙示録」
『斬、』は、単なる時代劇ではなく、暴力と倫理、生命と死を根底から問う作品です。塚本晋也監督の視線は鋭く、観る者の内面を抉り出すような力を持っています。
「人を斬るとはどういうことか?」という問いは、同時に「人間とは何か?」という問いでもあります。この映画は観る者に対して、簡単な答えを提示しません。しかし、だからこそ観る価値がある――『斬、』は、そんな映画なのです。