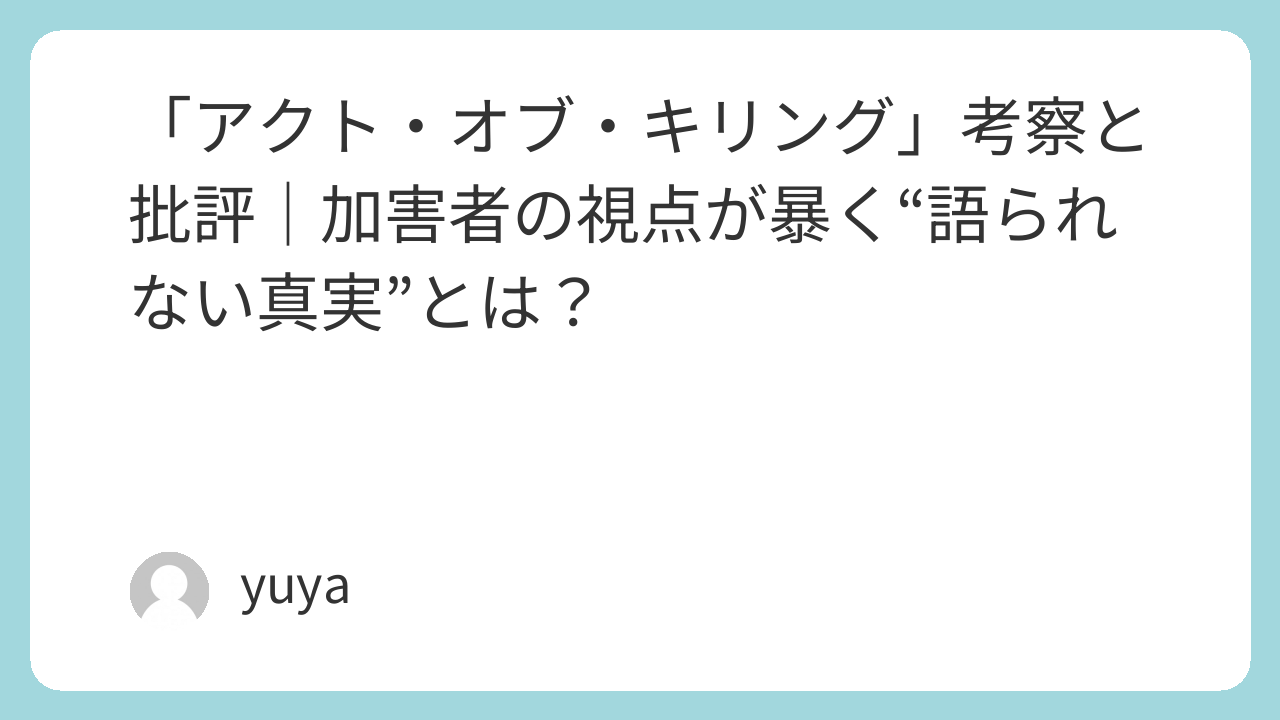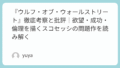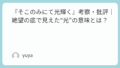ドキュメンタリー映画『アクト・オブ・キリング』(監督:ジョシュア・オッペンハイマー)は、1965年のインドネシアで起きた共産主義者大量虐殺事件を題材としながらも、従来の「加害=悪/被害=善」という二項対立を超えた異様なアプローチで世界中に衝撃を与えました。
この作品が特異なのは、被害者の証言を集めるのではなく、加害者本人たちに自らの行為を再現させるという手法をとった点にあります。果たして、それは倫理的に許されることなのか?あるいはそれこそが真実に迫る唯一の方法だったのか?
本記事では、この映画の持つ問題提起、構造、演出、そして観る者に与える心理的衝撃まで、5つの観点から深く考察・批評します。
加害者視点の再現手法:演じさせることの倫理と表現性
この映画最大の特徴は、「加害者が自分の過去の犯罪行為を自らの手で再現する」という異常な演出手法です。しかもそれが、ジャンル映画――ギャング映画やミュージカル――の形式を模倣する形で行われるという点で、観客は現実と虚構の奇妙なズレに困惑させられます。
演じている加害者たちは、自分たちの行為を誇らしげに語り、まるで英雄譚のように記録しようとします。しかし、次第にその演技の中に、不安や矛盾、葛藤が滲み出し、やがて主犯格アディ・コンダルは「嘔吐」という身体的反応を通じて自壊していきます。
これは、演じることを通してしか自己と向き合えなかった加害者の末路を示すと同時に、表現そのものの力と危うさを浮き彫りにしています。
歴史的背景とその現在性:1965年インドネシア虐殺の記憶と制度の残響
映画の背景にあるのは、1965年にインドネシアで発生した約100万人の共産主義者・その関係者の大量虐殺です。この大虐殺はインドネシア政府の黙認のもと行われ、現在に至るまで公式な断罪や謝罪が行われていません。
この「加害が正義として記録された歴史」は、加害者たちが現在でも「英雄」として扱われ、地元の有力者や警察・軍とつながりを持つという、異常な構造を生んでいます。
『アクト・オブ・キリング』はこの構造に真正面から切り込み、「歴史とは勝者の記録である」という認識を根本から覆す作品でもあります。
心理的インパクトと観客の感覚:ショック、葛藤、悪との対峙
この映画を観るという行為自体が観客に対して「ある種の加担」を突きつけます。加害者が笑いながら語る拷問や殺害の様子、淡々と繰り返される残虐行為の再現。それをカメラを通して“鑑賞”することに、観客は強烈な嫌悪感と罪悪感を抱かされます。
同時に、その「正気とは思えない現実」が、遠い世界の出来事ではなく、私たちが属する社会の構造的問題とも地続きであることに気づかされます。
倫理と感情、報道と娯楽、現実と虚構――その境界を揺さぶられる体験が、観客の中に「見ることの責任」を問いかけ続けるのです。
フィクションとドキュメンタリーの境界線:真実とは何かを問う演出
『アクト・オブ・キリング』は、典型的なドキュメンタリー手法――インタビュー、資料映像、ナレーション――を排し、代わりに「演出された現実」「演技する加害者」という二重の虚構によって真実に迫ろうとします。
この“虚構を通してしか語れない真実”という手法は、従来のジャーナリズムや記録映像の限界に挑戦しているとも言えます。
演出とは嘘をつくことではなく、「語られなかった真実を可視化する技法」であるという強烈なメッセージが、この映画には込められています。
被害者の声の不在と記録映画としての限界・可能性
この映画で唯一大きく欠けているのは、被害者の肉声です。被害者家族が一瞬だけ登場する場面もありますが、全体の物語は加害者たちの主観・語りに支配されています。
この「声の不在」は、構造的暴力がいかに被害者の言語を奪うかを示すものであると同時に、映画そのものが加害者の手記にすぎないのではないかという疑念も呼び起こします。
しかし、それでもなお本作が記録として重要なのは、「加害の記憶がどのように保存され、美化され、再演されるのか」を克明に記録した点にあります。そこから私たちは、「語られなかったもの」への想像力を働かせる責任を負わされるのです。
総括:加害の記憶と向き合うとはどういうことか
『アクト・オブ・キリング』は、単なる歴史ドキュメンタリーではありません。それは、歴史を語る手段そのもの、記録とは何か、演出とは何か、人間とは何かという根源的な問いを突きつけてくる作品です。
この映画を観ることで私たちは、自分がどれだけ「他者の痛み」に無関心でいられるのか、そして「語ること」がどれだけの暴力にもなり得るのかを知ることになります。