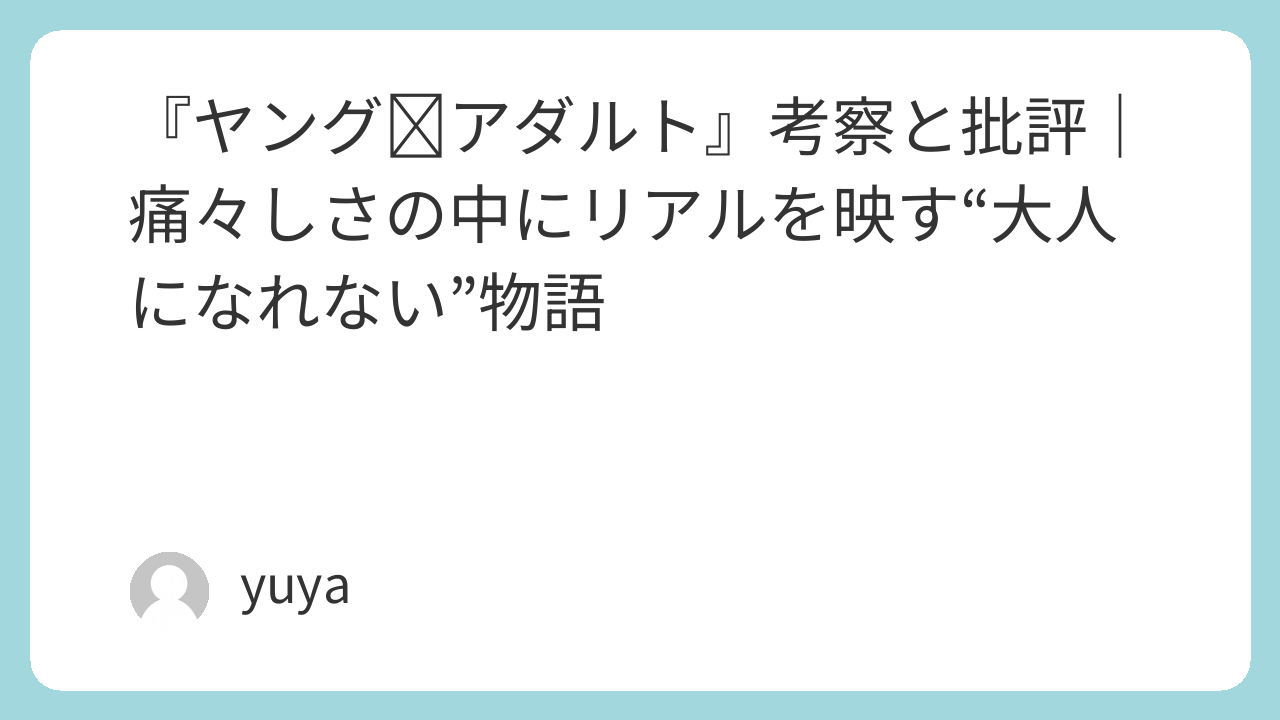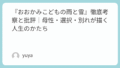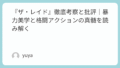映画『ヤング≒アダルト』(原題:Young Adult)は、2011年に公開されたアメリカ映画で、監督はジェイソン・ライトマン、脚本はディアブロ・コーディ。主演のシャーリーズ・セロンが演じるメイビス・ゲイリーは、“成功した都会の女性”という表の顔とは裏腹に、過去の栄光と幻想にしがみつく孤独な人物として描かれています。
本作は一見すると「帰郷して元恋人を取り戻そうとする女性」の物語ですが、その奥には「大人になりきれない人間の苦しみ」や「社会的成功と内面的未熟さの乖離」といった、現代人の心の深層が織り込まれています。本記事では、そんな『ヤング≒アダルト』を深掘りしながら、批評的視点と考察を交えて紹介します。
メイビスという主人公像:痛さと自尊心のあいだで揺れる女
メイビス・ゲイリーというキャラクターは、見る人にとって非常に“痛い”存在です。高校時代の栄光をいまだに引きずり、ゴーストライターとしての仕事にも身が入らず、酒とジャンクフードに頼る生活を送る彼女は、自信満々であるように振る舞う一方で、その裏には深い自己否定が潜んでいます。
彼女の行動の多くは、一見すると「自信家」で「傲慢」に見えますが、実際は「承認欲求のかたまり」であり、「過去の自分だけが唯一誇れる存在」であるがゆえに、そこから抜け出すことができないのです。これは、現代社会においてSNSなどで“過去の自分”を見せつけることに安堵を覚える多くの人に通じるものがあり、メイビスは決して他人事ではないのです。
青春の呪縛と故郷への回帰:過去に縛られる心理構造
本作の中核には、「青春時代」への執着があります。メイビスがわざわざ故郷ミネソタに戻るのは、かつての恋人バディと再会し、あわよくば“やり直せる”と信じているからです。この行為は現実的に見れば無謀ですが、心理的には極めて人間らしい衝動です。
彼女にとって青春時代は、すべてが輝いていた「唯一の成功体験」であり、それを手放すことは、自分の存在価値を否定することに等しいのです。これは、誰しもが経験する「過去の美化」と「現在への不満」の構造そのものであり、故郷に戻るという行為が象徴的にそれを表しています。
幻想と現実のギャップ:“最盛期”への執着とその破綻
映画は、メイビスの幻想が少しずつ崩壊していく過程を丁寧に描いています。バディには既に家庭があり、彼女の登場に戸惑いを隠せません。周囲の旧友たちも彼女の振る舞いに戸惑いながらも、どこか哀れみの眼差しを向けます。
このように、彼女が信じていた「自分はまだ特別な存在だ」という幻想は、現実の中では何の意味も持たないのです。そして、それを突きつける存在が、マットという障がいを持つ元同級生です。彼はメイビスの“痛さ”に気づきながらも、彼女を人間として受け止めようとします。
この現実との衝突が、彼女にとっての“目覚め”を促す一歩となるのですが、その道のりは決してドラマチックではなく、むしろ地味でほろ苦いものです。それがまた本作のリアリズムを際立たせています。
ユーモアと苦痛の共存:観客を引き込む“痛いけど見てしまう”魅力
本作の優れた点の一つに、「痛々しさ」をあえてユーモラスに描いている点があります。ディアブロ・コーディの脚本は、ブラックユーモアを交えながらも登場人物たちの心の闇に迫っていきます。
メイビスの言動はときに滑稽であり、観客は「そこまでするか?」と突っ込みたくなる瞬間も多々ありますが、同時に「分かる…」と感じさせる絶妙なバランスが取られています。だからこそ観客は彼女を“嫌いになりきれない”し、“目を背けられない”のです。
“大人になれない大人”としての自己評価と他者比較
メイビスの物語は、現代における「大人とは何か?」という問いにもつながります。年齢を重ね、表面的には成功しているように見える人間でも、内面は思春期の延長線上にいることは珍しくありません。
彼女は常に他者と自分を比較し、自分が「まだイケている」と思い込もうとします。しかしそれは、他人の幸せを否定することでしか自分を肯定できない不健全な精神構造を示しています。これは、比較と承認を軸に動く現代社会において、多くの人が抱える共通の問題とも言えるでしょう。
結論:痛々しいけれどリアルな人間ドラマ
『ヤング≒アダルト』は、決して「救いのある話」ではありません。メイビスは最終的に劇的に変わるわけではなく、ただ少し「気づき」を得るだけです。しかし、そのわずかな変化こそが本作のリアルであり、観る者にとっての余韻として残るのです。
🔑 Key Takeaway(要点)
『ヤング≒アダルト』は、「過去に縛られたまま生きる人間の痛々しさ」と「そこからほんの少し踏み出す瞬間の輝き」を描いた、極めてリアルな人間ドラマである。現代人の多くが抱える葛藤を象徴する主人公メイビスを通して、自分自身と向き合うきっかけを与えてくれる作品だ。