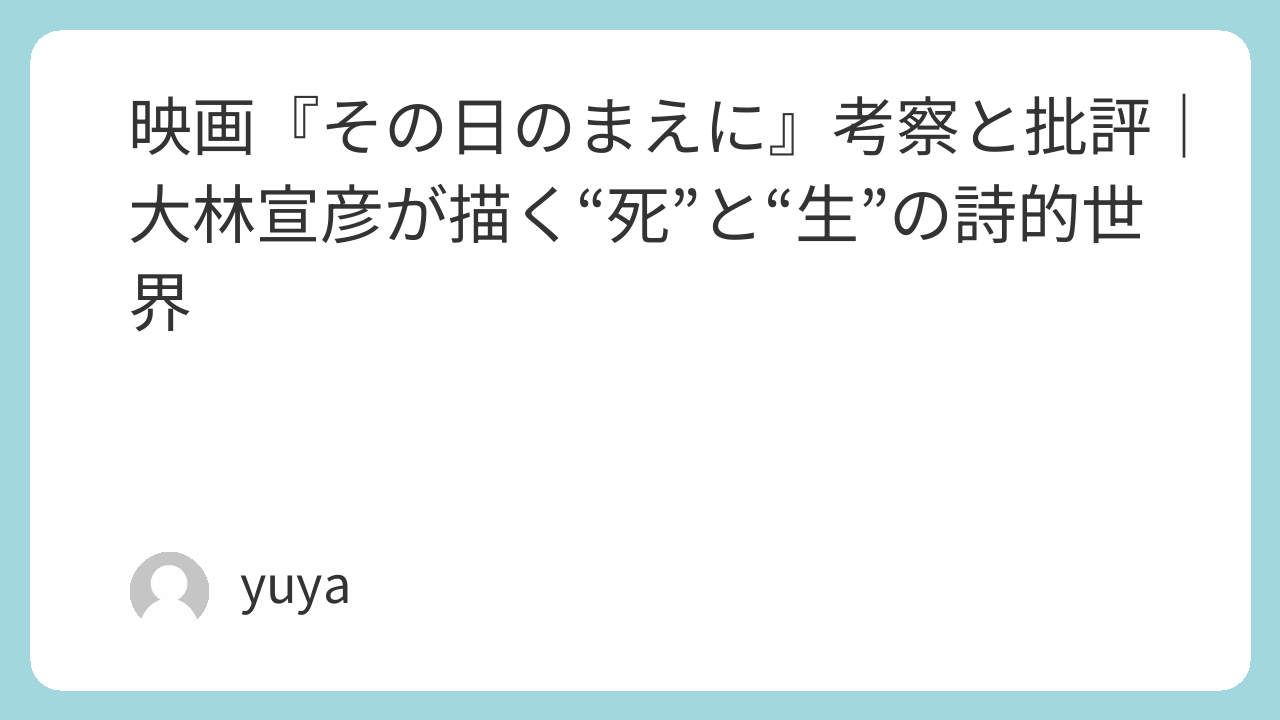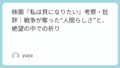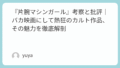大林宣彦監督による映画『その日のまえに』(2008年)は、「死」をテーマにしながらも、決して悲劇に留まらず、むしろ“生きること”の意味を静かに問いかける作品です。原作は重松清の連作短編集であり、映画ではその一部が再構成されています。
本記事では、映像演出、原作との違い、観客の評価、俳優の演技、そして識者の見解に至るまで、多角的に作品を掘り下げていきます。
大林宣彦監督らしさとは?映像美と詩的演出の特徴
大林宣彦監督の作品には、いわゆる「大林ワールド」と呼ばれる独自の映像スタイルが存在します。『その日のまえに』でもそれは健在で、たとえばカメラの視点がふわりと浮遊するような演出や、画面上の文字演出など、非現実的でありながらも詩的な要素がふんだんに盛り込まれています。
これにより、重いテーマである「死」や「別れ」も、どこか幻想的で、静かな美しさを伴って描かれます。大林監督は、死を“終わり”としてではなく、“通過点”として描こうとし、それが映画全体に穏やかなリズムと優しさを与えているのです。
原作とのギャップ:連作短編から映画への再構成
原作は重松清による連作短編集で、個々のエピソードが独立した短編小説として成立しています。しかし、映画版ではそれらが一つの長編ストーリーとして再構成され、主人公・とし子と夫・真の物語を主軸に据えながら、原作の他エピソードが挿話的に挿入されています。
この再構成は大胆な試みである一方で、原作ファンからは「唐突」「物語が薄まった」との声もあります。特にエピソードごとの余韻が映画ではやや希薄になり、原作にあった“静かな感動”が散漫になっているとの批判も見られます。
賛否両論に見る “大林ワールド耐性” と映像の好き嫌い
この作品に限らず、大林作品は「観る人を選ぶ」と言われます。『その日のまえに』もまた、特異な映像表現やナレーションの多用が「冗長」「わざとらしい」と感じる観客も一定数います。特に、映画的リアリズムを重視する層には、演出の“作為性”がノイズに感じられるかもしれません。
一方で、そうした表現がむしろ作品の魅力だという声も多く、「現実と非現実の境を曖昧にすることで、“死”という不可視のテーマに肉薄している」との評価もあります。要するに、大林監督の演出は“好みが分かれる”のです。
永作博美が体現する「生きる力」と「静かな覚悟」
主演の永作博美は、余命宣告を受けた主人公・とし子を演じ、死を恐れるのではなく、受け入れながら日常を丁寧に生きようとする姿を見事に表現しています。その演技には過剰な感情表現はなく、淡々とした言動の中に滲み出る強さと優しさが観る者の心を打ちます。
また、夫・真を演じた南原清隆との夫婦のやり取りには、時にユーモアさえ感じられ、生の最期を迎える準備というよりも、「最期まで生き抜く」という意志が込められています。永作の静かな存在感が、この映画の精神性を支えていることは間違いありません。
識者が語る大林作品の美学:一貫した世界観とアウトサイダー性
映画評論家の宇多丸氏をはじめ、識者たちはこの作品を「商業映画の枠を超えた、アウトサイダー的アート」と位置付けています。特に注目されるのは、大林監督がどの時代でも一貫して「死」や「記憶」「郷愁」といったテーマに挑み続けている点です。
その一貫性こそが、「大林宣彦」というブランドの強さであり、鑑賞者に「これは映画なのか、詩なのか」という問いを抱かせる所以です。本作もまた、映像詩としての完成度を持ち、評論家の間ではその芸術性が高く評価されています。
まとめ:『その日のまえに』が描いた「死」と「生」
『その日のまえに』は、単なるヒューマンドラマでもなく、社会派映画でもありません。それはむしろ、映像を通して“生きること”と“死に向かうこと”の意味を模索する一編の詩なのです。
万人受けする作品ではないかもしれませんが、大林宣彦監督の世界観や、永作博美の静かな演技に触れたい方には、一見の価値がある作品です。自分自身の「その日」を想像させるという意味で、本作は心に深く残る一本と言えるでしょう。